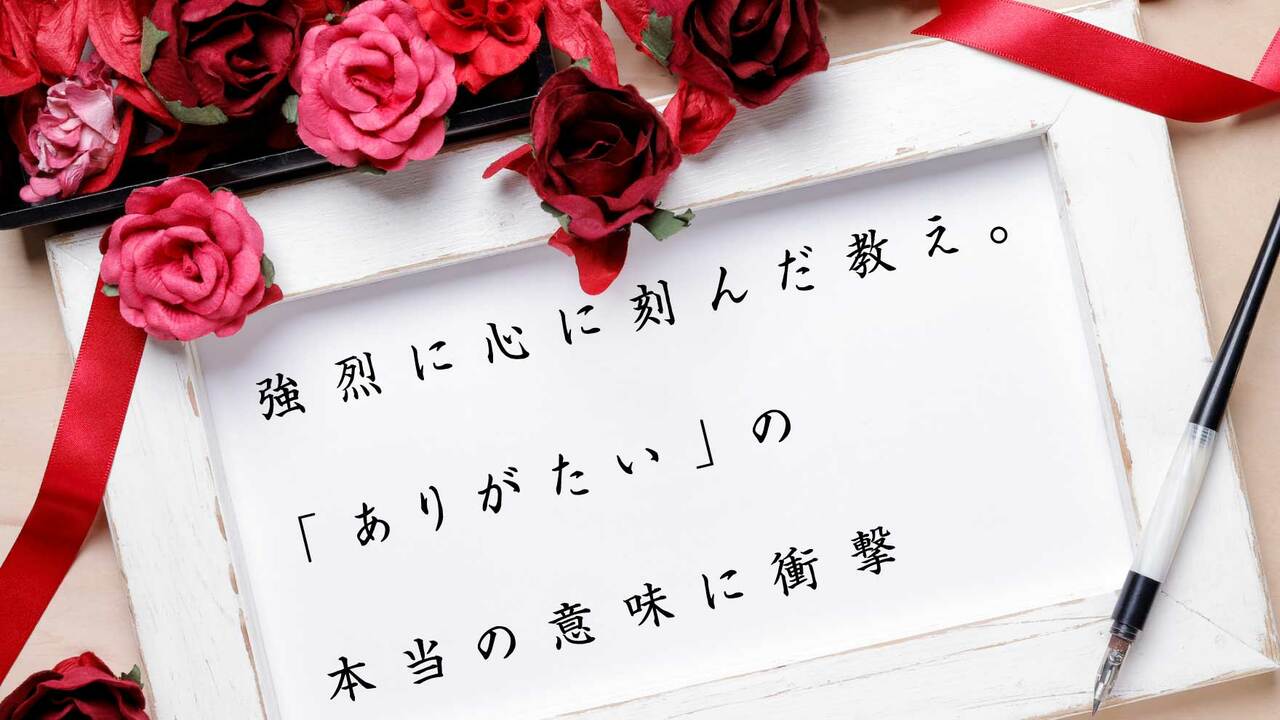時分の花まことの花
二〇一一年の東日本大震災によって、私は生まれて初めて自分が何もできない人間なのだということに気づかされ、自信のすべてを失ってしまった。そのどん底からなんとか抜け出したころ、お出しした年賀状のお返事でこの言葉を戴いたことがある。その年賀はがきには、原稿を書く人特有の、特徴のある字で一行「時分の花よりまことの花」とあった。
この言葉は世阿弥の言葉だとは知っていたし、意味も多少は理解していたつもりだったのに、そのとき、賀状に添えられた一行のこの言葉にハッとして、なにかが胸にぐさりと刺さったような気がした。
「時分の花まことの花」という言葉は、世阿弥の芸論『風姿花傳第一年来稽古條々』の上の項に記されている。世阿弥の芸論のなかでもとりわけ有名な言葉である。
この書のなかで世阿弥は能の修行について年代ごとに分けて説いている。
修行と年齢
少年時代の、姿も声もそのままで愛らしく、清らかな様子はもうそれだけで美しく、幽玄でさえあると世阿弥は言う。
たしかによくわかる。
能舞台で、六、七歳の子方が精いっぱいの甲高い声で謡ったり、その子が舞い終わり扇をしまう場所を探して袴を探るときのたどたどしい手つきを見たりすると、観客はその愛らしさに、もうそれだけで胸いっぱいになってしまう。拍手喝采したくなってしまう。
そして青年時代になると年齢に応じて整った肉体が若々しく、見よいものになる。声変わりも済み、たっぷりと出る声もそのままで十分に美しいし、人の気を惹きつける魅力は十分であるという。だが、その美しさは年齢そのままの「時分の花」だというのである。自ずとその肉体に備わった美しさだけに頼っていては、やがてそれらは失われるときがくる。
肉体や声が衰え、花がなくなる時期になって、修行を積んで克ち得てきた芸に表現されてくる幽玄の美こそが「まことの花」だというような意味だったと思う。四、五十代の中年期になって「まことの花」が備わらなくては、能役者としては望みがない、というような論旨の文章のなかにでてくるのが「時分の花」「まことの花」という言葉である。