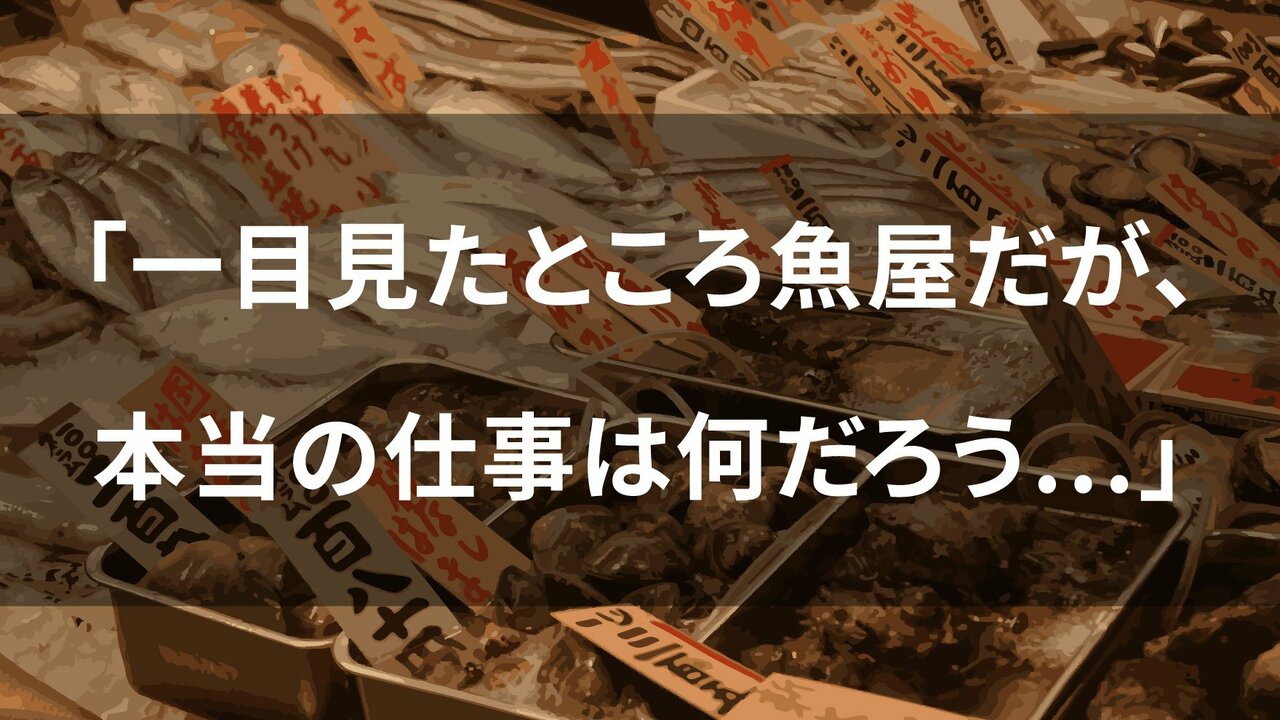どちらの男がいい人か?
「死んだって、殺されたのですか?」
「さ、朝見てみれば、背中に一突き、刺された後があったそうだ」
「そう……それとね、蔵の鍵を落していったのよ」
「フフフ、盗賊が入ったと言う証だね」
「そう……」
虎谷屋は、何か裏でやっているのかもしれない。麻衣はその時そう思った。ここに来たかいがあった。麻衣はそう思った。新之助は、まだわからないことがある。
「あの親分は誰ですか?」
「あなたが来ていてよかったわ。わたしが一人だと、必ず体を触るのよ」
「へ、そうですか。で、親分の名は……?」
「この町一体に目を光らせている、大親分なの。熊手の鍛治蔵って言うのよ」
新之助は、鍛治蔵は聞いたことがあると思っていた。会ったのは初めてだが、名前は時々聞いたことがある。たいてい大きな事件の時だ。即ち鍛治蔵がどうしたと言うことばかりだった。
「麻衣さんは、いろいろ知っているのですね」
「この鍛治蔵さんは、おじいさんから聞かされたのよ。それで、ちょっと顔見知りになったってわけ」
新之助は、麻衣はそこら辺の女とは違うと思った。裏の社会にも顔が通じている。忍びの術も知っている。ただの武家ではないのだ。だが、新之助は胸がはやるのを抑えようがなかった。
俺が欲しかった女はこういう女だ。麻衣だと確信したのだ。麻衣はまた退屈な武家生活をしていた。今日も祖父から言われた。
「林太郎が、逢いたいと申している。早く用意して行ってきなさい」
今日は、いろいろ考えることがあるのに。と思いながらも、林太郎に会いに行くのだった。今日は、数奇屋のような贅沢を凝らした料亭だった。麻衣は料亭に入ると、開口一番言った。
「わたし、こんなところはあまり好きではないのですよ」
「では、どういうところですか?」
林太郎も、今日は張り切っている。
「もっとね、こう、何というか、ひなびた温泉みたいなところです」
「ここもいいですよ。見かけは豪勢だが、ほら、ここにこんな置物がある」
と林太郎が指差したのは、何の変哲もない壺だった。
「へ、あら、これは有名な、蚊木之元博仁の作品よ」
「蚊木之元博仁は、あまりお金がなかった。だが、瀬戸物を作るのは好きだった。作っているうちに認められて有名になったのだ」「ま、よく知っているわね」
麻衣はそう言って、林太郎を見るのだった。この林太郎はしっかりしている。麻衣とは頭脳が違う。どう違うのかと言ったら、麻衣は、世俗のことに関して、いろいろ知っている。
林太郎は、武家社会のこと、すなわち世の中の進み具合に関して、知識が広いのだった。麻衣は、林太郎も大切にしなくてはならないと思った。武家社会もいろいろ知っておかなくてはならない。つかず離れず、という具合にしよう。麻衣は一人で頷くのだった。
「外に出ましょうか?」
どうもこの料亭は体に合いそうにない。
「ええ」
麻衣は林太郎と一緒に、外に出るのだった。林太郎は、どこまでも麻衣に忠実だ。
「こうして歩いていると、付近の皆さんはどう見えるでしょうか?」