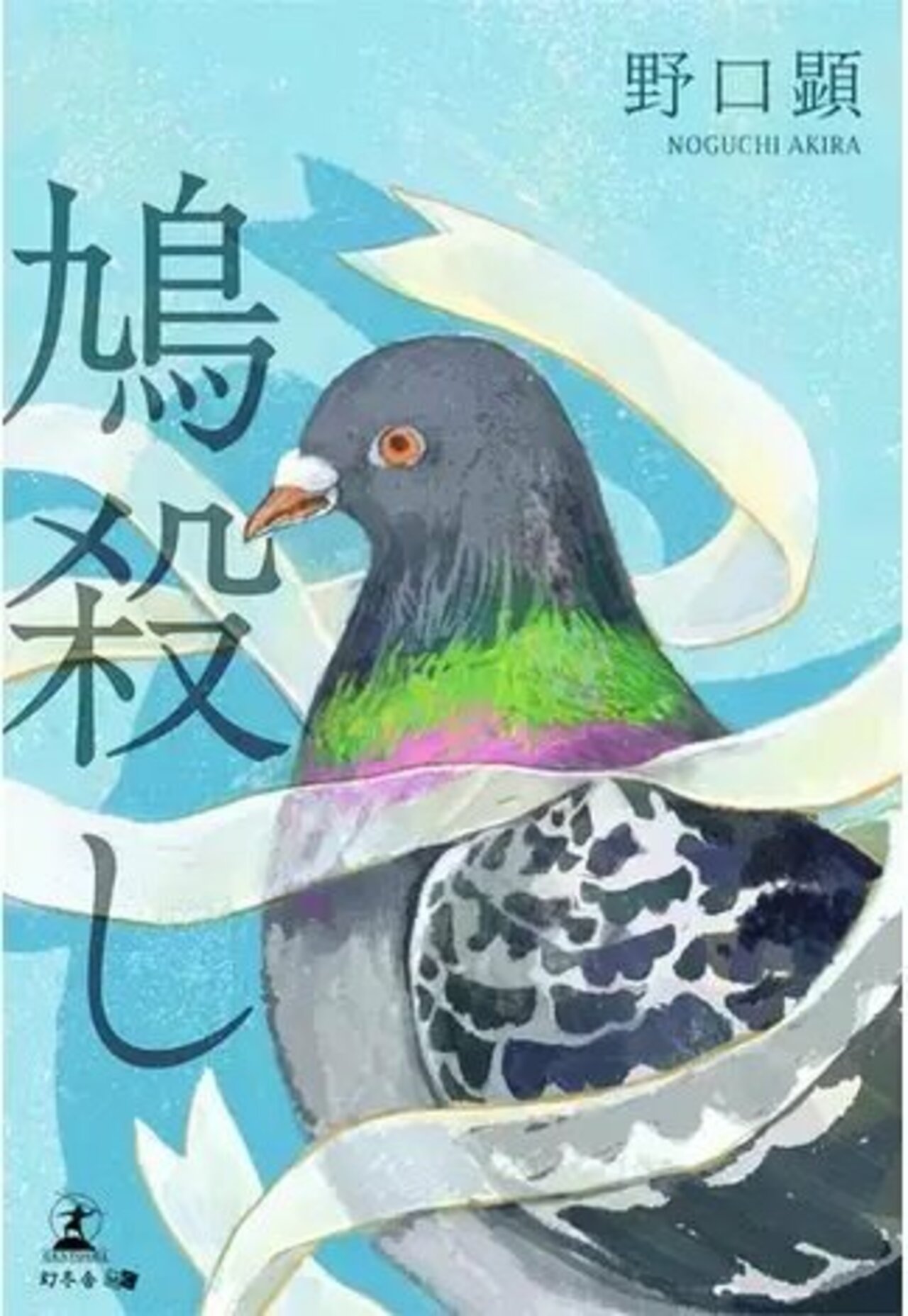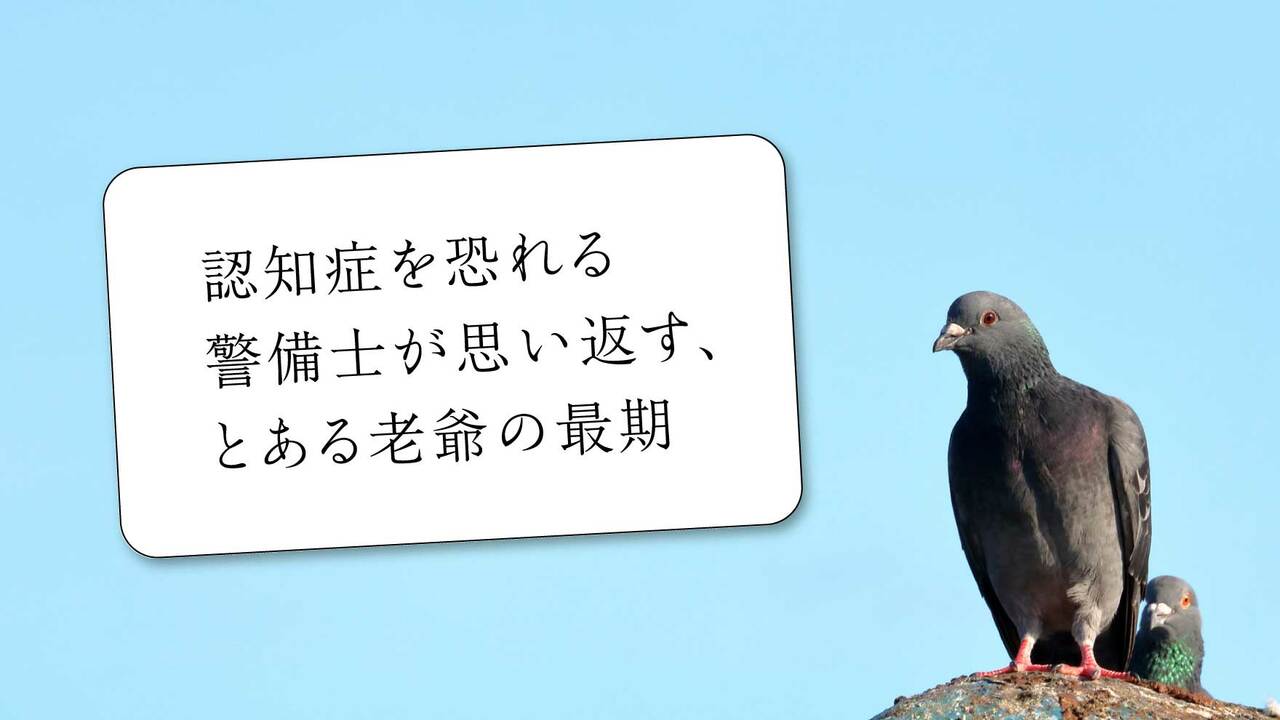「小笠原さん、小笠原さん」
公団住宅の方から叫びながら駆けてくる人がいる。大柄で肥ってゴマ塩頭をふり乱して……長谷川女史だ。私の横を、それこそ私を無視して小笠原老人に駆け寄った。
「ああ驚いた。こんなに暗くなって寒くなって、お身体に障ります。表へ出てはいけませんわ。さ、これを羽織って……」
そう言って小笠原老人の肩を抱くようにして、ゆっくり国道を歩いて行く。私はあっけにとられて、しばらくポカンとしていた。あのいつも憎々しげに睨みつけてくる三白眼の、そして口汚く罵しってくる女史の、何という変わりようだ。そういえばいつも彼女の後方についている小柄な田中女史の姿がない。
私は帰り仕度をはじめた。警備報告書に記入して自転車に乗る。走らせるとより寒い。小原係長は不在だったので課の女性に報告書を渡し、表へ出て会社に下番報告をし、自宅へ向かう。夕食をとりながら、明日の小笠原老人宅への訪問は、手ぶらでよいのだろうかと考えた。
いくら何でも初めてのお宅へ伺うのに、手ぶらでは失礼だ。いい年をしてみっともない。しかし、何を持って行ったらよいのだろう。先方の好みも何もわからない。酒を飲むのか下戸なのか。甘いものは好きか嫌いか。それに末期の肺ガンであれだけ弱っていらっしゃる。普通の食物を受けつけるかどうか。深く考えずに老人の招待を受けてしまったが……。何を持って行ったらよいのだろう。手土産でありさえすればよい、という気にはなれない。風呂へ入ってベッドに横になる。また、あれこれ考えてみるが答えが出ない。そのうちすっかり眼がさえてしまって、眠れなくなった。
三.スープが冷める距離
第六日。前の晩寝そびれて、テレビを見たり本を読んだりしているうちに、窓の外が明るくなってきた。私は思い切って公園へ行ってみることにした。ラジオ体操をやっていた。そこから私の基地は離れているのでリュックサックを置いて制帽をかぶろうとした時、公団住宅の方で何か音がした。
見上げると、二階の右から三番目の部屋のドアが半開きになっていて、誰かが外をのぞいている。一度部屋に戻ってそれから小柄な人が出て来ると、小走りに建物の右端の階段を上がって行った。その人物が誰だかわかったと思う。あの長谷川女史の後ろにいつも居る田中という老婆だ。
彼女が出て来た二階の右から三番目は、確かあの大村という男の部屋だ。合点がいった。大村と田中女史は男女の仲なのだ。私は大村の顔を思い浮かべた。そして田中女史も。二人には申し訳ないが、何となく薄汚れた感じがする。嫌だ、私は頭の中から見たこと思ったことを追い払った。