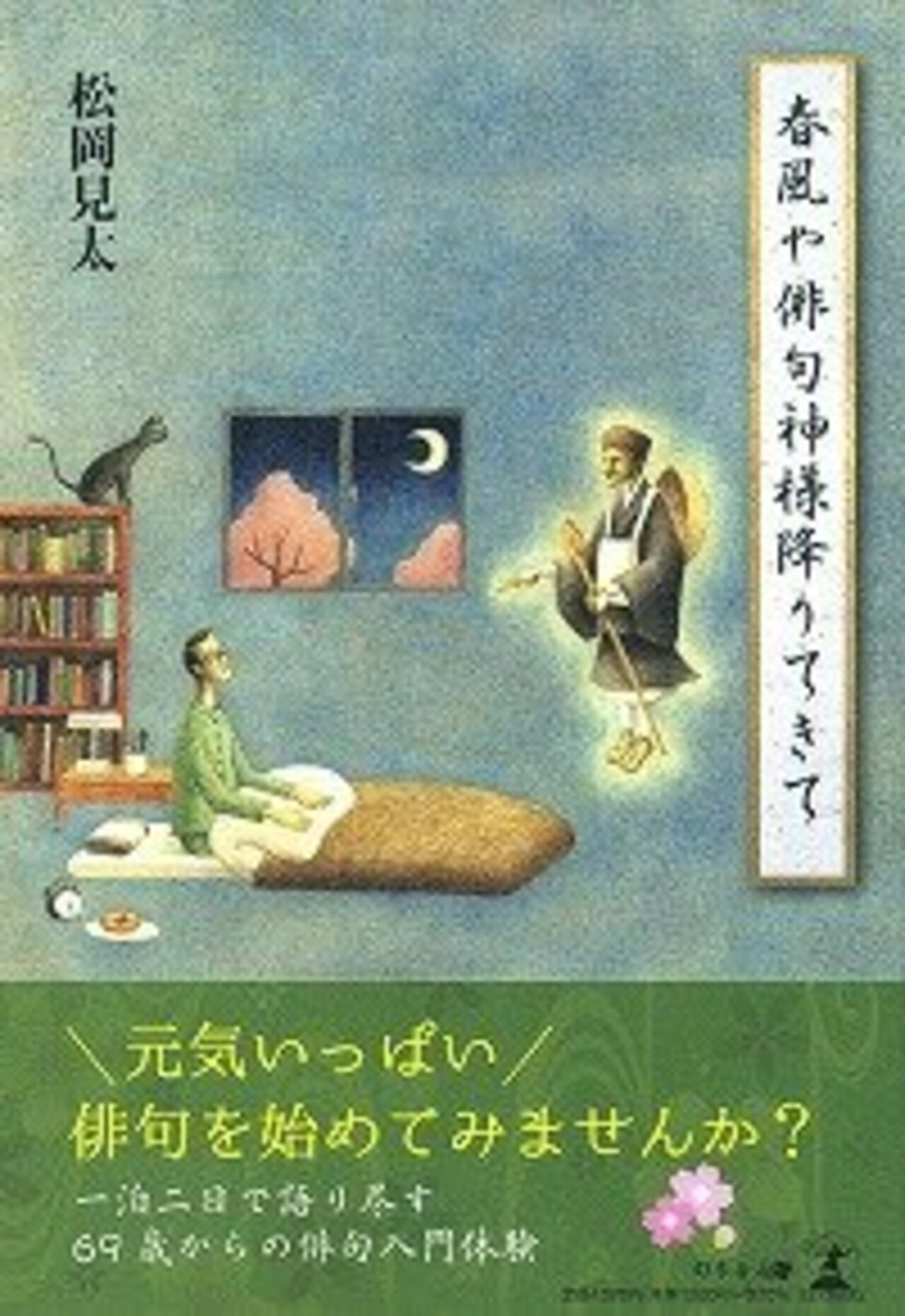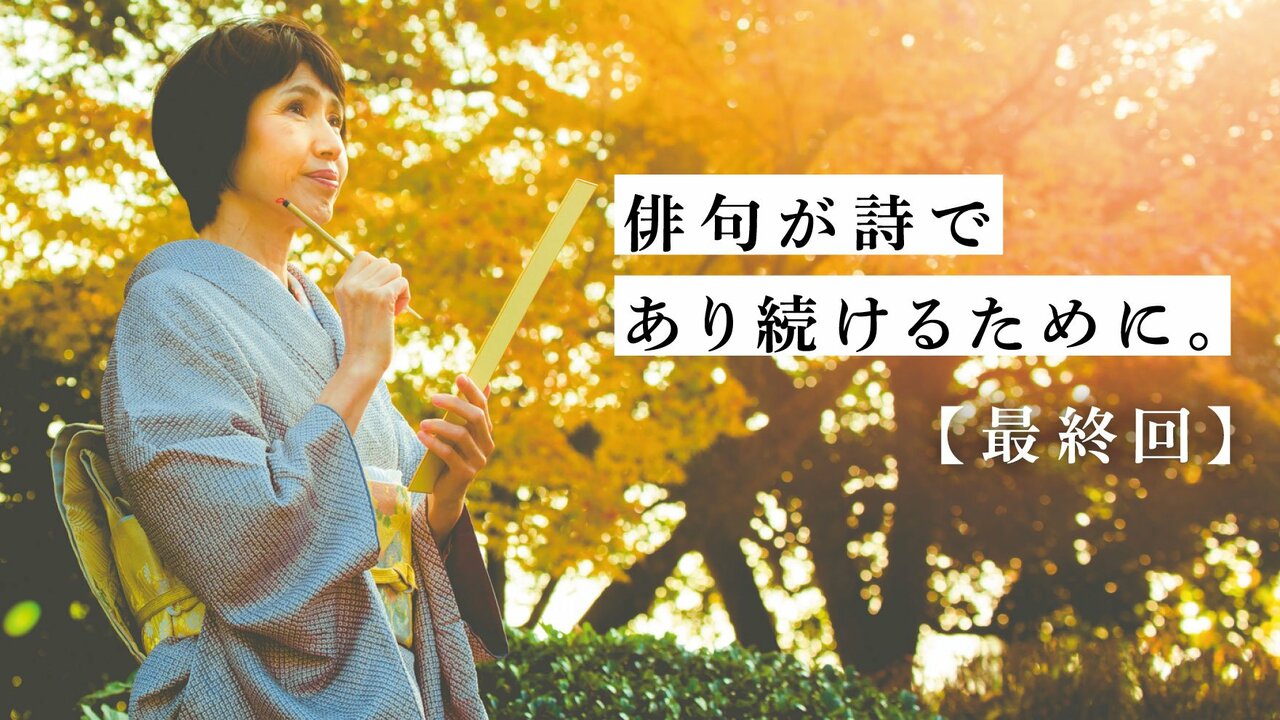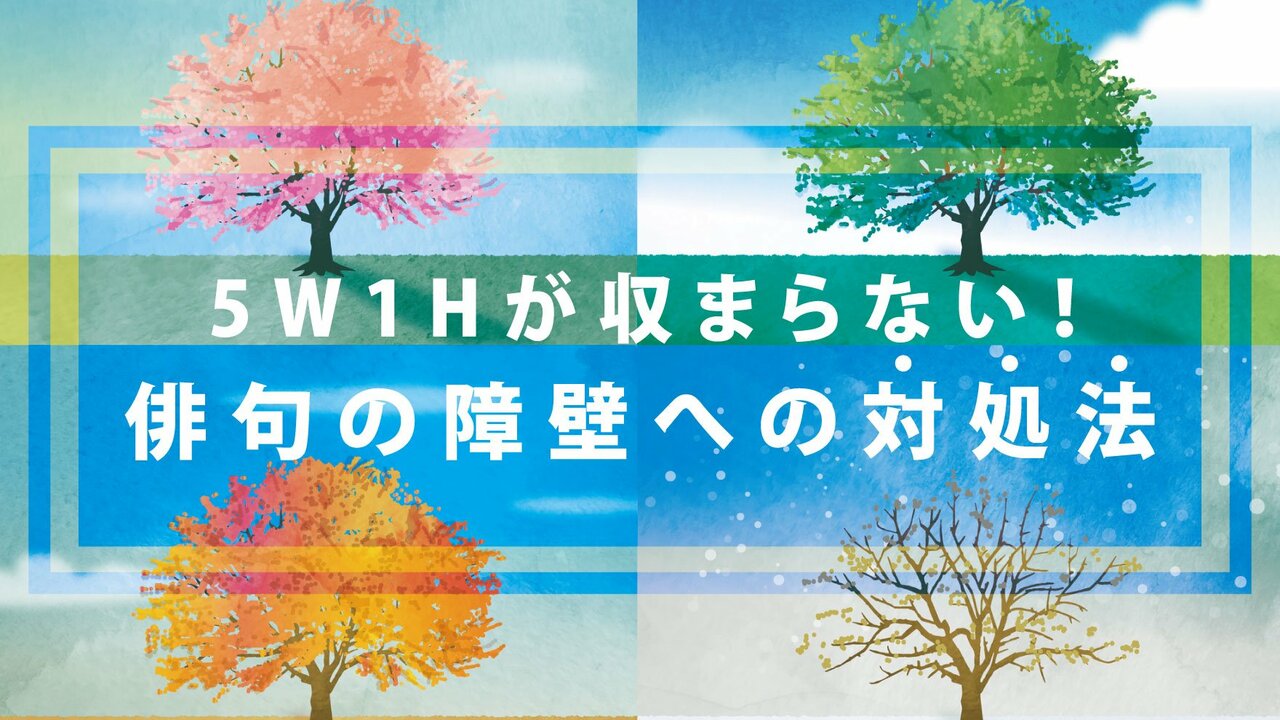神様の俳句講義 その四 うつぷんを(鬱憤は歴史的仮名遣いで『うつぷん』と書く)
四度目に神様に会ったのも、いつもの散歩道だった。五十代、額が広く鼻の下に髭を蓄え、職業は自由業のおじさんのようだ。
「久しぶりに、東京に来てみたが、新型コロナウイルスの流行でみんな元気がないな。昔のスペイン風邪を思い出すなぁ」
神様は、口元に皮肉な笑みをたたえて話しかけてきた。
「こんなはっきりしない時こそ、スカッとした俳句が欲しいものだ」
「例えば」
という私の問いかけに、三分間ほど口中でもぞもぞ言い、一分ほど空を見上げてから
「『うつぷんをはらせ乙女の荒神輿』でどうじゃ」
「女の神輿は見たことがないです。若衆や子供の神輿ではいけないのですか」
「それはいかんな。うっぷんの溜まった世の中だからこそ、色気のあるいい女、それも若い乙女でなければならぬ。娘たちは外出自粛で好きな男に会えず、大好きな濃密接触が不可能、さらに旨いパスタやスイーツが食べられず、かなりストレスが溜まっている。若いだけに、フェミニンマグマの圧力は相当なものだ。
だから、神輿も荒神輿になる。揃いの白い股引から伸びた脚が汗に光って妙になまめかしい。コロナウイルスも久米仙人のように、退散せよ」
ちょび髭のせいか、中年男のいやらしさがやや垣間見えたが、怪しいおじさんではなさそうだ。プラス面を言えば、発想がかなり柔軟で、大胆な感じだ。
「これから神戸に行くので」
神様は紫紺のソフト帽にそっと手を添えて、姿を消した。家に帰り手元の俳人アルバムで調べたら、私の予想通り、西東三鬼だった。今回の神様は、ルックスも言動もユーモアにあふれていた。
『乙女の荒神輿』という発想が面白かった。俳句の神様は毎回異なったコスチュームで、異なる人物となって私の前に現れる。そのサービス精神に感心するとともに、俳句作りに苦しむ私へ、作品を提供してくれることに、感謝するばかりだ。
うつぷんをはらせ乙女の荒神輿
水枕ガバリと寒い海がある 西東三鬼