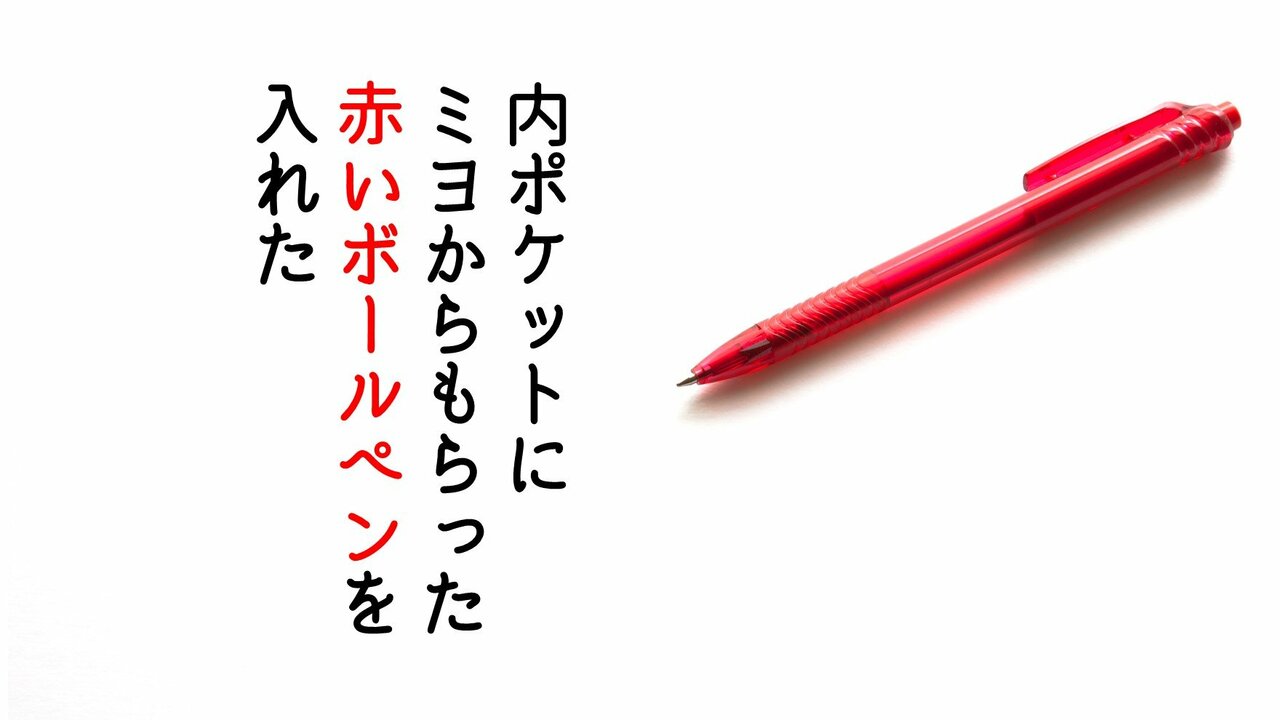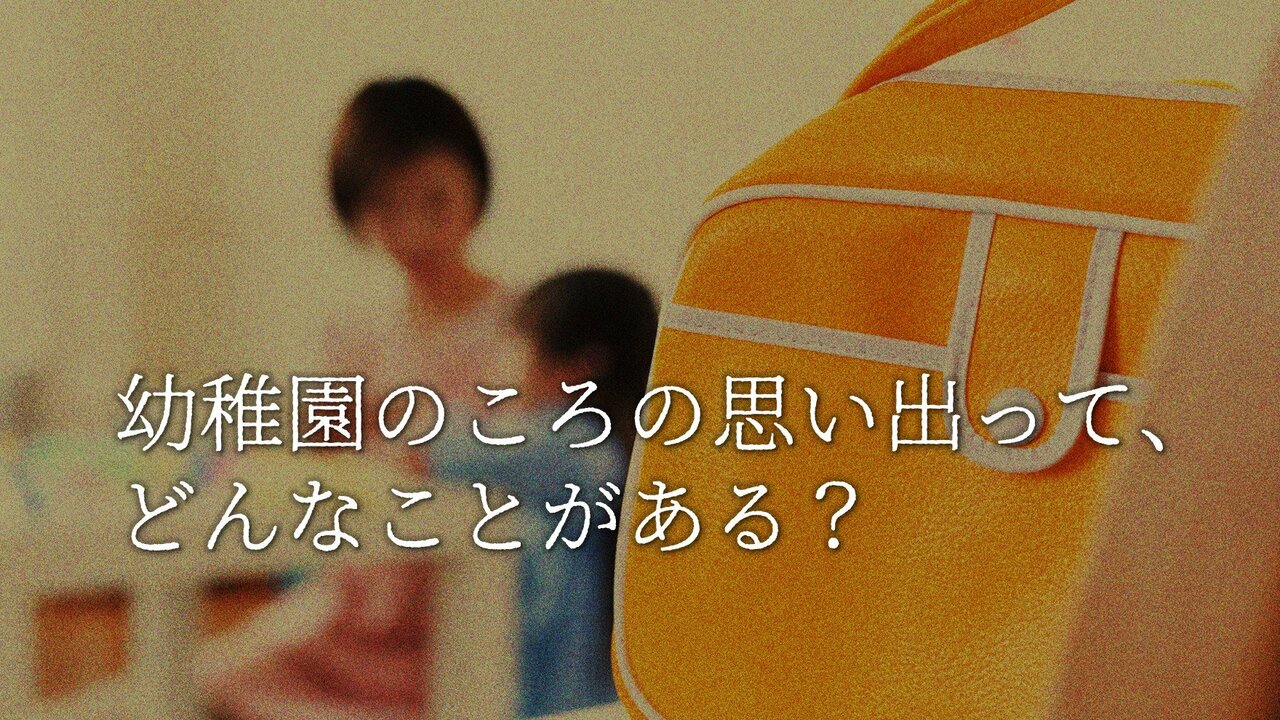第一章 赤い光
これまで夢についてなど考えたこともなかった。部活三昧(ざんまい)の平凡な中学校生活を送ってきた達也にとって、スケールの大きすぎる問題だ。
「これといって特に。すみません」
「謝ることなんてないさ。まだこの時期は夢どころか志望校も決まっていない生徒の方が多いくらいだからな。ただ、おぼろげながらでもやってみたい仕事やなりたい自分のイメージがあれば、いくつか学校を紹介できるかもしれないと思ってな」
これまでやってきたことは、自分の未来につながっているのだろうか。達也は全く想像できずにいた。
「先生は中三の時、どんな夢があったんですか?」
「中三の時か。そうだなあ。当時、憧れの先輩がいてな。とてもきれいな人だった。その先輩と同じ高校へ通うのを夢見て猛勉強していたのを今でもよく覚えてるよ。まあ、入学後フラれちゃったんだけどな」
春口は少し気恥ずかしい様子だ。
「そうだったんですね、先生になろうと思ったのは、なぜなんですか?」
「まあ、いろいろあってな」
春口は腕時計に目をやる。
「いかん斉藤。もうこんな時間だ」
達也が職員室の時計に目をやると、十時を回っていた。
「長く引き留めてしまって悪かった。来週から各高校で学校説明会が始まるんだ。次回、資料を準備しておくよ。受験まであと半年だが、斉藤の場合、いろいろな学校を見ておいた方がいいと思う。志望の動機につながるきっかけを得られるかもしれない」
春口と外にでると、日中の暑さはない。夜風が秋の訪れを感じさせる。
「じゃあ、気をつけて帰るんだぞ。お家の人には連絡をしておくから」
「はい、さよなら」
春口に見送られ、達也は駅まで急いだ。達也は松本駅のプラットホームで電車を待ちながら、将来の夢について考えていた。何気なく向かいのホームに目をやる。
その時だった。一瞬、時が止まった。電車を待つ人でいっぱいのホームで、セーラー服の少女が瞳を閉じ、色白の顔を縁取る、つやのある長い黒髪をゆっくりと耳にかけようとしている。胸元の赤いリボン、銀色に見えるのは校章だろうか。
よく見るとわずかだが、彼女の体がほんのりと赤く光って見えた気がした。彼女は涼しい表情で時間を気にしている。達也はもう一度目を凝らした。
電車がホームに入り、ドアが開く音で我に返ると、達也はあわてて電車に乗りこみ、また彼女のいるホームへ目をやった。しかし、彼女の姿はどこにも見当たらない。高校生だろうか。どこの学校の人だろう。
気にすればするほど、心臓の鼓動が耳の奥で聞こえる。達也には初めての感覚だ。電車の窓から見える空では、星が輝いていた。汗ばむ肌に秋の気配を感じる夜のことだった。