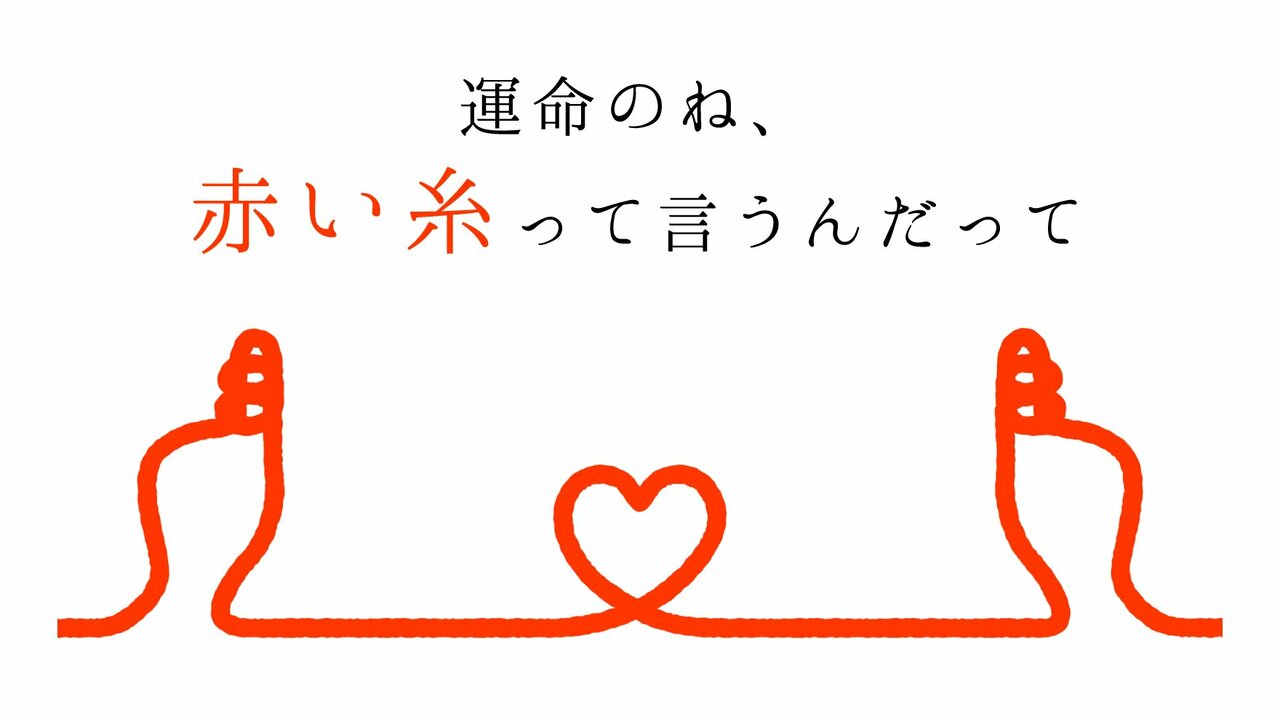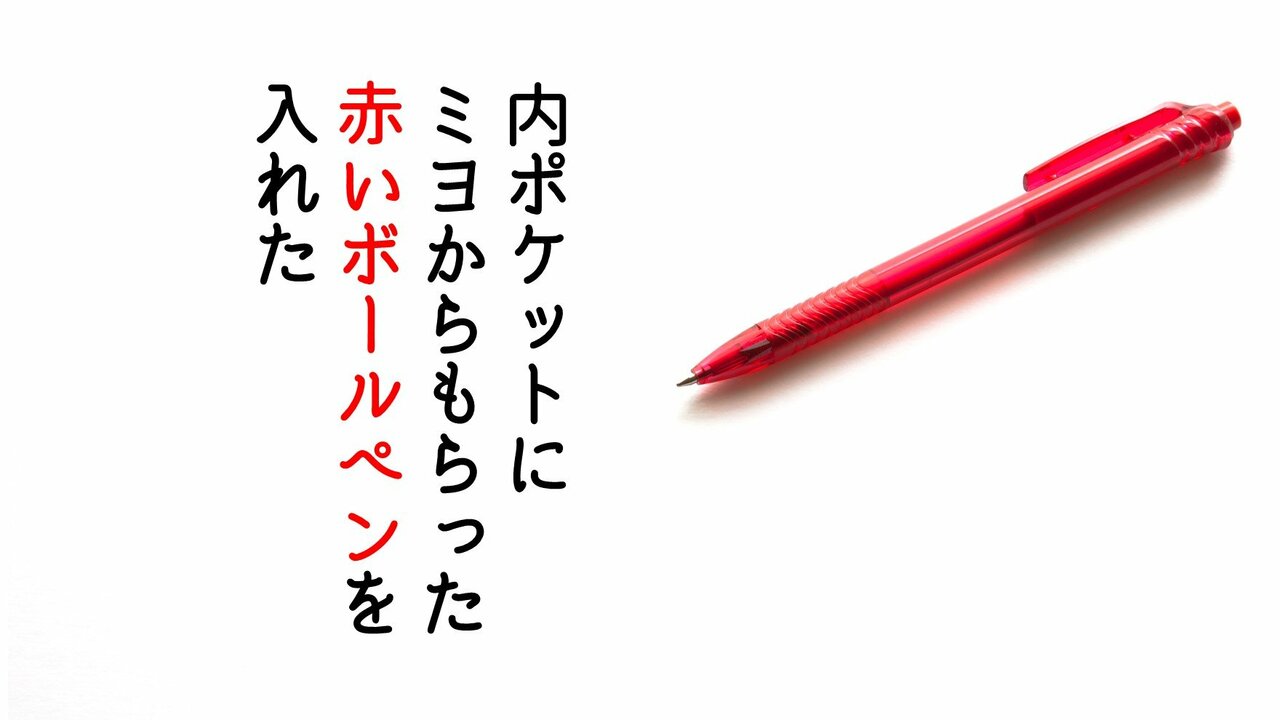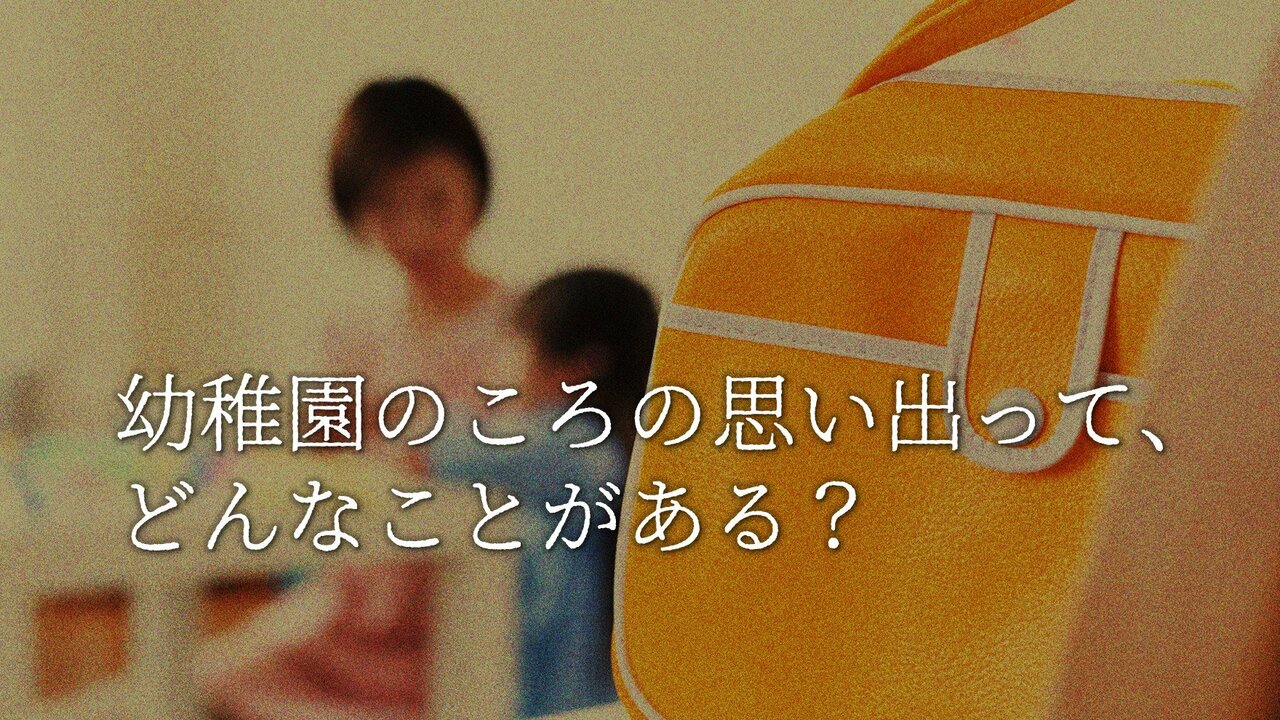第二章 希望
紅葉した葉が太陽の光に輝いている。木漏れ日が射しこむ教室で、二人はその日もいっしょだった。女の子は画用紙に「空」を描きはじめた。
時折、耳にかかった少女の黒髪に秋の陽光がたわむれて、つややかなさざなみが走っていた。空の下には男の子と赤いランドセルの女の子の絵が描いてある。女の子は赤いクレヨンを男の子に優しく手渡した。
真っ赤な太陽を描こうと誘う。男の子の汗ばむ手のひらに、クレヨンに巻かれた紙がふやけていく。完成を目前にしたその時、赤いクレヨンは真っ二つに折れてしまった。
思わず手を開くと、いくつかの小さな欠片(かけら)が画用紙の上に飛び散った。男の子はあわてて拾おうとするが、画用紙にその赤い色がこびりつき、絵の中の女の子の顔や首、腕、膝は赤く染まってしまった。
声をあげて泣く男の子。すると女の子は自分のバッグをガサゴソと探しはじめた。女の子の顔がパアッと明るくなる。ゆっくりと画用紙に近づくと、バッグから取り出した赤いクレヨンで絵の中の二人の小指をつなぎ、男の子に微笑んだ。
「運命のね、赤い糸って言うんだって」
「ウンメイ?」
来春、小学校へ進学する女の子は、自分が先に卒園してもお互いずっと忘れない印だと言う。女の子は、右手の小指を笑顔になった男の子に向けた。男の子もまた女の子の小指に自分の小指を絡めた。
「たつや……」
微かに自分を呼ぶ声が聞こえる。やっと迎えに来てくれた。声がする方に気持ちが引き寄せられていく。
「……起きなさい。達也! いいかげん、起きなさいよ!」
勢いよく体を起こして、目を開けると不機嫌そうな母の姿があった。
「いつまで寝ているのよ。あなた、今日は早く学校行くんでしょう? きちんと自分で起きなさい。試験の時、困るわよ」
母はそれだけ言うと、部屋をあとにした。
「なんだろう、前にも同じようなことがあった気がする……変な夢だったな」
十月のある日、達也は朝早く学校に向かった。安曇野(あずみの)市立穂高第二中学校。中二の四月に達也はこの学校に転校してきた。公立の学校だが、生徒の九十パーセント以上が運動系、文科系いずれかの部活に所属している活発な学校だ。
達也もすぐにバスケット部に入部し、中三の最後の大会まで熱心に練習を続けた。時刻は七時を少し回ったくらいだが、今日も後輩たちが練習に励んでいるようだ。達也はホームで見かけた不思議な少女のことがどうしても気になっていた。
どの学校に通っているのだろうか。手がかりは制服だけだが、図書室で調べてみようと、鍵を借りるため職員室へと向かった。まだ誰もいないワックスがけされた廊下を一人歩く。上履きの音がまるで新品のボールをていねいに磨いているように響く。
頭にチラつく少女のことを思った時、背中にふと視線を感じた。振り返るが、朝日が射しこむ廊下が続いているだけだった。職員室から男性教諭の声が聞こえる。二回ノックして職員室に入ると、バスケ部の顧問である木嶋(きじま)が上履きをバスケットシューズに履き替えているところだった。
「失礼します」
「斉藤か、おはよう。こんなに朝早くからどうした?」
「おはようございます、木嶋先生。実は進路について調べたいことがありまして」
「そうかそうか。斉藤もいよいよ受験生らしくなってきたじゃないか」
相変わらずハイテンションだ。特別おもしろいとは思えないことにも必ず豪快に笑うのが木嶋だ。朝が弱い達也もこの大きな笑い声で目が覚め、練習に取り組んだものだ。