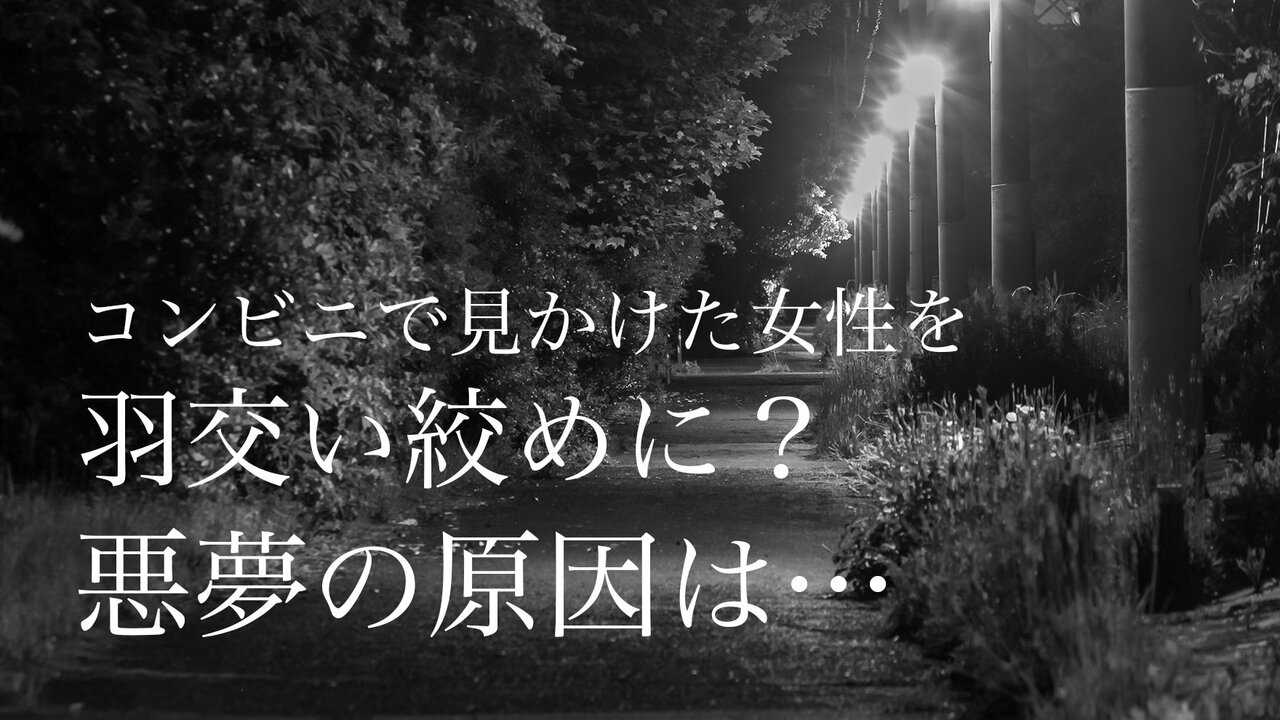双頭の鷲は啼いたか
いつしかタケルは深い眠りにまた落ちていた。
それは先ほどの帰り道と同じく、タケルはつめたい夜風に吹かれながらひとけのない高架下、雑草だらけの路地を歩いていた。
前を歩いているのはあの女性なのか? 白いブラウスに黒いカーディガン。紺色の長めのスカートを着てキャメルのコートを羽織っていた。すれ違いざまに声をかけた。
「こんばんは」
「…………」
警戒する女性は身を固くした。
「先ほどハンカチを落としたでしょう?」
花柄のハンカチを差し出す。そのあとは何も言わずに歩みを速めて彼女を抜き去ってゆく。怪しい奴だと思われないように。
「あの、これ……私のではありません」
その女性は少し後ろから声をかけてきた。
「あれ? あなたがコンビニから出た時、座っていた場所に落ちていたので」
「違います」
「じゃあ、僕がまた、あのコンビニに行った時にでも届けておきましょう。誰か探しているかもしれない」
タケルはそう言うと、女性の真横に立った。そして、そのハンカチを受け取りざまに、彼女の細い手首をそっと掴んだ。トンネルの少し手前、人通りはなく明かりも民家もない。
彼女はとても驚いた顔でタケルを見たがもう遅かった。その瞬間に羽交い絞めにした彼女の首筋には銀色の薄いナイフがあたっていた。
軽くスライドした瞬間に彼女は声を出すこともなかった。驚きと恐怖の入り混じった表情から、その瞳は焦点を失い、凍りついた表情に変わった。鮮血が彼女の上半身を覆う。
膝からガクンと倒れそうになるところを、左腕で彼女の細い腰を抱き留める。そして、土手の草むらにそっと座らせてみた。まるで儀式のいけにえが佇んでいるかのように、細いきれいな脚を伸ばした。
コンビニでは顔を見ることはなかったが、とても美しい顔立ちをしているじゃないか。彼女の血はさらさらとしていて、まるでただの赤い水のようだ。
あのハンカチでナイフと手をぬぐうと、そのまま横を流れる川に捨てた。彼女の部屋には誰か待つ人がいたのではないだろうか。
なんだかきれいなユリの花でも折ったような気持ちになり、罪悪感ではない、高揚感でもない、言いようのない不思議な感覚を覚えた。
そして、タケルは右手に彼女の髪を掴んでいた、まるで絹糸のようなきれいな髪だった。
「うわっ!」
タケルは右手を大きく布団から突き出して、がばっと起き上がった。ひんやりとした部屋で洗濯機の終了を告げるブザーが鳴っていた。
右手を恐る恐る見た。血糊はおろか、長い黒髪もついていない、きれいな僕の手。
そう、夢だ、すべては夢だった。昔の彼女との別れを連想させた夢の続編みたいな、だが自分が殺人者になってしまうなんて。
ショッキングな内容に、のどがカラカラだった。まだ二月の下旬、気温は低く部屋は冷え込んでいた。