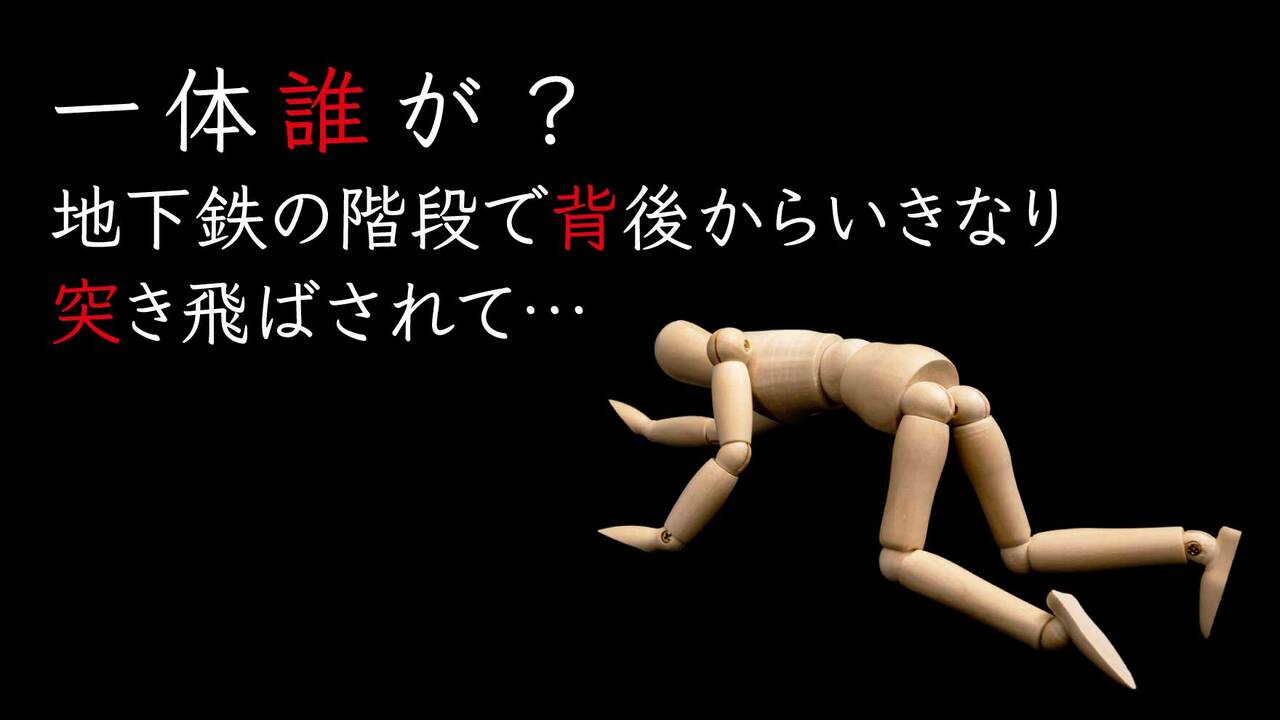双頭の鷲は啼いたか
人当たりの良いチーフとして仕事をこなしていた時、秋元さんに話しかけられた。
「チーフ、昨日の夜九時に、烏丸御池の交差点角のコーヒーショップにいましたよね」
大きな瞳が印象的な秋元さんが、周りに誰もいないことを確認して言った。
「いや。その時間まだここで仕事していたはずだけど」
「ですよね……私達は七時で帰ったじゃないですか。そのあと、友達と待ち合わせしていたら、古谷さんそっくりな人が女性とガラス越しにおられたのを見たもので。八時前かな」
言葉を選んでいるが、冗談ではないようだった。
「他人のそら似だよ。そんな時間に終わらないのを知っているよね」
答えながらタケルは苦笑した。
「ですよね、すみません。つまらないこと聞いて」
タケルが少し笑うと、秋元さんも笑った。仕事では厳しい子だが、普段はかわいい女性だ。きっと素敵な彼氏がいるのだろうな。
自分には縁のない話だ。だが、タケルは本当にそれが自分だったら楽しいだろうにと、内心は自分に似ていた男性に嫉妬した。街で若い女性とお茶や食事でもしてみたい。
付き合ったりすることなく、友達でいいから、本当は封じ込んだ女性への不信感を払しょくしてくれる出会いを望んでいるのかもしれない。
所詮、またボッチ飯の毎日がやってくる。仕事が終わると、悲しいかな誰とも話すこともない。地下鉄を降りて階段を上がる足が重かった。
他にもサラリーマンや若い女性などが家路を急ぐ。雑踏の中でタケルはその中にいるかもしれない、自分に似た誰かを無意識のうちに探していた。この世には同じ顔をした者が三人いるというではないか。
タケルが地下鉄の階段を急いで降りていた時だ。
タケルは急に後ろから背中に誰かの両手を感じた、軽く、掌と指がポンとタケルを押し出した。と同時にすぐ下の数段を転げるように落ちた。とっさに以前手術をした頭を両腕で庇った。
「!」
下まで落ちることがなく、踊り場で止まった。数段落下しただけで済んだ。周りの中年男性が驚き、
「大丈夫ですか?」
と声をかけてくれた。
「すみません」
タケルは手にもっていたバッグを放りださなければ、頭を強打していたかもしれない。右肘を少しぶつけたようで、痛みを感じた。
二年前の事故に比べたらこんなものなんてことはない。さすりながら自分のバッグを探した。更に先に黒い手提げのバッグはあった。
何事もなかったように、たくさんの人々が行き交う。世の中はスピードを上げて変化している。人ひとり倒れたときに声をかけてくれる人が一人いただけでもありがたいと思った。
タケルは察知していた。自分がつまずいたりしたのではないと。明らかに誰かが故意にタケルを突き飛ばしたのだと。だが、人の流れはまるで今の出来事を無視するかのように同じ場面を繰り返していた。
男も女もみんな年代も違うのに同じ顔に見えるのは何故だろう、自分が時の速さから脱落しているから?
液晶広告の所に背中をついたタケルは、カバンを取り上げポケットからハンカチを出して軽く拭いた。
スマホは壊れていないだろうか、上着の内ポケットから出した。よかった、割れていなかった。なんだ、この不穏な気持ちは。鳥肌が出るほどの明確な悪意がタケルを確実に狙ったはずだ。
僕が何か狙われるようなことを?
思い当たることもない。周りを見回しても先ほどと違う人の波が慌ただしく交差するだけだった。立ち尽くしても、状況は変わらない。タケルは再び動き出した。