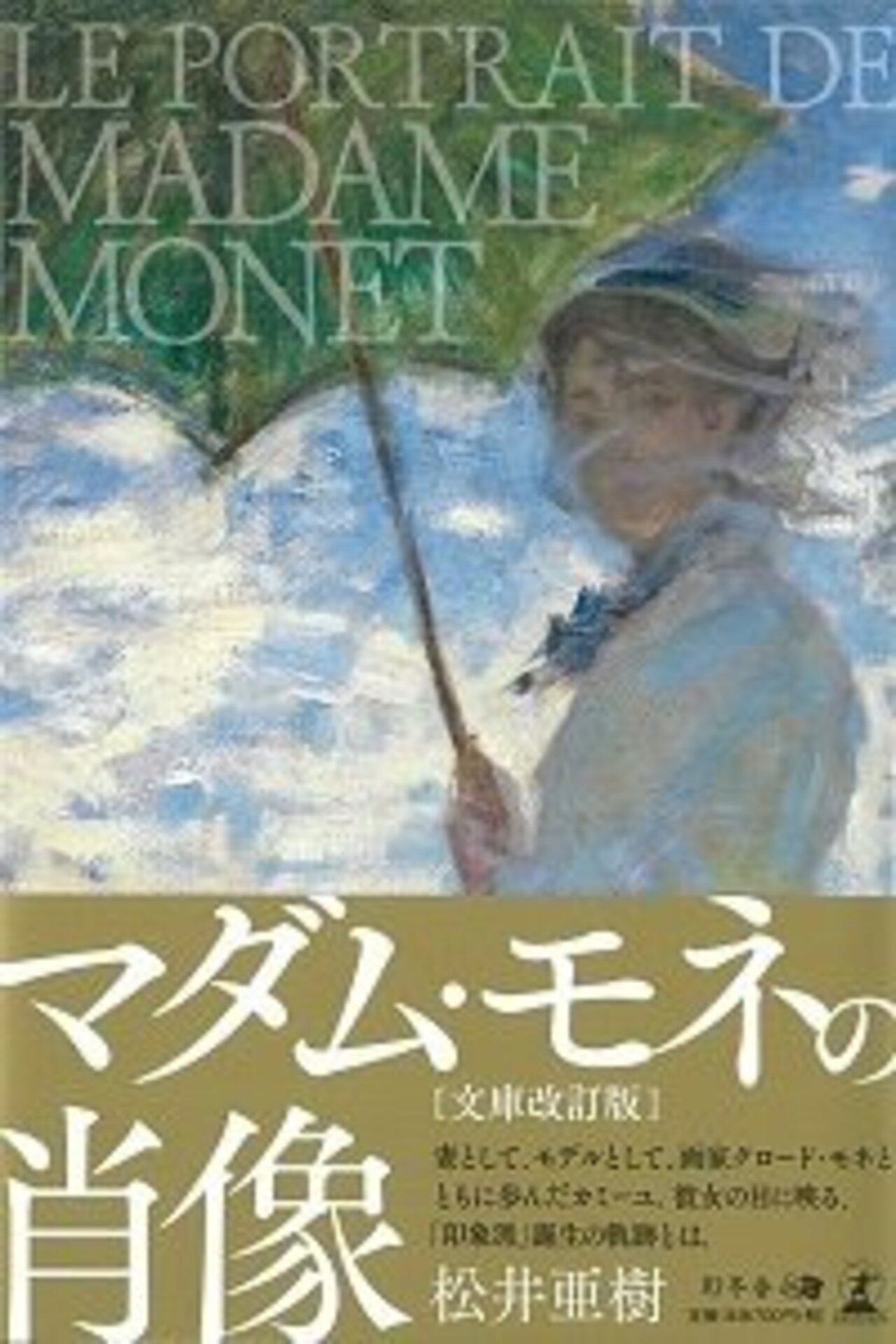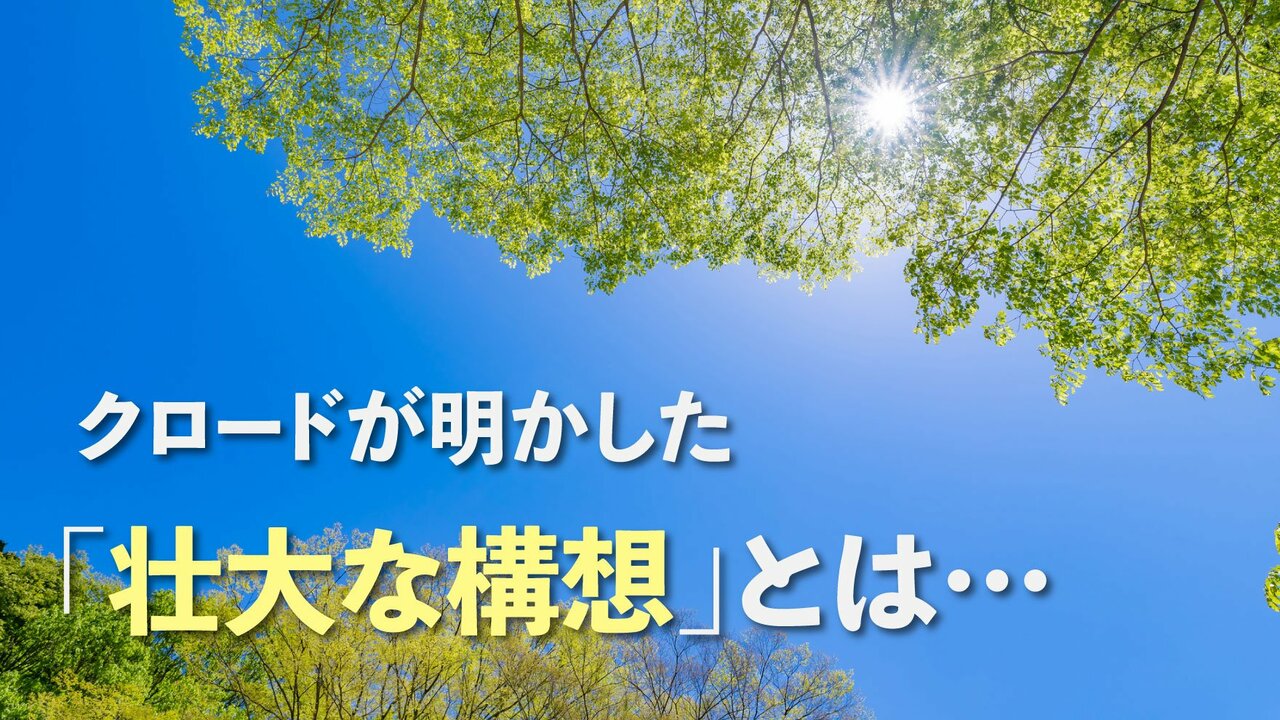「泣けるわけがないだろ、十六の男がさ。僕はママンが死んでも泣かなかった。自分が嫌で、もう何もかも嫌で、学校も辞めた」
クロードは泣いていた。カミーユの肩に額を預けて。あのときママンが死んでも泣かなかった。そんな自分を心の奥で責め続けてきたのだろう。死んだママンのために、今ようやく泣くクロードの頰を、カミーユは思わず両手でギュッと包み込んだ。二人はそのまま唇を重ね、初めての夜は、ただ夢中のうちに過ぎた。
翌朝目覚めると、クロードはすでに起き出していて隣にはいなかった。カミーユは、どんな顔をして彼に「おはよう」と言えばいいのかわからなかったから、つかの間ホッとした。この朝日の中で、昨夜のことを一部始終思い出す勇気はない。
でも、最後にクロードが耳元で囁いた「ジュテーム」だけは、もう一度味わっておきたかった。目をつぶってもう一度だけ。その言葉の記憶は、みるみる体中を幸福感で包んだ。これからずっとこんな日が続くといい。さあ、クロードに「おはよう」と言わなくちゃ。
体を起こしかけたところへ、すっかり身支度も整えたクロードが顔を出した。
「森へ行くぞ」
それ以上、わだかまりを感じる暇もなかった。カミーユは慌ててベッドから降りながら、昨夜の余韻など微塵もないクロードに少しがっかりした。でも、大切なのは制作。クロードの構想を実現することが旅の目的だ。
それは、カミーユにとって冒険の始まりのようでもある。二人して宿のドアを開けると、心のどこかが躍っていた。クロードは、森の中をすごい勢いで歩き回る。ある場所で立ち止まると、向きを変え位置を変え、しばらく辺りを眺めては、また勢いよく歩き出す。
一緒にいるカミーユの歩調などまるで念頭にない。カミーユはドレスの裾を持ち上げ、足元を確認しながら歩く。時折、裾に絡まる草を払い除(の)けていると、クロードはもう何十メートルも先を歩いている。ふと曲がって視界から消えてしまうこともある。付いていくのが精一杯。森の中で一人になるのも心細くて、息を切らしながら付いて行った。