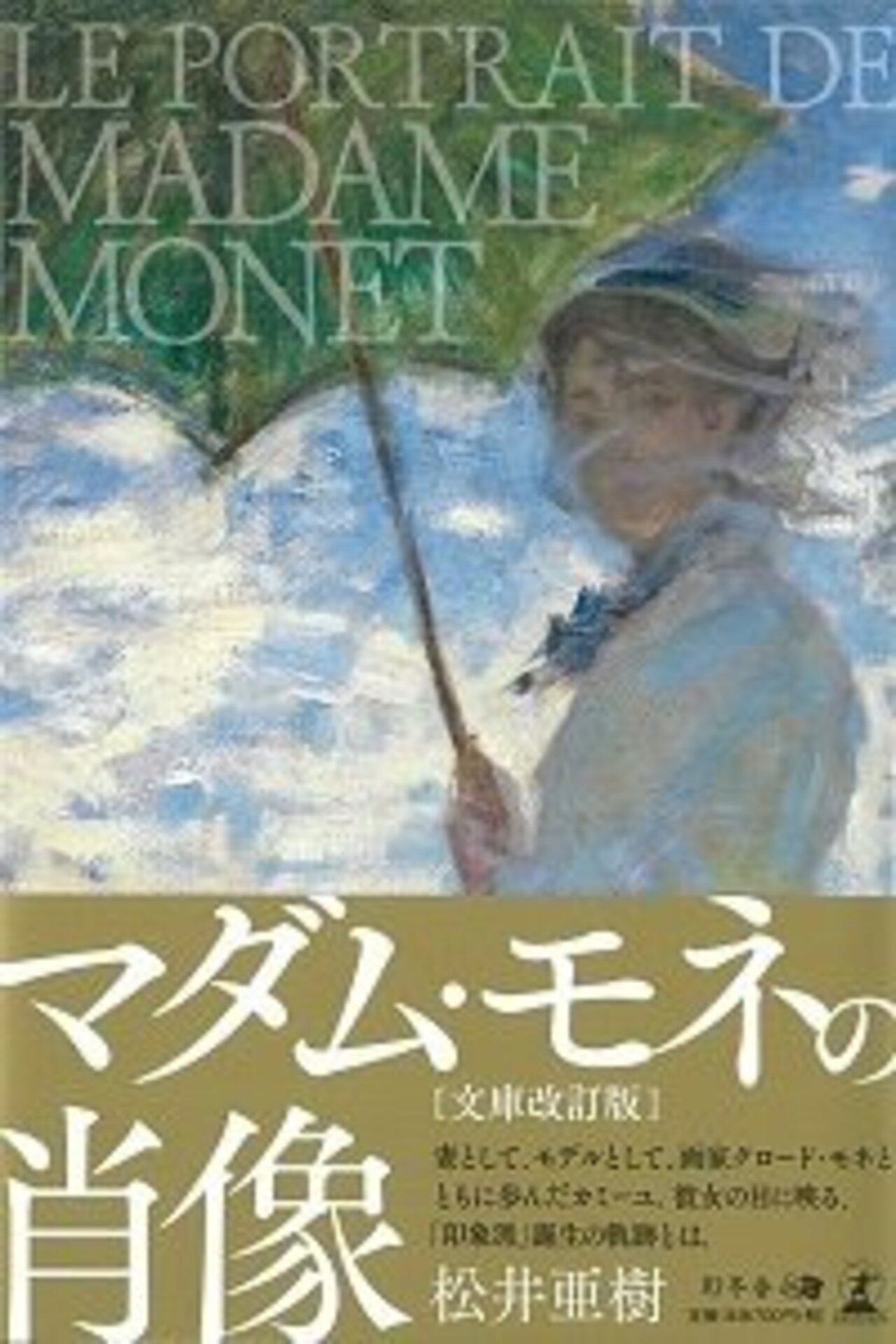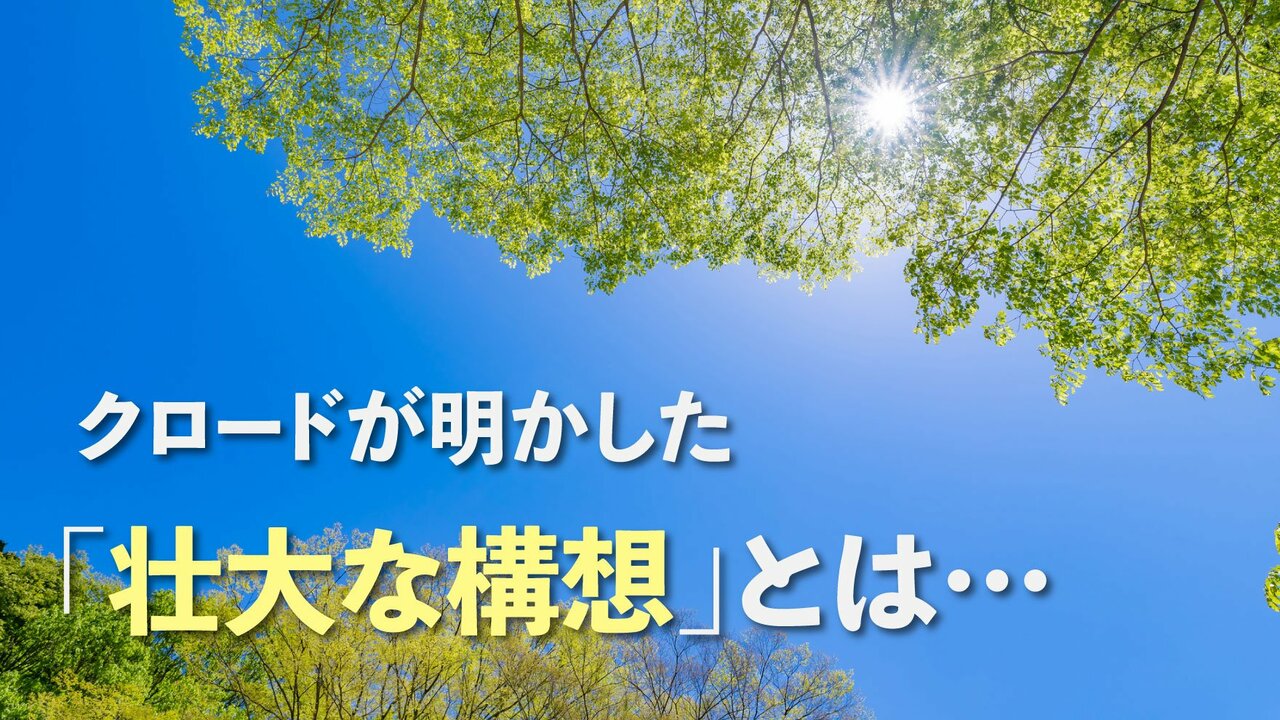デート
今日は、黒いチョーカーに合わせて水色のドレスを選んだ。このドレス、彼と一緒に歩く女としてふさわしいかしら。
初めて会ったときからクロードは、お金もないくせにいつも上等な服を着ている。今日着ているチャコールグレーのスリーピースは、ジレだけが同系色のチェック柄というおしゃれなものだ。着る物でさえ、自分の美意識を決して曲げることができない。わがままな自信家。
私を描いているときも、こちらを見ていながらいつも私なんか見ていない。そう、大切なのは、自分がパレットから取る色、筆が落ちる位置、形づくられる姿。思い出しながら、カミーユは小さく笑った。そんな彼が好き。
クロードの腕に添えた指先にほんの少し力を込めてみたけれど、彼は何も気づかないようだった。クロードに遅れないように、歩調を合わせながら歩く。こうして二人腕を組んで歩くのはまだ不慣れなことが、周りの人たちには悟られているような気がした。ルーヴルのサロン会場への入り口は観覧者で溢れ返っていた。
この当時、サロンは民衆が芸術に触れるほとんど唯一の場で、高級な娯楽の一つである。皆が貴族のように着飾り、紳士淑女の顔をして会場内を歩き回っている。一日に一万もの人が訪れることもあった。ようやく会場内に入ったものの、クロードとカミーユは人だかりに阻まれてなかなか絵に近づくことができない。
やっと、アトリエで慣れ親しんでいた絵が人の肩越しになんとか見える程度に近づいたとき、クロードが「お」と言葉にならない声を発した。
クロードが『引き潮のラ・エーヴ岬』、『セーヌ河口、オンフルール』と名付けた二枚の海景画は、エドゥアール・マネという画家の大作を挟んで展示されている。絵は名字のアルファベット順に並べられているから、マネとモネを混同した係員が、あるいは間違って配置したのかもしれない。
クロードはさっき一声発したきり、目の前で起こっていることを何度も確認するように大きく目を見開いていた。驚いている、とカミーユは思った。明らかに興奮しているようだった。久しぶりに見たからといって、自分の絵に驚いたわけではないだろう。なぜなのか、どういった種類の興奮なのか、カミーユには全くわからない。