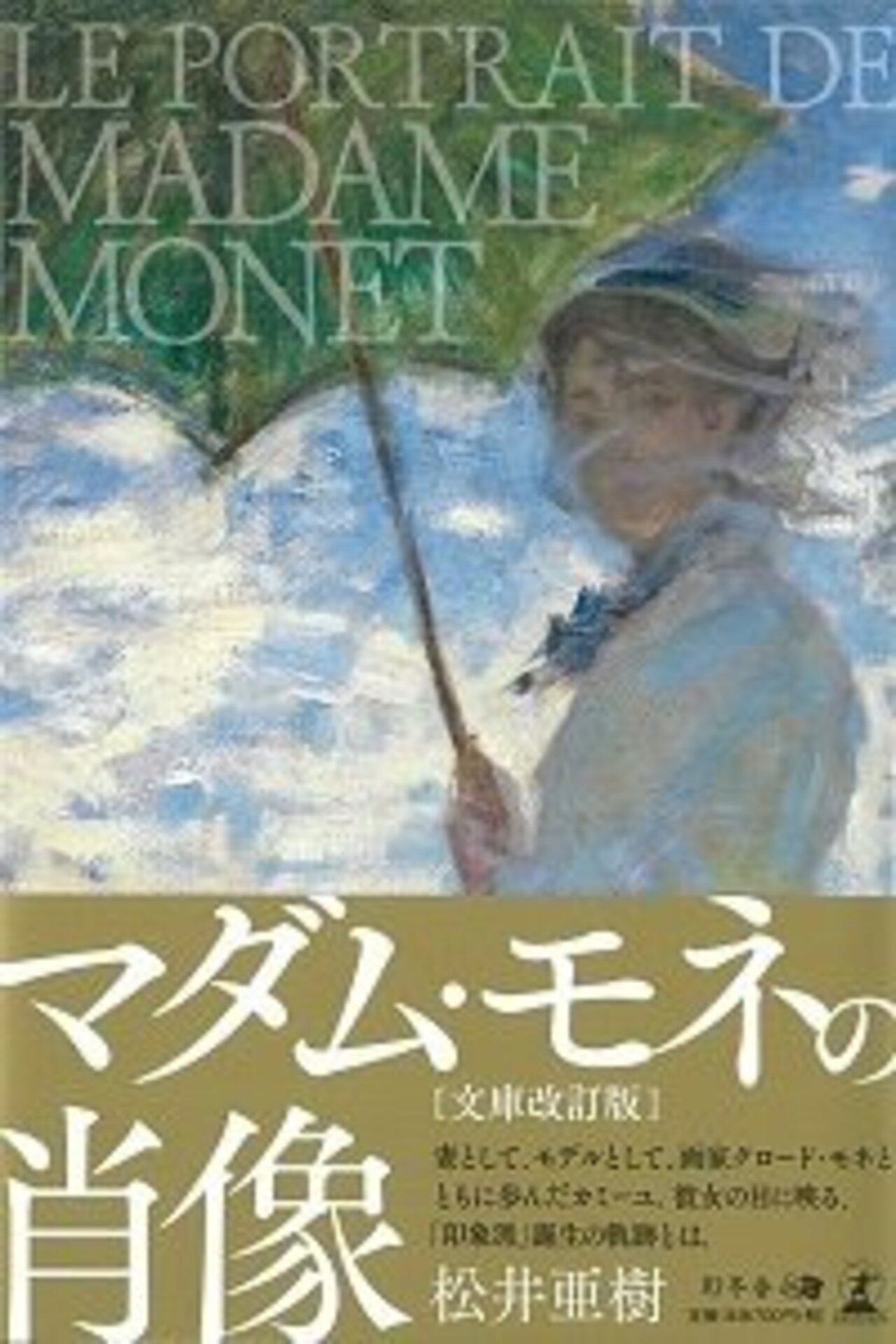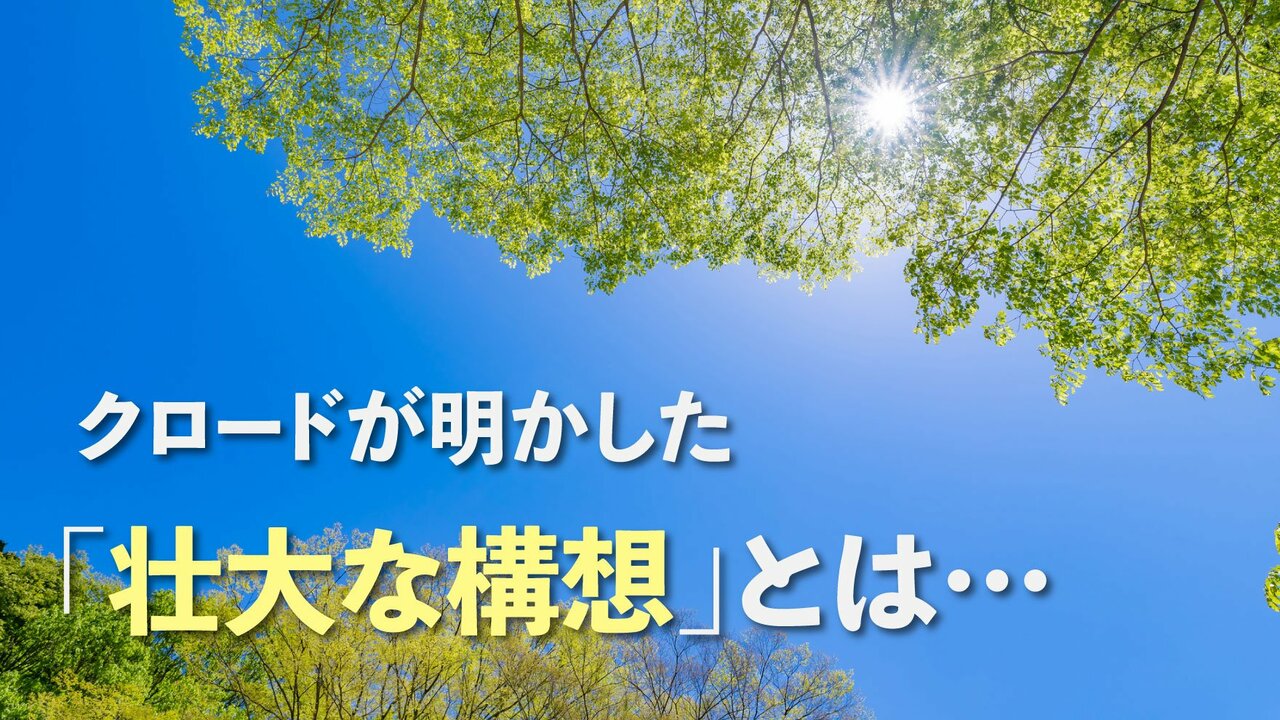気が付けば、周囲の観衆たちも興奮気味に思い思いの言葉を口にしている。それはどうやら、クロードの絵に挟まれたエドゥアール・マネの作品のことを言っているらしい。
カミーユも、やっとのことで人垣の間からその絵の全体像を見ることができた。タイトルは『オランピア』。裸婦がベッドに横たわり、物怖じする風もなくじっと観衆に視線を注いでいる。その奥では黒い肌の下女が花束を抱え、裸婦の足元では、黒猫が毛を逆立てて観衆に挑戦的な視線を投げている。
カミーユは漠然と、これまでに観たこともない裸婦だと思った。この人だかりの中で、話題はもっぱらこの絵のことだった。聞こえてくるのは、大方があからさまな非難の声だ。
「これは娼婦じゃないか、けしからん! アカデミーもどうかしとる」
一人の紳士がそう言うと、周囲は一斉に同調した。
「全くですな。芸術を愚弄していますよ」
レースのハンカチを口に当てた淑女は、ことさらに甲高い声を出した。
「裸婦の足元に猫なんて、汚らわしい!」
裸婦という題材自体、サロンでは決して珍しいものではない。現にこの会場にだって何十枚と飾られている。しかし、それを描くには一定のルールがあった。裸婦は、神話の世界の女神としてのみ描くことを許される題材だったのだ。さらに、実際の裸体を美化し、理想像として具現化する場合にのみ、人々の鑑賞・賞賛の対象となり得た。
そして、それらの女神は観衆を慈しむかのような微笑を湛えるか、あるいは微かな恥じらいを含む慎み深い表情を浮かべているのが“常識”だった。このころの観衆は、芸術鑑賞の歴史を持たない。芸術は、王侯貴族の専有物から広く民衆の鑑賞対象になったばかりで、独自の鑑賞眼を持つまでには至っていない。
彼らは、王侯貴族とその肝煎りのアカデミーが“正しい”と認める題材を、“正しく”“丁寧に”描いたものを“美しい”と評価した。つまり、評価基準は、全く王侯貴族の受け売りに過ぎない。“正しい”題材、“正しい”技法を求めるアカデミーの存在同様に、民衆の保守的な鑑賞眼とも、こののちクロードたちは闘うことになる。