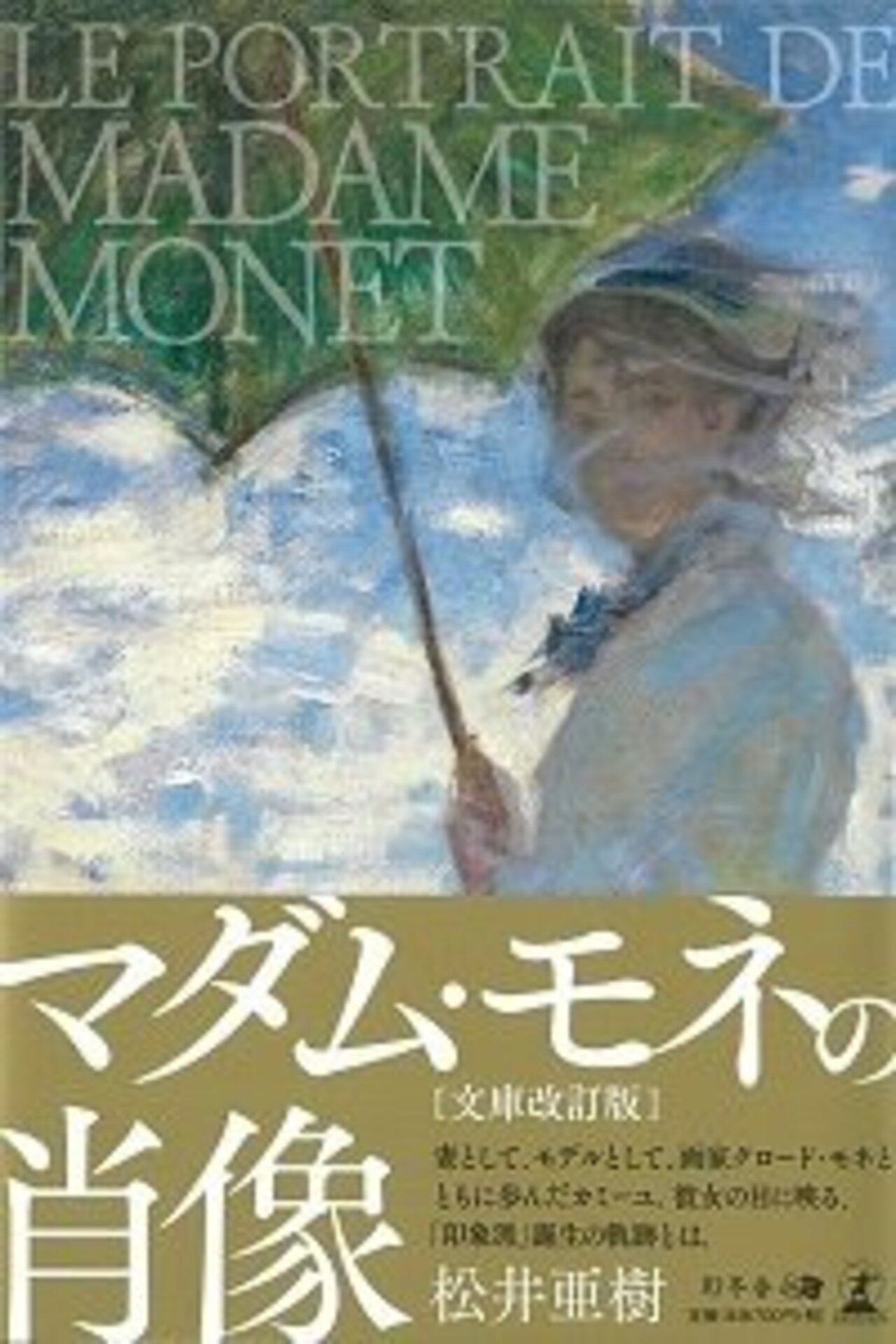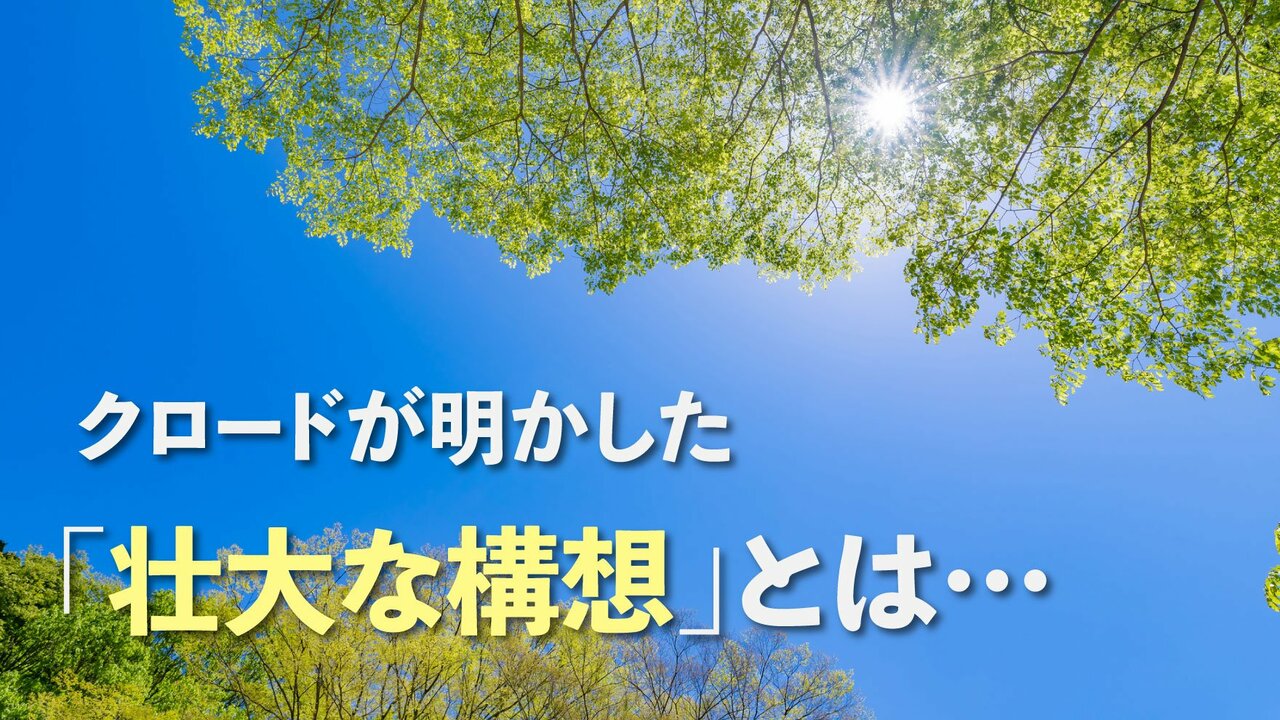カミーユは高くなった陽の中を、重たい体を引きずるように歩いた。来週も、同じ時間にアトリエへ行く約束だ。私にそれができるだろうか。朝になったら、わざと忘れてしまうんじゃないだろうか。ポン・デザールのたもとに花売りの少女がいた。まだ花でいっぱいのかごを抱え、道行く人に微笑みかけている。カミーユは、その懸命な笑顔を見ると思わず少女を呼び止めた。
「ガーベラを三本、もらえるかしら」
今日、謝礼に受け取ったばかりのフラン札を差し出した。家に帰り着くまで胸元で揺れていたその可憐なガーベラを、カミーユは細長い花瓶に活けた。それを眺めながら食事をしたり、縫い物をすると、いつもより少し豊かな時間が流れているような気がした。自分が働いて得たお金で、ささやかでも好きなものを買う。あのフランス革命以来、この街に溢れる“自由”という言葉はこういうことを指すのかしらと思う。
両親には、やはり裸体モデルのことは話さなかった。テーラーの客に画家の卵がいて、休みの日だけモデルを務めてほしいと言われたのだと話した。父親が険しい顔をしたので、今日の私のドレスが、もっと素敵に見えるような絵に仕上がったと伝えた。何も着ていなかったなどとはとても言えなかった。
翌週も、カミーユはアトリエのドアをノックした。
注文通り裸体モデルを務め続けた。二人の画家の卵たちはその間、夢中になってデッサンする。他人の目の前で裸でいる自分にたまらない羞恥と違和感を覚えることも、二人の視線を痛いほどつらく感じることも前回と変わりはなかったが、その真剣な表情を見ていると、彼らの気が済むまで頑張らなければとカミーユは思う。
バジールがデッサンの合間に教えてくれたところによれば、二人は去年の春まで同じシャルル・グレールという画家のアトリエに通っていたという。その画家の病気が原因で閉鎖が検討され始め、それを知ってモネが、続けてバジールもアトリエを辞めた。確か、そこでも裸体デッサンはやったと言っていた。「あごが下がってる」。そう叫ぶモネの厳しい口調と顔がふと浮かんだ。
「そのときのモデルは私よりきれいだったかしら」
何てくだらないことをと思いながら、その疑問は幾度となく意識に上った。