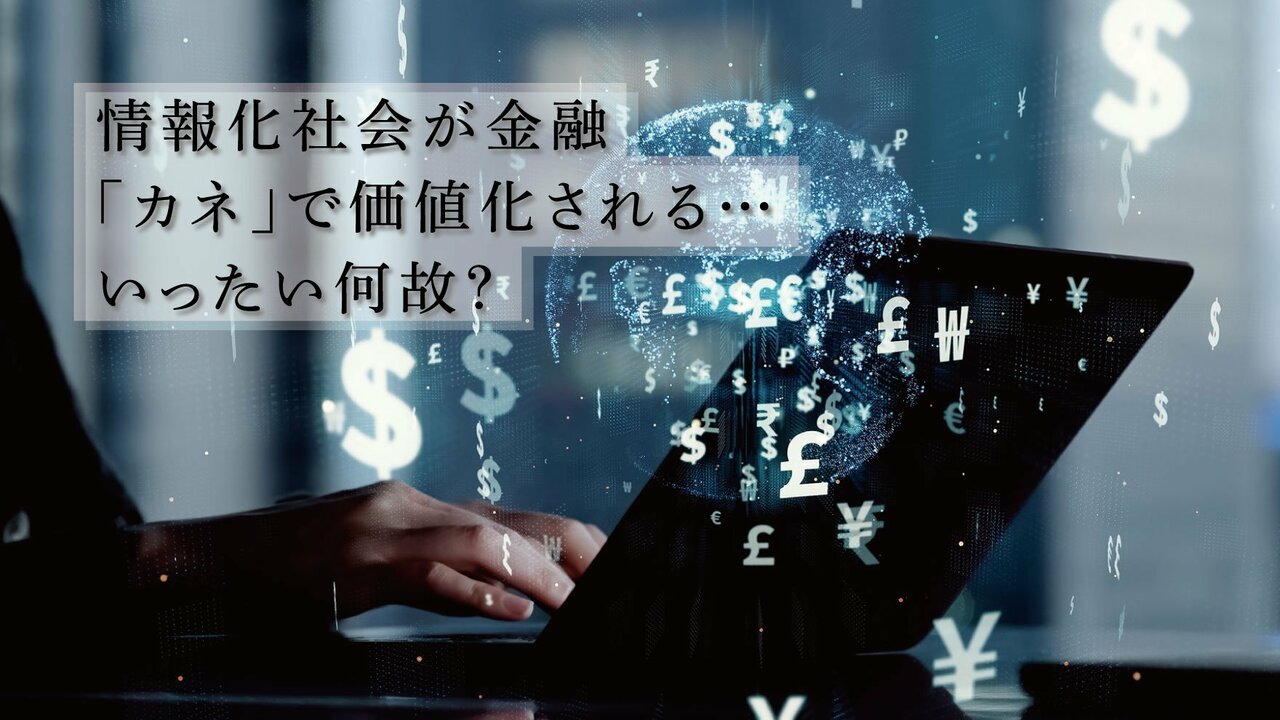「情報化がもたらす社会の二極化」
エンロン事件に代表される新技術における信用の二重構造は、デジタル革命の起点となるスマートフォンを通してインターネット・ウェブサイトや検索エンジンなどのアプリケーションの登場により、まさに複層的に、表から裏まで何層にもわたって発生したと認識すべきだろう。
通信回線のキャパシティの一割の契約をしてその回線の十割分の売り上げを上げることは、その回線の契約を0か1かに区切るからである。
また、ペーパーカンパニーを経由した資金は出し手から見て融資であっても借り手側では資本であると会計上で処理できるのは、1を0にするようなものだ。信用の二重構造が発生するとき、そこの原理には0か1かという二分法の論理が介在する。
0か100かという一般的に使われる用語と同じであって、割り切ったほうがその後の行為を正当化し、かつ行動の過程を制御しやすくなるからだ。ロボットを機械で言う通りに動かすことと同じだと言える。
例えば、財務諸表監査における重要性基準(Materiality Test)の適用も、関係者に対する賛否(Yes/No)のヒアリングで判断していては、基準が機械的・総括的になり、信用の二重構造の罠から逃れられない。
たとえ、経営に影響するある重要な事象の発生確率を、0、20、50、80、100%と五つに分類してみても、断面的な元の判断が賛成か反対かという二者択一の固定性によって結果的に二重構造を発生確率ごとに五通り生み出しているだけだ。
発生確率を五つに分類するのであれば少なくともその発生確率分布によってどう対処し、責任をどうするかまで決定しておかなければ、当該事象を0か1で判断していることの言い訳にしかならない。
そして、0か1で判断できる時代は、デジタル革命による情報化の進んだ今、二〇二〇年からモノの電動化が急激に進む時代には過去のものとなるだろう。翻って、過去の二十世紀は情報の「非対称性」と言われた時代である。それは「知らないか、知っているか」の0と1の二つしか選択肢がないことを歴史的に証言し、かつ、その二つの間の選択で事足りた時代の懐かしい言葉のように思える。
つまり、論理的な0か1かのデジタル思考の持つ欠点がまだアナログな実社会体制の現場によってカバーされていた良き時代であったとも言える。今後はその二重構造、敢えて言えば賛否の二極化は現場でカバーされることはなく、極端な対立軸や議論できない状況を招くことが多くなるだろう。
従って、デジタル社会の本質は二極化に向かいやすいということだと認識しておいたほうが世の中のリスクに対応できるのではないだろうか。