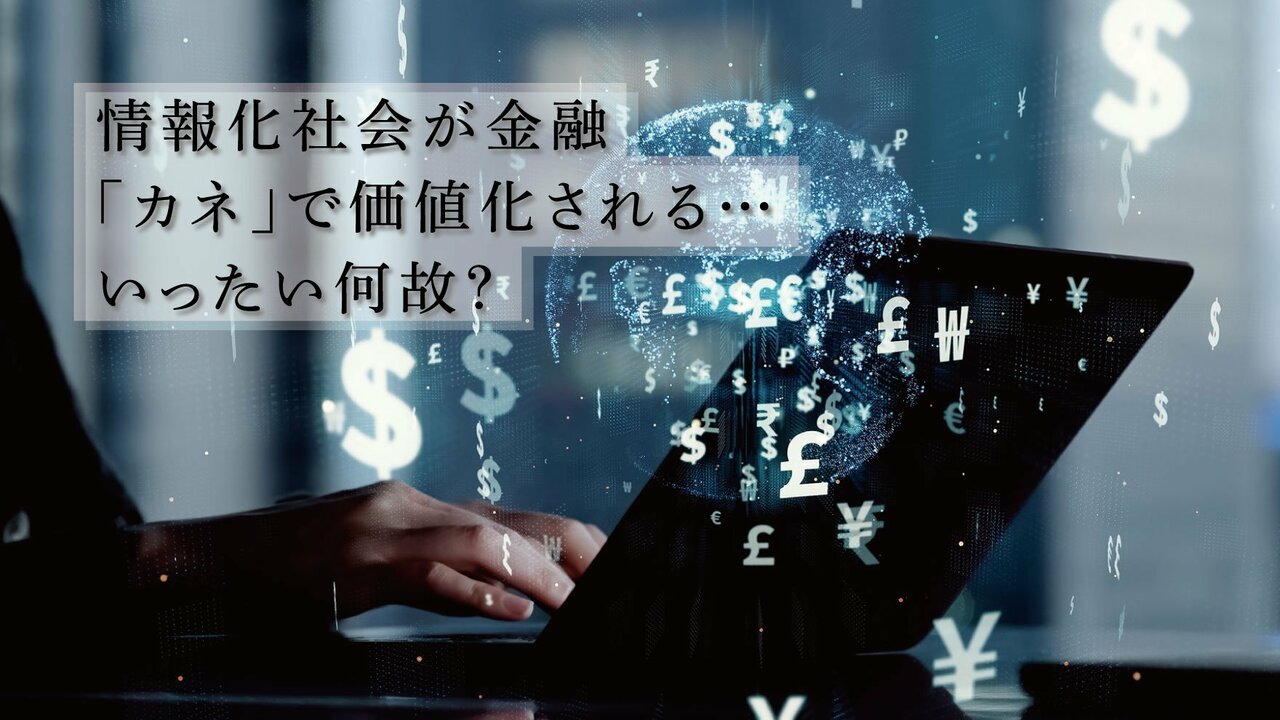「デジタル化の本質」 情報の拡大と共有は何をもたらしたか
アナログ社会は数値と言語と映像により急速にデジタル化、即ち0と1のデータログに置き換えられることになった。その結果として本来なら知っている人と知らない人がいるという状態の「情報の非対称性」は消えるはずである。
金融の事例で言えば、情報をすべて取り入れた政策決定や中央銀行に代表される経済合目的な金融操作はすべて金融市場で裁定されること(Arbitration)により、国際通貨は安定し、金利は実体経済の適正水準に収まるはずだ。
実際、二〇二〇年までの超低金利時代と言われる日本の二十年間も、米国の最近十年間も多くの事象に対する政府・中央銀行の対応は合理的であり、社会的事件や大きな災害にもかかわらず、金融は安定してきたと言えるだろう。いわゆる実証データに基づく最適政策決定(EBPM、Evidence Based Policy Making)が、金融においては実行されてきた。
これは金利の低下も経済実態には直接効かないような金利の罠に陥ったデフレの時代だからこそ、国債・通貨を大量に発行する量的金融緩和策により景気を直接管理できたと言っても過言ではない。
このように、市場の金融経済政策から見た情報デジタル化は、情報の非対称性をなくすことによって、大量生産・大量消費に基づく市場裁定の効率化を通した相対価格の下落(ディスインフレーション)を起こすと同時に、実質潜在成長率以下の局面では量的金融政策の有効性(EBPM効率)を高めていると言える。
ところが、デジタル化による情報の拡大と共有化は、一方で市場経済の安定化に寄与しながらも、他方では深刻な問題を引き起こしている。最近の政治的特徴としてマスコミなどでも取り上げられるポピュリズムと国家資本主義の台頭である。
個人が意見を言える社会は自由で民主的だ。
しかし、そこにルールを支える価値観の共有がなければ、単なるポピュリズムとなってしまい、形の上で「民主的」であればあるほど将来に向けた政策決定はできなくなり、価値観を共有していない「自由な」社会では身勝手な言い放しの混乱に陥る。そうなると、今までも見てきた通り国家は何とかして国民の意思を尊重したような目先の決定を優先するようになる。
経済政策だけでなく、対外政策にも同様の手法が採用されるようになり、国家資本主義とも言うべき、アメリカファーストや共産党一党支配の国際化を政治的に標榜することになった。
二十世紀末のグローバリズムは情報通信の発達により情報の国際化が進んでいる状況を反映していたが、今世紀のデジタル化による情報の国際的拡大と共有は、価値を共有していないことを明確化させ、アンチグローバリズムを強化することになった。デジタル化によるポピュリズムがアンチグローバリズムを生み、目先の技術経済戦略を優先する国家資本主義を育成したと考えている。
ここで国家資本主義のリスクを論ずる前に技術的なデジタル化の性質に立ち返って、今そこにある技術がもたらす情報化の誤謬について考えておきたい。私たちが容易に陥る落とし穴だが、そこは溢れるデータ情報に惑わされることもなく危機感もなければ、デジタル社会の日常としては意外と心地よいものなのかもしれない。