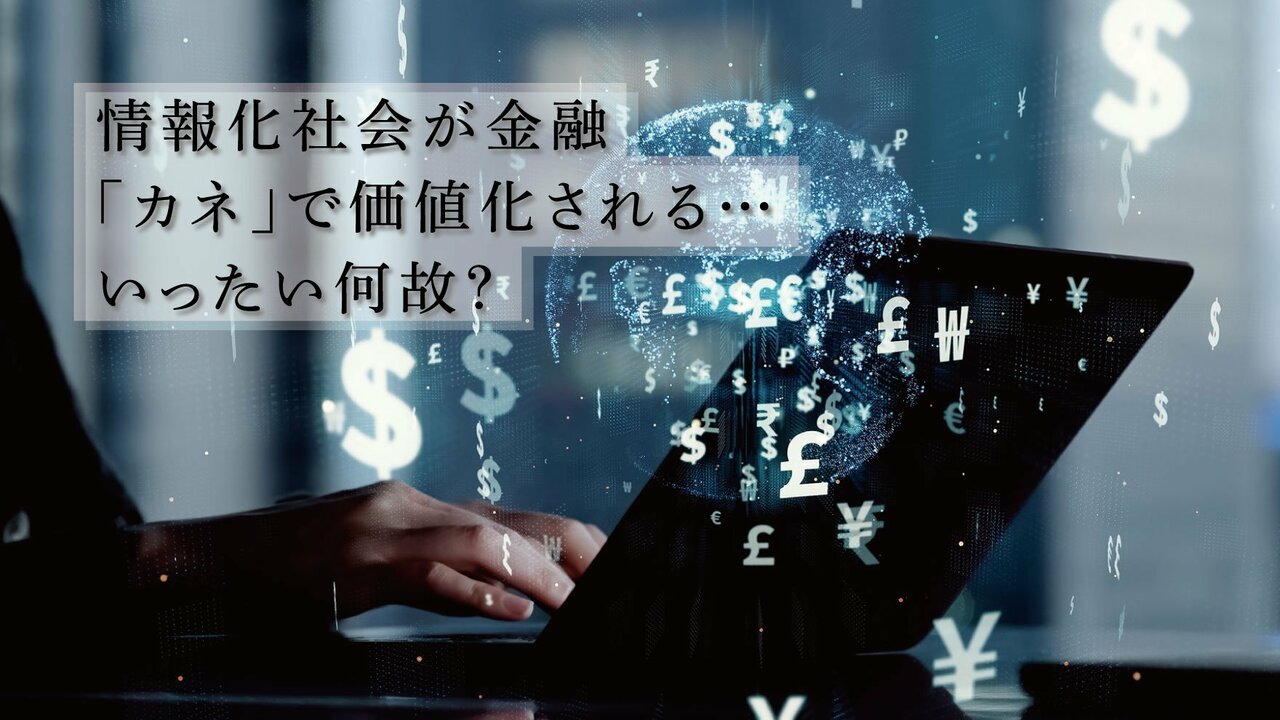「通信技術の変容と信用リスク」
いつの時代でも技術の発展は利便性をもたらすと同時に、新しいリスクも生んできた。なりすまし詐欺に始まり大規模な資金ファンド詐欺など、通信を使った多くの事件を目の当たりにされたと思う。スマートフォンやLINEによる通信技術の発達は通常の販売や生産だけでなく昔風の詐欺をも現代的に効率化させ巧妙にしてしまうことが、私たちの見た通りの世の中なのだろう。
最近は特に企業・金融システムのハッキングを通したデータ抜き取り・改ざんなどのサイバー攻撃が多発し、普通に生活している私たちが従来は信頼していたはずのデータの取り扱いも既に安全性が脅かされている。サイバー攻撃とその防御の狭間で破られない暗号はないというデジタル社会の状況では、量子を制御できない限り顔認証は常にフェイクが作られ、静脈認証や虹彩認証も一度流出すればパスワードと違って一生変更できないだけに取り返しのつかない事態になる。
このような漠然たる不安を抱えたままデジタル化推進を押しつけられても、私たち一般市民は日常の生活の中でどう対処していいか分からない。一人ひとりの将来のリスクに備えるためにも、情報化という技術が社会的にはどのような方向性を持ち、その中で次々と生み出されるリスクの本質をどのように見るべきかについて考え続けてみたい。
振り返って通信技術のイノベーションということでは、二十世紀末のITバブルが記憶に新しい。ちょうどニューヨークに駐在していた私は、この時期のITというものは便利な通信技術の進歩だと考えていて、まだ情報技術という処理そのものの変容を理解していなかった。
日本国内の会社に勤務していた人たちのITへの理解はもっと軽いものであったかもしれない。既存のプログラムが二〇〇〇年に停止するかもしれないとの専門的な問題が大きく取り上げられる中、実際、当時は「Eメールでやりとりするよりも電話のほうが手っ取り早い」というビジネスマンも珍しくなかった。
最初にITバブル崩壊が表面化してきた事象として、通信ベンチャー企業群に係わるインサイダー株式取引というものを目の当たりにした。いくつかの通信ベンチャーは、技術の偽りにより、あるいは、売り上げの過大計上により、破綻していった。その中でも最大規模の事件がエンロンの粉飾だった。
通信ルートの売り上げについて、ひとつのルートの通信回線キャパシティの一部の契約だけでその通信回線のフルのキャパシティ相当分の売り上げを計上するという手法であったが、当時の旧技術に対する解釈の範囲では、過大な解釈も粉飾ではないと申し開きすることも可能だった。新領域に対する価値の解釈が常識を越えて拡大されたために結果的に粉飾とされた事例と言える。
だが、後に当エンロン事件が契機となって成立する米国サーベンス・オックスレー法のうえでは、意図的に(intentionally)、または知ったうえで(knowingly)行った過大計上に対して厳格な罰則を適用することとなった。エンロン事件の調査において、その技術的な解釈を議論した記録が当のエンロン社内と担当する会計事務所に残っていたことが新しいルール制定のきっかけとなった。