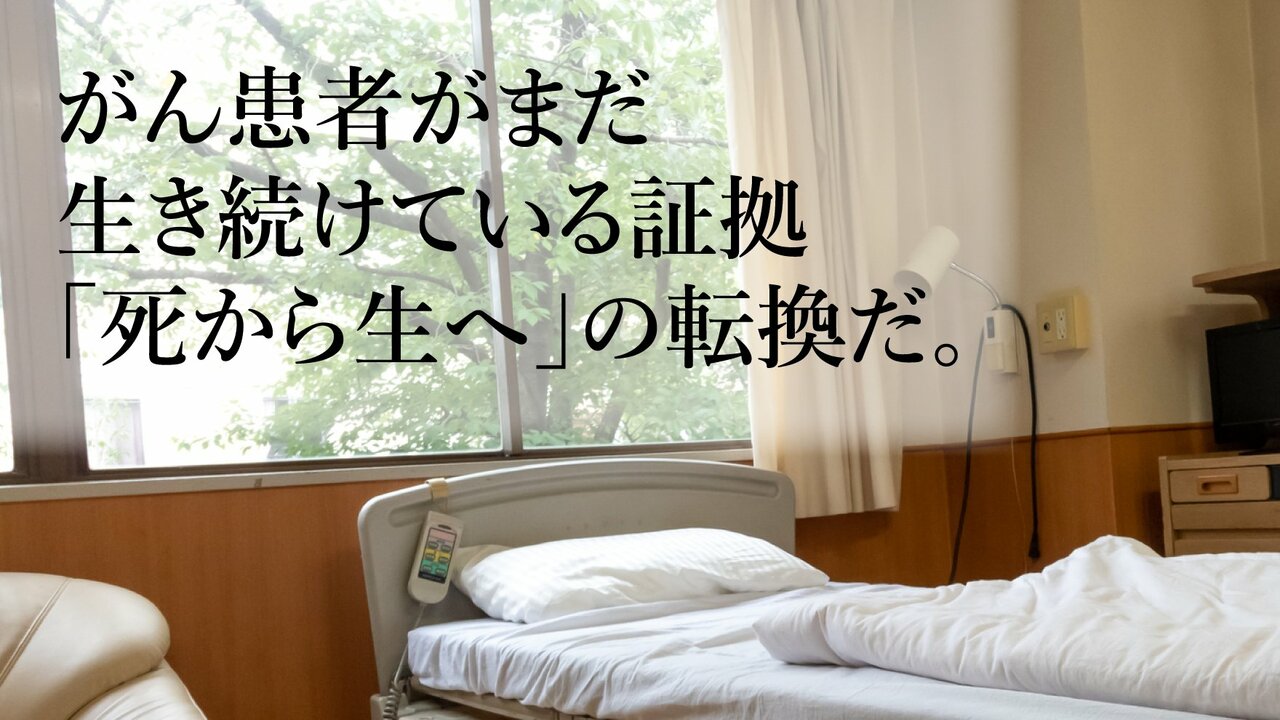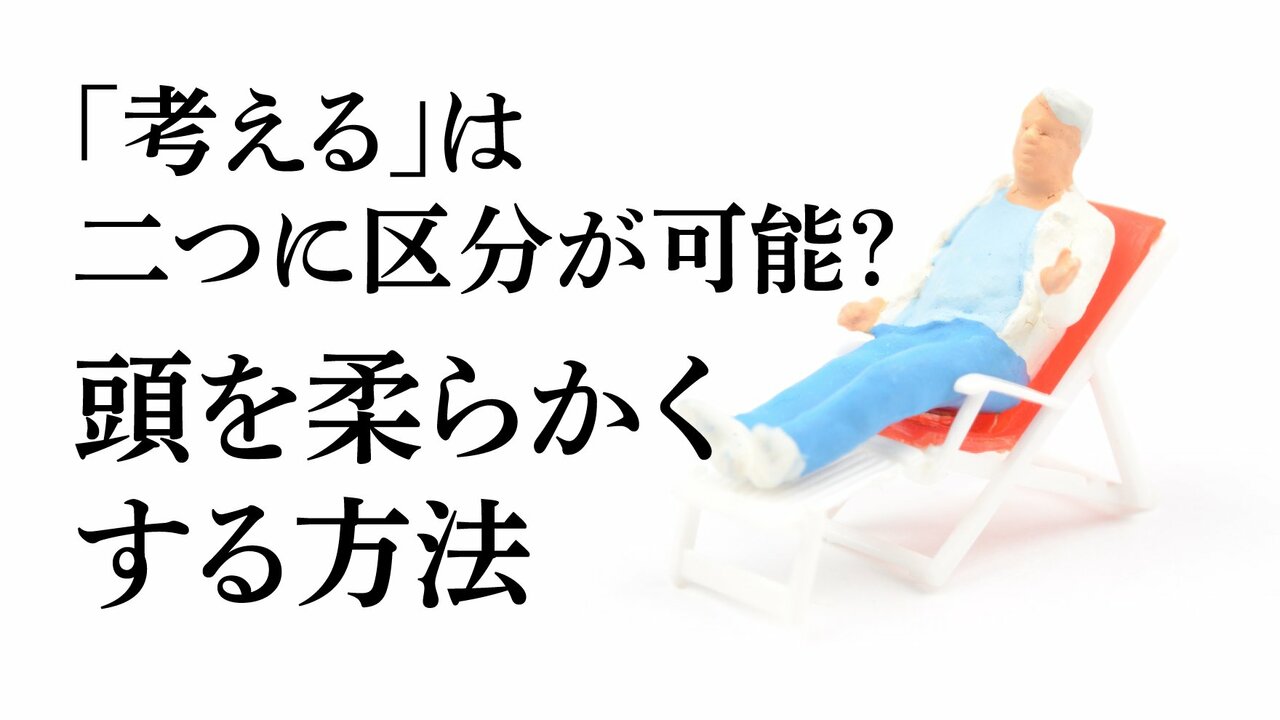「死」から「生」へ。明日がある
元社長とミツオ少年が出会ってから、どのくらいの歳月が流れただろうか。ある日のこと、元社長はミツオ少年から山奥にある「沢」に行こうと誘われた。その沢には竹薮があり、竹の花が咲いたことがあるとのことだ。ミツオ少年は、どんどん沢に向けて歩いて行った。だが、病弱の元社長はミツオ少年について行くことができずに倒れ、意識を失ってしまった。
しかし、ミツオ少年と地元の農家の主人に助けられて、意識を取り戻す。普通の体に戻った元社長は決心した。突きつけられた現実に、潰されない。「生」に対して諦めず、人生の終わりをまっとうしようと決心する。来年のお盆の頃までは生き続けたいと……。
そして、お盆が来た。ミツオ少年はいつもの様に、バス停で赤いバスを待っていた。バスが走って来た。そのバスからはミツオの姉が降りてきた。続いて元社長も……。
西村は、この『赤いバス』というドラマを毎日のように聴いていたことは既に述べたが、聴くことによって、自分の生死の意識が変化したことに気づいた。「死」から「生」へ変わり、自分には大切な明日があると。
西村は「もうダメだ。もう出来ない」と諦めていた絵画や版画の制作を再開した。残された二度と来ない人生を生き抜いてゆこうと、やり残したことに力を注ごうと思うようになった。その一つに執筆活動があった。
西村が小説の構想を練っていると、娘の藤木由美が来た。孫の侑菜を引き連れてである。西村の病状については、藤木もよくわかっている。部屋に入るなり彼女が言った。
「お爺ちゃん、『小さなお葬式』ってテレビコマーシャルに出ているでしょ。お爺ちゃんがお亡くなりになったら、『小さなお葬式』をやってあげるよ。駅の近くに、小さな葬儀場が建ったでしょ。そこがいいね。ついでに、お婆ちゃん(母親)の葬儀の予約もしておこうかしら」
皆が爆笑した。親子関係がよくて、信頼できるからこんな会話ができるのだ。
小学2年生の侑菜が、西村の肩に手を載せて言った。
「爺ちゃん、今度は何を食べさせてくれる?」
「何を食べたい? 侑菜はうなぎは嫌いだったな。やっぱり刺身か?」
「そうだね。それもいいけど、今はカレーが食べたいな」
「じゃ、カレーを食べに行こうか」
「カレーの次は、コンビニでイチゴが入ったアイスクリームだよ」
孫の目は澄んでいた。キラッと光った目を見て、西村は思った。《俺にも、こんな時代があったんだ。俺は子どもの頃から絵を描くことが好きだった。将来は画家になりてぇ》。
子どもの頃の夢は消えなかった。だから西村は二十歳代の半ばに、洋画家の小川博史先生に絵を学んだ。学ぶと言っても、小川先生からの具体的な指導はなかった。先生の優れているところを見出し、自ら学びとるというものだった。小川先生は重厚なマチエールの絵を描いていた。
アトリエに通う画学生たちは、経済的に裕福な人たちであった。高額な油絵の具を、まるで遊ぶみたいにキャンバスに塗りつけていた。画学生たちには小川先生のアトリエに通っているということが、一種のステイタスになっていた。西村のように経済的に窮する人はいなかった。
若い時に画家になりたいと思ったことを思い出していると、西村の脳裏に自分が罹った緑内障について浮かんできた。