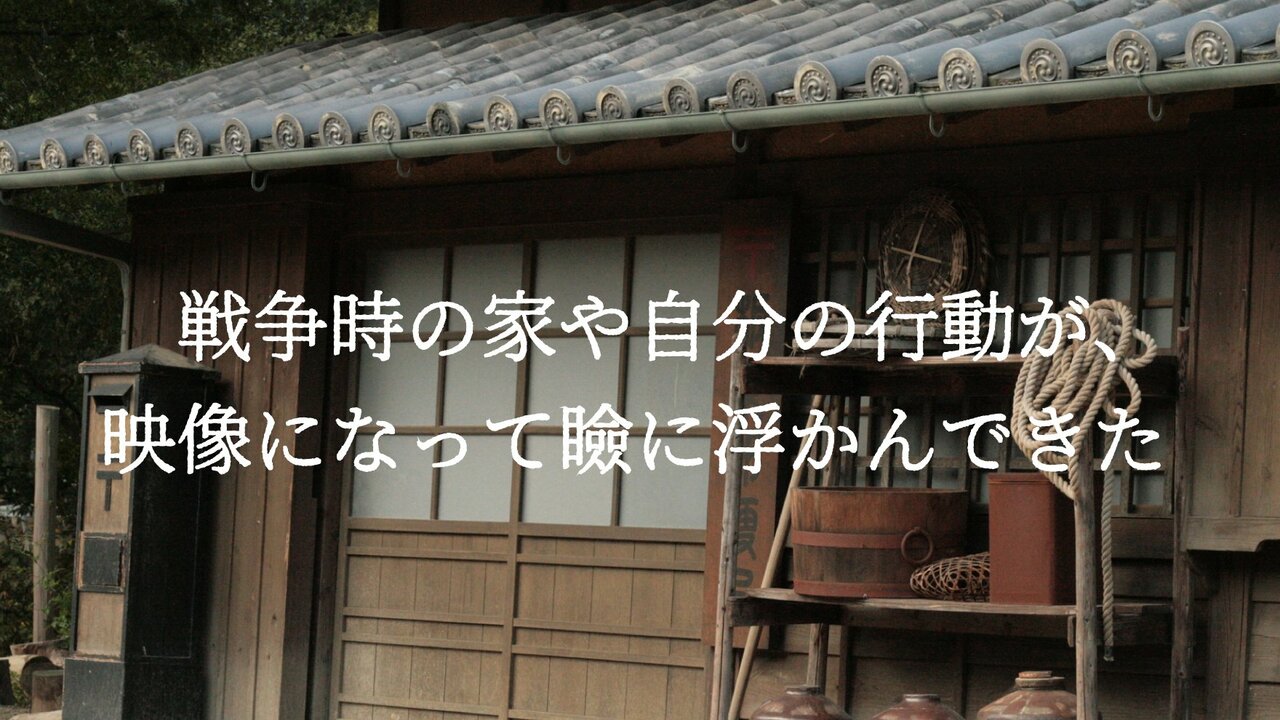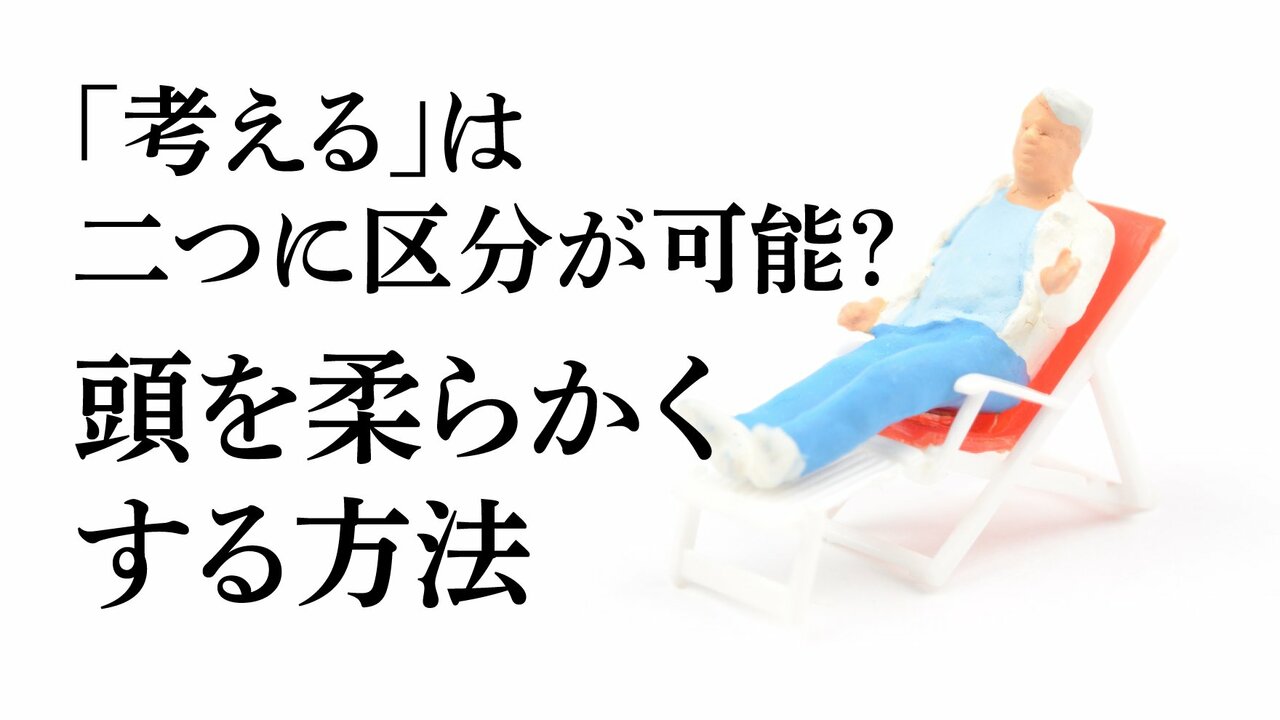「死」から「生」へ。明日がある
自分は東京生まれだ。一家は、東京市(当時は東京市であった)の葛飾区下千葉町108番地に住んでいた。
父は東京で警察官をしていた。キリリと締まった警察官の写真を見たことがある。息子から見てもいかにも格好がいい。その父は、太平洋戦争にて一兵士となった。母と私は、亀江戸にいた父に会いに行った。葛飾区のわが家に帰ったら、景色が一変していた。水道管が剥き出し、電柱が倒れた焼け野原と化していた。父との面会に出かけていたので、生き残ることができた。当時の家や自分の行動が映像になって瞼に浮かんできた。
黒いコールタールを塗布した板塀の平屋には、玄関の戸を開けると、正面の床下に防空壕が設けられていた。アメリカ軍の飛行機が飛んで来た。機体が銀色に光っている。空襲である。母は私を抱えてその防空壕に入った。私は、じめじめした黒土の狭い空間を忘れていない。私は家の格子窓から米軍の飛行機を鉄砲で打ち落とす仕草をしたことも覚えている。玄関の入り口の脇には、防火用水を入れる薄いコンクリート製の箱があった。狭い道路で身丈に合わない大きな三輪車に乗っている私。懐かしい写真が今でもアルバムに残っている。
懐かしいと言えば、私の裏の家だ。『岸壁の母』を歌う二葉百合子さんの母が住んでいた。私は家の裏の珊瑚樹の垣根をかいくぐって、二葉百合子さんの母親の家に遊びに行ったものだ。彼女は私に対して「アキちゃん、アキちゃん」と可愛がってくれた。「アキちゃん」とは、西村明広の「明」を「アキ」と呼んだものだ。
家が半分くらい焼失してしまったことを知った父は私たちに、「小布施に移れ」と言った。父から命ぜられたとおり、母と私は長野県の小布施に疎開した。それは終戦の直前のことであった。小布施は父の本家があった所だ。父の本家はかなり大きな農園を営み、地域のリーダー的存在であった。当時は主として、リンゴの生産をしていたが、間もなく「栗」に変えた。幾分かのリンゴの生産も残したが、リンゴから栗への転換は大成功した。
終戦直後のことであろう。父は警官を辞めた。なぜ辞めたのか理由は定かではない。その後間もなくして、私たちは小布施から長野県と山梨県との境界近くにある諏訪郡の富士見に引っ越した。そこは私の母の実家がある所であった。
父は開拓者となった。母の実家から徒歩にて十数分の場所は原野であった。原野の中に雑木も立っていた。父は鶴嘴、鍬をふり、鋸で雑木を切り倒し、開拓していった。
その頃から父は、鍬や鎌を売り歩く行商人となった。続いて、営林署で働くようになった。母は実家の細々とした農業を手伝う傍ら、この地区では盛んであった製材所で働いていた。父母は懸命に働いたが、それでもわが家は貧乏だった。私たちが住んでいた家は、雨漏りがし、冬になれば、雪が顔の上にチラチラと舞い落ちて来るボロ家であった。子どもの頃は、貧困のためにジャガイモしか食べられなかったこと、ジャガイモを洗って、皮を剥いたことなどを、脈絡なく西村は思い出していた。