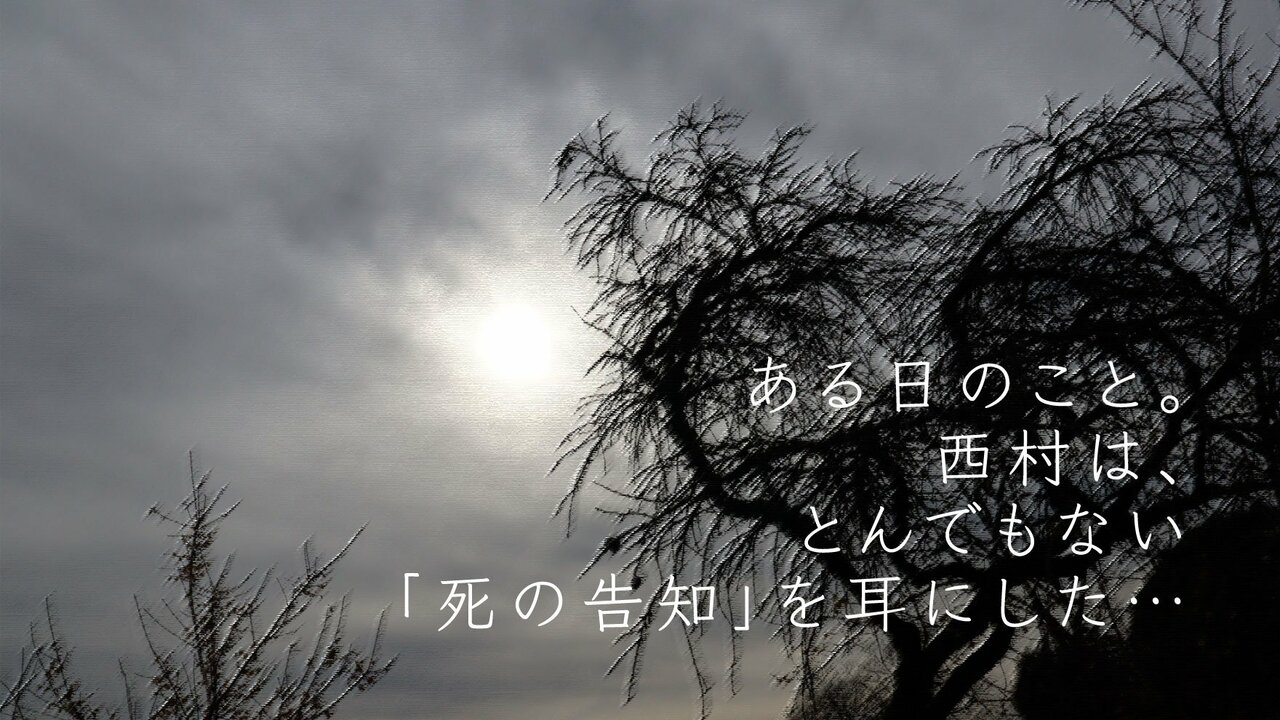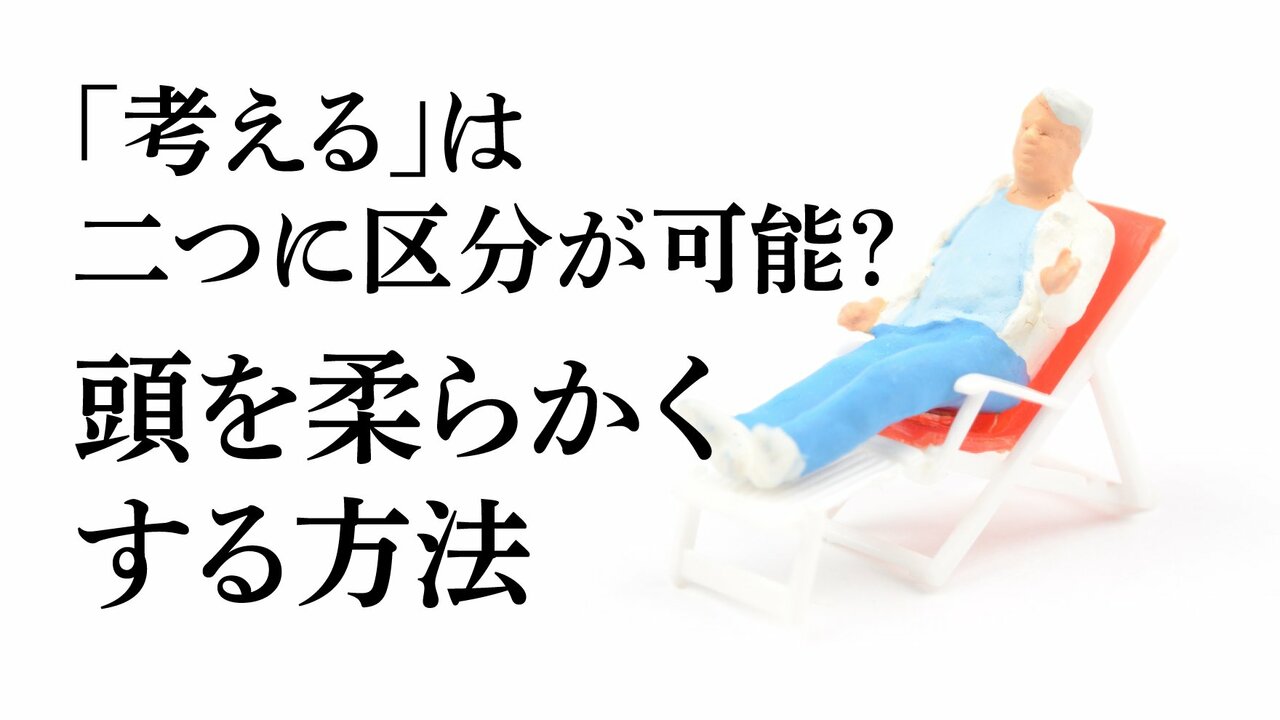「死」から「生」へ。明日がある
洗面所の鏡の前に立った西村明広は、じっと自分の顔に見入った。
白髪が混じった薄い髪であったとはいえ、その髪はすっかり消え失せてしまっている。濃い眉毛も数本の毛だけになった。つるつるの頭が光っている。毛根からは、何かしらネチャネチャした汗みたいなものが出ている。
西村は思い出した。自分は半年前には、総合病院に入院していたのである。入院時に、左腕に番号付きの「腕輪」をはめられた。あたかも囚人みたいに収容された。番号は0002658860である。
収容されたが、アウシュビッツではない。温かい心を持った医師や看護師に囲まれていた。酷暑の体育館の中で卓球をやり、帰宅後に缶ビールを三缶飲み干した。普段と変わらない夕食を食べ、10時頃に床に入った。
体の異常を感じたのは、その直後からだった。妙に腹が張った。強い赤橙色の小便が出た。西村は小便の薄気味悪い赤橙色が消え去るのを期待した。
待った。だが、透明な色の小便は出なかった。翌朝、西村はかかりつけの野村内科医院に駆け込んだ。採血した。結果は驚嘆すべきものだった。
肝臓の機能を示す数値が、基準の100倍も悪かったのだ。したがって、即時、総合病院に入院することになった。入院の初日は、エコー、レントゲン、血液検査、CT検査など「検査、検査」であった。
当日の夕刻。西村は、とんでもない「死の告知」を耳にした。
2019年の8月29日のことであった。近田という若い担当医が言った。
「膵臓がんです。ステージ4」
「……」
西村の口からは、何も発せられなかった。だが、彼は動揺していなかった。西村自身も不思議に思えるくらい落ち着いていた。
思い起こせば、予兆があった。西村の体についての予兆ではない。玄関に飾ってあった瀬戸物の犬の造形物。立派な置物である。座った犬で、座高は数十㎝はあろう。
その犬の胴体に西村の妻が触れるか触れないかした時、犬の胴体が真っ二つに裂けてしまったのだ。入院した当時の西村の体はまったく異常だった。
西村は水の一滴も飲めなかった。また、飲もうとも感じなかったのだ。無理して水を飲むと気持ちが悪くなってしまった。西村にとって未体験なことだった。
よく見れば、体が真っ黄色だった。黄疸である。全身に痒みが走った。痒みの原因は、黄疸とのことだった。痒みは夕方の7時頃から始まり、一晩中痒みが続いた。痒いから眠れないのだろう。
だが、「止痒水」を体中に塗布しても眠れない。睡眠薬を飲んだ。だが、わずかに頭がボーッとなるだけで、眠れなかった。一晩だけではない。何日も続いた。おまけに強い吐き気が襲ってきた。吐いてしまった。濃いお茶というか海苔のような色をした嘔吐物であった。
後からわかったのだが、吐いたのは胆汁だった。入院してから数日後、近田医師が言った。