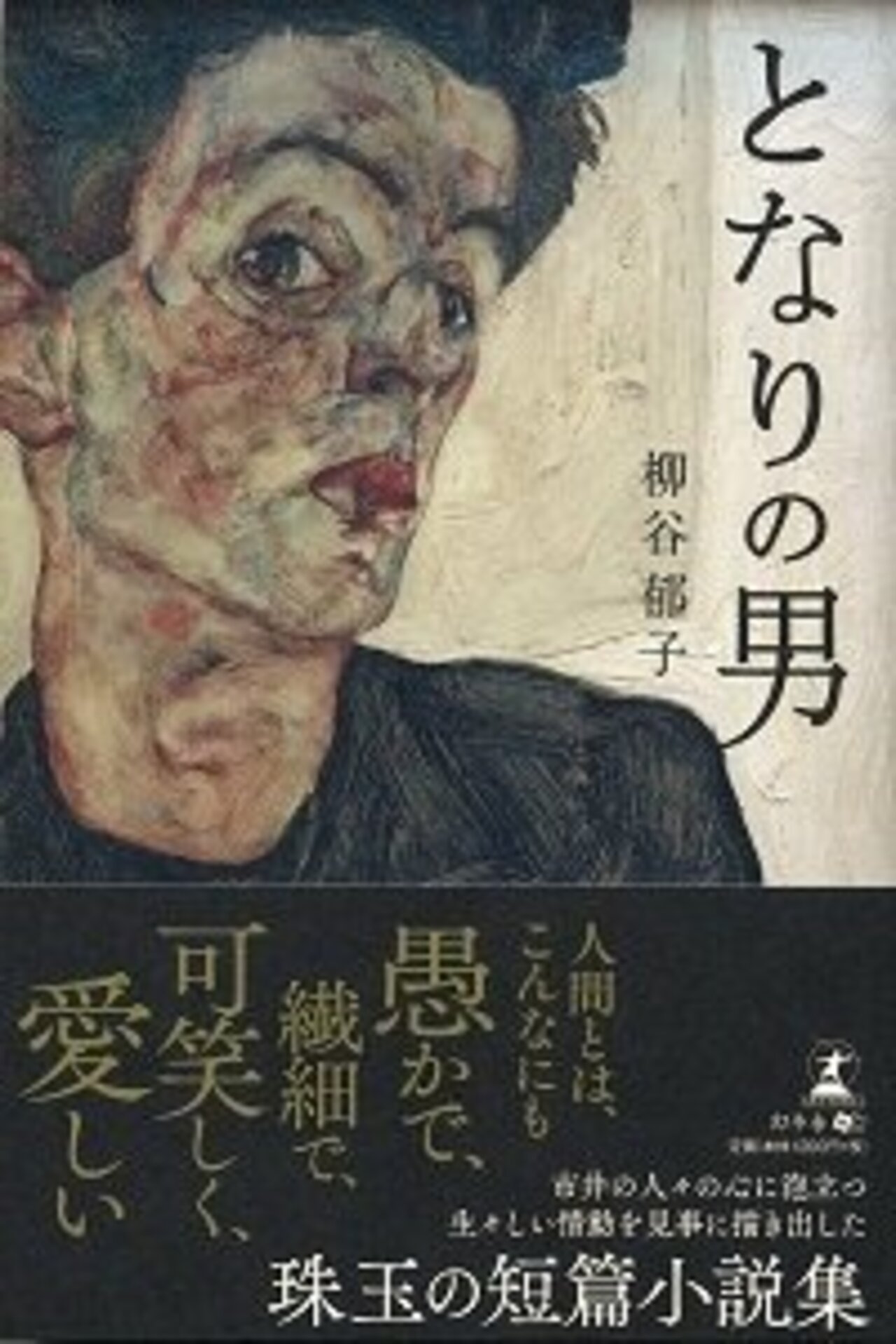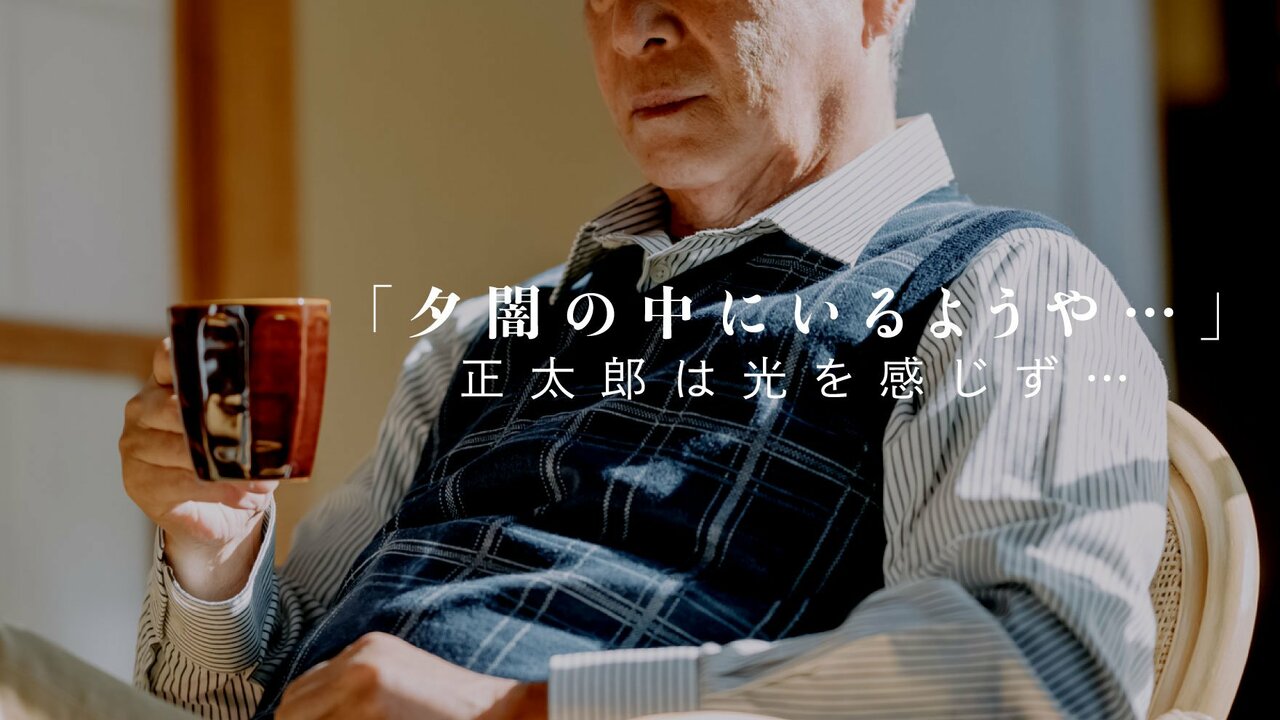時代は戦争へ戦争へと向かう昭和の初期や。張作霖爆死に絡む陸軍省某重大事件からやな、尾崎なにがしとかいう東京裁判所判事を中心とする反政府グループ活動を取締り始めた。その取締りに引っかかった。勉強会はよからぬことを企んでいる集まりと見なされたんや。まあわしたちは裁判所を依願免官ということで済んだんやが、その後はてんでばらばら、仲間はみんなどうなったんやろなあ。
ともかくもわしは、それからまた独学や。暮らしを立てるために先ずは司法書士の資格を取ることにしてな。
強度の近眼と重症の脚気のために徴兵を免れた正太郎は、それほどまでにして得た司法書士の資格を、今ではとても許されないことだが、戦地で銃弾を受け腹に数発の弾を持ったまま帰還した弟に貸して、もともと家業の鍛冶屋関連の会社を興したりした。それはそれで戦後のカネヘン景気があったりなどして満更でもなかったのだが。
武彦の大学卒業を待って父子で司法書士事務所を開業した。すでに五十に近い歳になっていた。所長としての給料がようやく五十万になると、市長の給料と同じになったと無邪気に喜んだ。
小学校時代、同級生であった市長とは一、二を争う成績やった、片や教育一家に育った市長は当時の県立中学へ進学してそのまますいすいと帝国大学へ進んだんやが、正太郎さは鍛冶屋の子とて中学なんぞへはやらせてもらえんかった、悔しかったろうなあ、儂らは心底惜しんだもんやと、同じ同級生であった寺の住職は言った。
「わし、なあ ―」
何でもない独り言のように、しかしいつもと違う余韻を曳いて正太郎が呟いた。
はい、とふゆ子は部屋を出かかった足を止めた。
「わし、なあ、さっきから急に目の前が暗うてな」
「おじいちゃん、まさか ―」
「いんや、うすぼんやりとは見えるんやがな。何か塊があるなくらいは、な。けどそれが色がないんや。みんな黒いんや」
「光を感じないということ?」
「ん、そうやな。夕闇の中にいるようや。あんたも形しか分からん」
正太郎の入院はその日のうちであった。