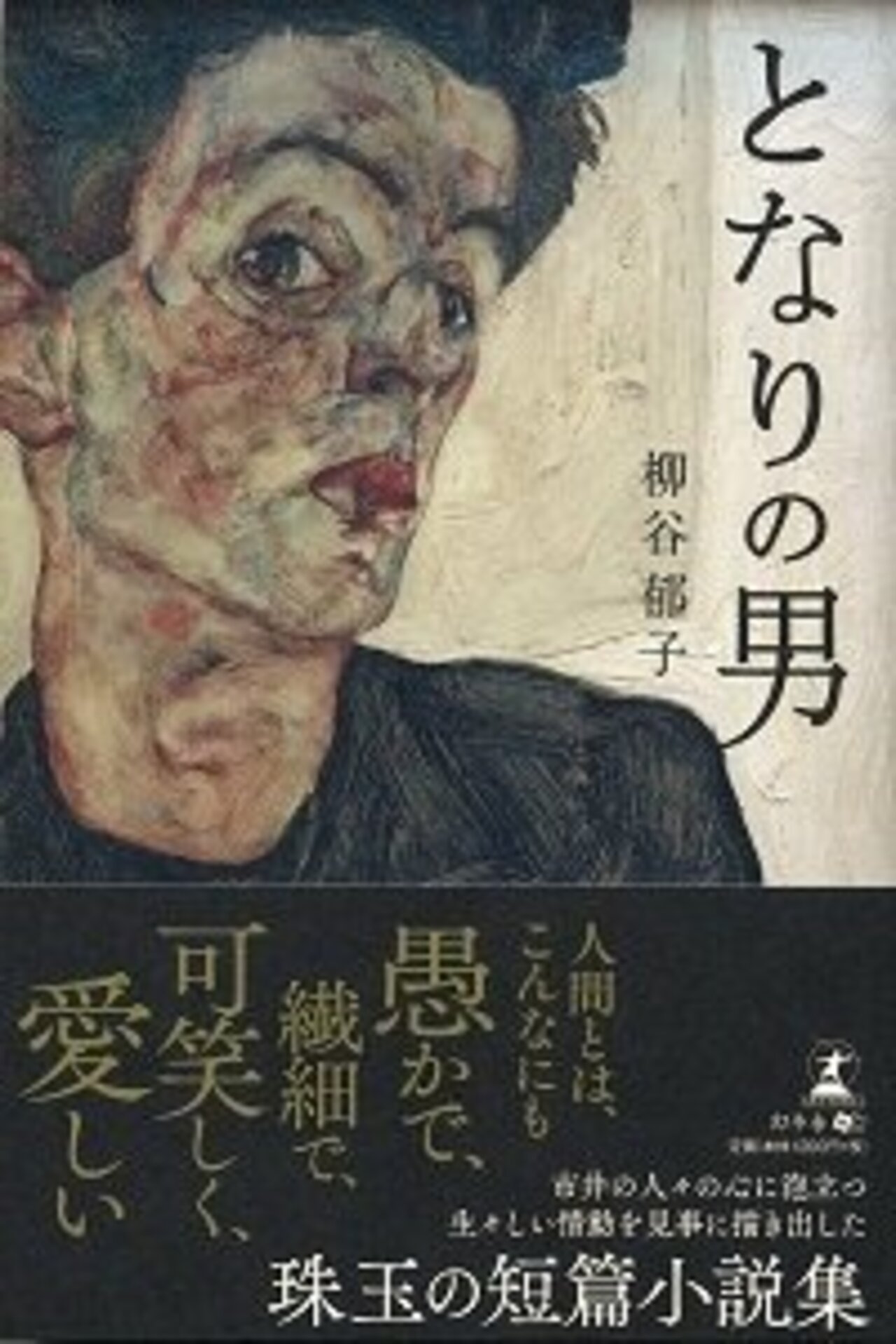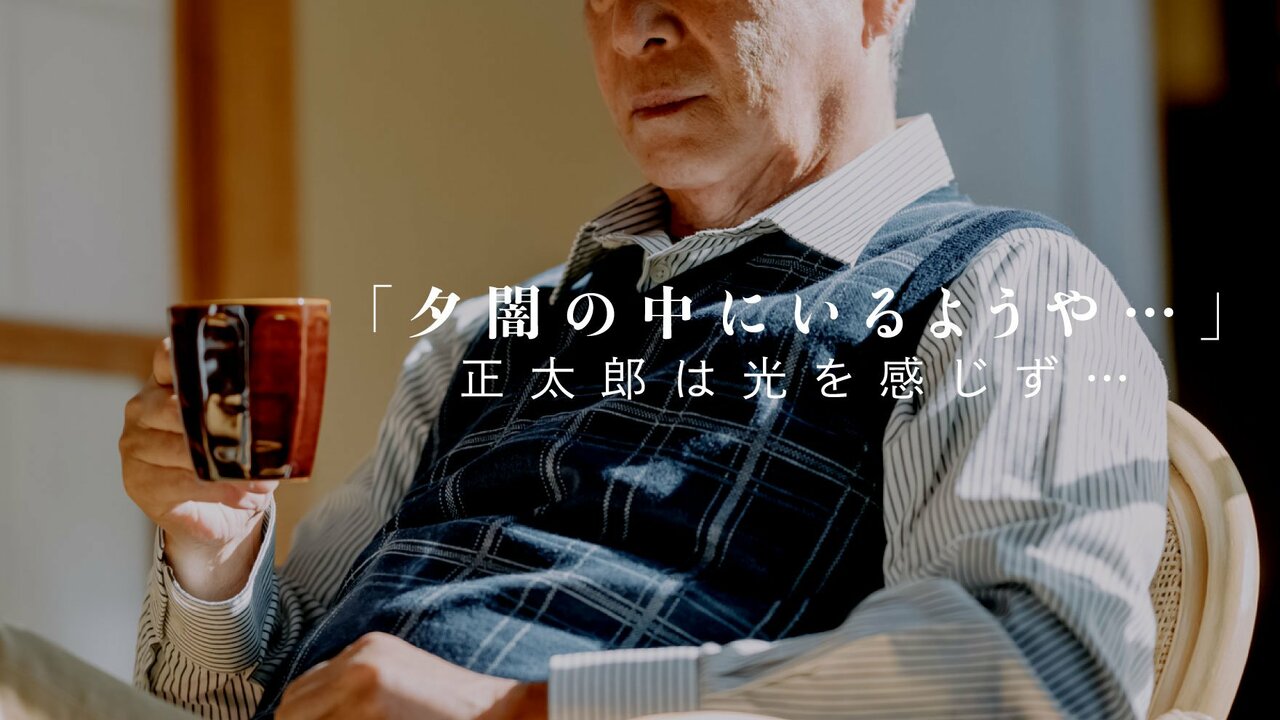【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
桜かがよう声よ
― はるか遠くの静かな友よ
感じるがよい
お前の呼吸がまだ空間を
豊かにすることを ―
〈リルケ『オルフォイスへのソネット』より〉
「ところでちょっとお伺いしますが、ニートって、本当はどういう人のことを言うんですか。圭二さんはニートなんでありますか」
浮世離れしてもらっては困るよといつものように世間話を盛り沢山にしたあと、受話器を握りしめる手は汗ばんでいるのだが、愉快そうにふざけた調子で訊ねるふゆ子に、
「僕は違うよ。ニートってのは働きも学びもしていない連中のことを言うんだからさ」
返事はすぐ返ってきたが、「そうだなあ、だけど僕はもう、そのニートの仲間にも入れてもらえそうもないんだよなあ」
「えっ? なに、それ」
「ニートってのはね、三十五歳までなんだってさ」
「三十五歳? へええ、それじゃあ、三十五歳を過ぎたら何て言うの?」
「さあ、どう言うんだろうな。ただの、無職者、寄生虫、ってことかな」
ふゆ子は一瞬、押し黙る。
次男の圭二の胸に底無しの穴があいている。穴がどんどん大きくなる。それを見て見ぬふりをしている母親の応答をどうしたものか。
仕方なく笑うことにする。
「あはは。そうですか、いよいよニートにも見放されちゃいましたか―。それはお気の毒さま」
「まあね。申し訳ないね」
「どういたしまして。こちらこそ」
本当は脚が震えているのだ。
けれども同時に、ふゆ子の目は目の前にある時計を睨んでいる。
「ごめん、おじいちゃんの目薬の時間だから―。今日は好江さんお休みだからね、切るよ」
「おじいちゃんの目、やっぱり進んでるの?」
「―みたい」
「それにしても相変わらずすごいボリュームだね、BGM」
「ああ、テレビ? 聞こえてるんだ」
「聞こえてる聞こえてる。朝から晩までそれで、おかあさん、よく気が変にならないね。おじいちゃん、耳は大丈夫なんやろ?」
「うん、まあね。でもやっぱり遠くなっているのよ、どんどん大きくなるわ。さすがに、おかあさん―」
で、止めた。
「じゃあね―」
受話器を置こうとして、
「大丈夫?― 持つ?」
圭二を呼び止める。
「―まあね、持たなきゃしょうがないだろ」
いつものことだが、このお互いの一瞬の間にぶら下がっている。
いつ切られるか分からない延命措置がとりあえず繋がったような、先行きの不安な束の間の安堵だ。圭二も同じように感じているに違いない。