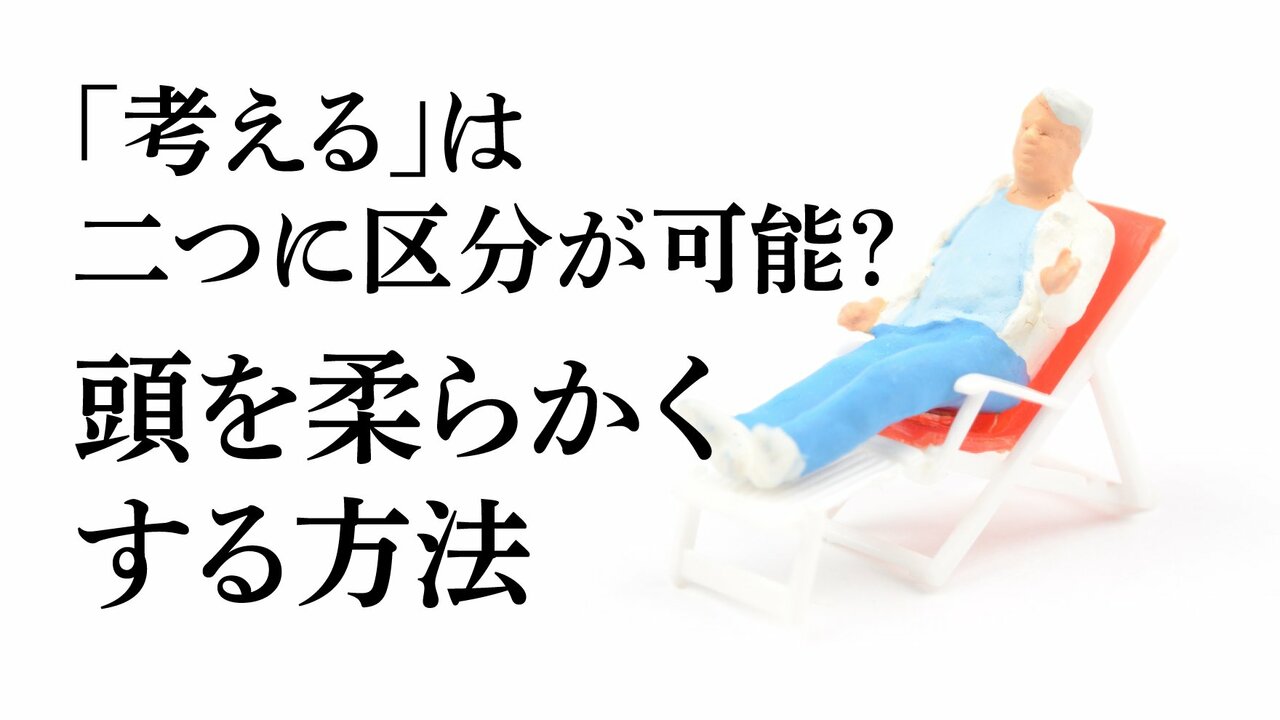「……おやじ、今まで、ずっと寝ていた?」
「何? 稔、眠れる訳ないじゃないか。俺とお母さんの二人は蒲団の中に入っていただけだ。まんじりともできるか、稔。たまには親の気持ちにもなってみたらどうだ」
父は怒るような声で言った。乱暴でも、訴え、願うような口調だった。
父のその言葉によって、若山洋子の勝手口から出て来た男は、凶悪犯の早川岩雄である、と稔はわかった。だが、稔の心は、重苦しい。なぜだろう?
生きていた早川岩雄は、二宮啓子のアパートとパチンコ屋で、自分を見ているのである。早川岩雄の恐怖の声は、稔の鼓膜を熱くするのだ。そんな気持ちなどまったくかまわずに、またもや電話がかかって来た。
「坊や、お前さんはいい子だ。だから、俺の言うことをよく聞くんだな。坊やが殺ったことをバラされたくなかったら、俺の言う通りにするんだ、いいかな」
「……」
「いいか、坊や、坊やの近くで若山洋子という美しい奥方が殺された事件があっただろう。あれは、お前の親父がやった、とデカに言うんだ。近頃、俺も住み心地が悪くなって来たぜ。デカが〝幻の早川岩雄〟を探し出そうとウロウロしていやがる。坊や、お前さんはお利口だ。わかったな」
電話は、プツンと切れた。
胸が張り裂けるほど、稔は苦しかった。〝若山洋子殺し〟は父がやったのではない。それを知っているのは自分だけなんだ。だが、父が憎い。
自分がこうなったのも父のせいだ。父は、俺が子どもの頃から今まで、俺と一度だって遊びに行ったことがあるか。遊びに行ったこともなければ、風呂に一緒に入った覚えもないのだ。父と俺とは〝血の糸〟が切れているんだ。俺が勉強しなくなった、とガタガタ言うし、金使いが荒い、と言っては怒る。あげくの果てに、ギターで頭をぶっ叩かれたことだってあるんだ。
俺は母だって憎い。豚のように太って、いつも煩わしく俺を罵っている。父と殺された若山洋子の間だって本当はどうなのかわかりはしない。その腹いせに、俺を怒るなんて母も母だ。若山洋子がいくら綺麗だと言ったって、父があの女に魅かれたのは、母に優しさがなかったからではないか、と思う。だが、母よりは父が憎い。
俺は迷う。迷うが、心の底では父に仕返しをして、打ちのめしたい、と思う。一晩中、寝床の中で考えたが、やはり、父を突き飛ばしたい。その気持ちは変わらなかった。こんなことを振り返ったり、考えたりしていると稔の気持ちは次第にいらだって来た。