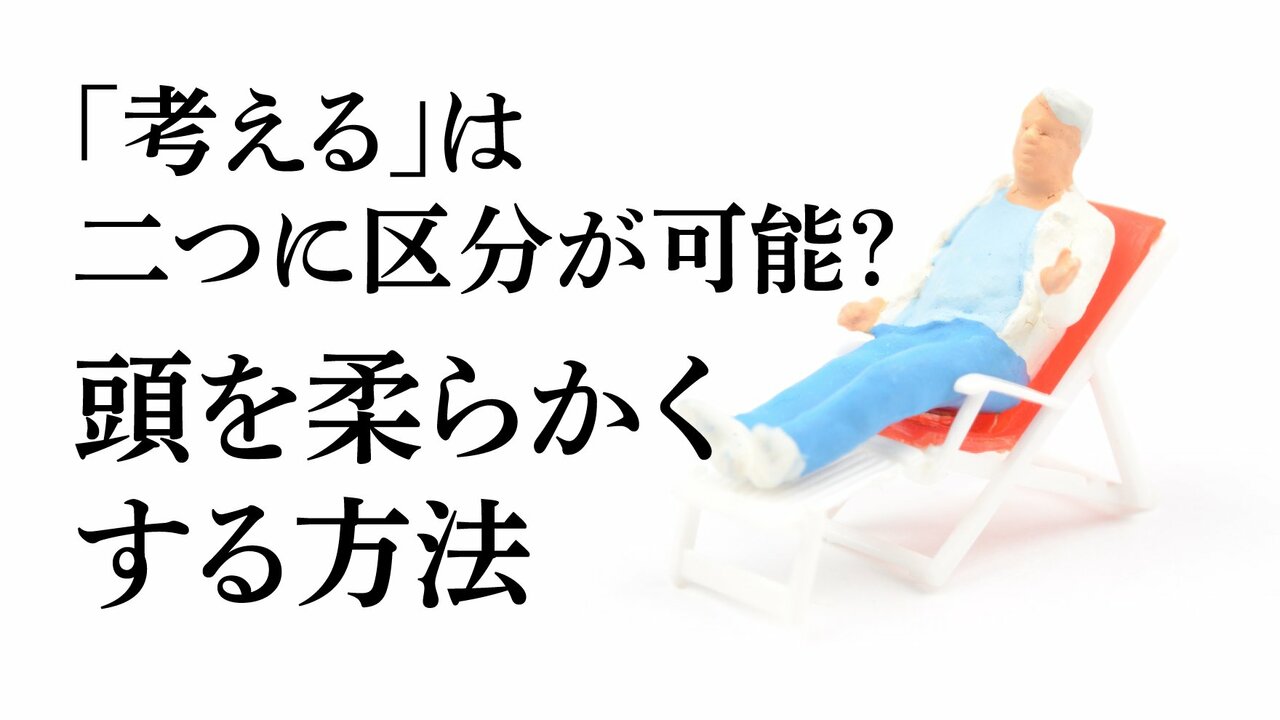【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
血の糸
下唇を噛み、男の顔を見た。
いや、男の鋭い視線から逃れられない状態だった、と言ったほうがいい。
男は、稔の頭から足までまじまじと見てから、あからさまに眉をしかめ、
「兄サン、荒れていたな。すぐにお帰り」
ドスの効いた声で言った。
稔は、「はい」、と答えるしかなかった。
急き立てられるようにその場を離れると稔は、パチンコ屋の出口近くの椅子を蹴って、表に出た。
しばらく訳もわからずいらいらして歩いていたが、ふと、あの男の顔は、どこかで見たような気がする、と思った。男の髪形が変わり、無精髭を生やしているが、あの男に間違いない、と思い浮かべた。その時、稔の背筋に冷たいものが走った。
9月の半ばだった。
香村稔は電話を受けた。受話器から低い男の声がした。
「……お前は、香村稔だな?」
「……うん、そうだけど?……」
「久しぶりだな。お前は結構贅沢な暮らしをしていやがるじゃあねえか。パチンコ屋でもよく遊んでいる。身のほども知らねえで」
「……あの、あなたは、どちら様でしょうか?」
「どちら様もクソもあったもんじゃあねえや。坊やは、早くもお忘れかね。坊やが、あのアパートでヤバイ仕事をなすったことをな」
稔は、それを聞いて生唾をごくりと飲んだ。心臓が激しく打ち出した。
「坊や、バラしてあげようか、ヘ、ヘ、ヘ、ヘ、ヘ、ヘ」
と男はしゃがれた声で笑った。
電話を切っても、稔の胸は疼いていた。あの日の記憶が、疼いている胸を刺してきた。すべてを葬ってしまいたいあの記憶。あの行為の後のことを思い出した。
それは稔が、二宮啓子のアパートの階段を、足音をしのばせ、かつ、速足で駆け下りた時のことである。