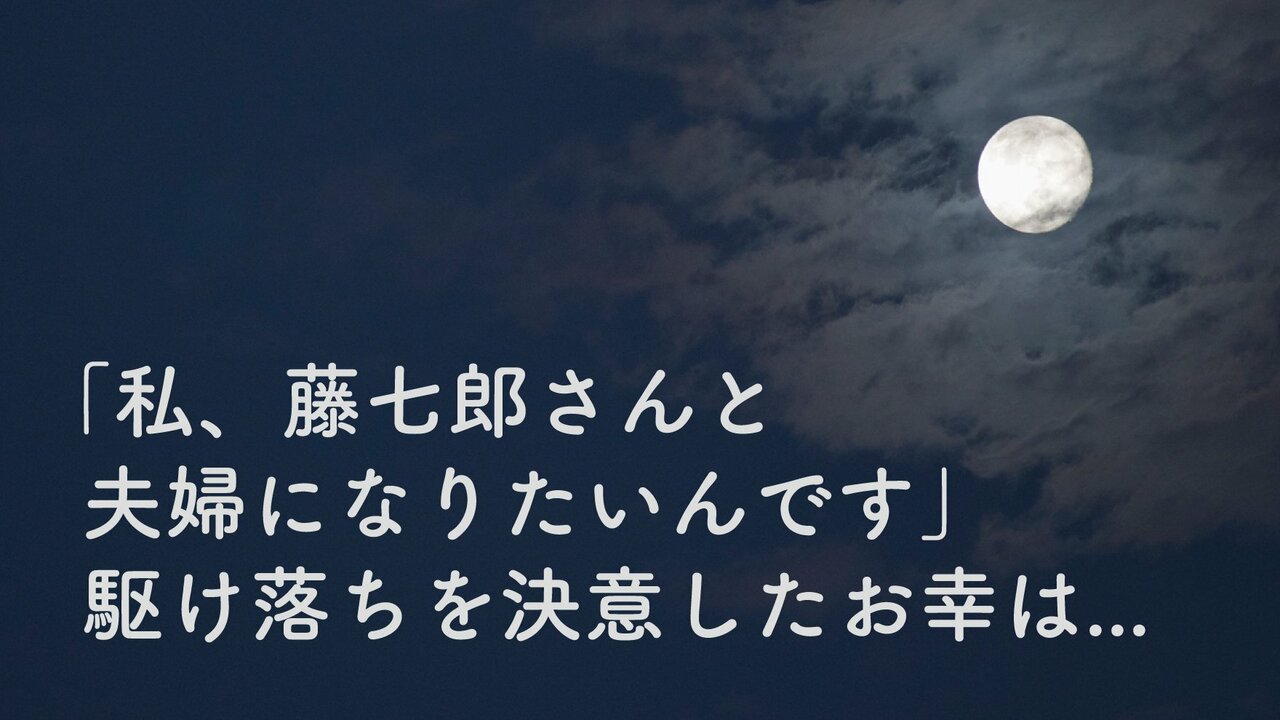【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
来客
テレビ局の例のディレクターはどうなるのだろうか。
気になって先日のディレクターとの話をすると、港は「ああ、あそこは僕が少し出資しているからスポンサーが僕だと言えば二つ返事で了承してくれると思うよ」と涼しい顔をして言った。……次元が違う。一体この男は幾ら儲けているんだ。
「仕上がりはどのくらいになりそう?」
「急かすなあ……。最短でも二ヶ月だよ」
「成程。じゃあ、その間にプロジェクトを立ち上げて企画を進めていくよ。役者も希望があれば声を掛けるけど?」
「顔が広いな」
「それ程でも」
はにかんで頬を掻くこの友人は私とは違ってデビューしてから二十年経った今でも色々な番組に引っ張りだこだ。
本人はバラエティーは余り好まないようだが、繋がりが作れるし芸の肥やしになるなら、と余程肌に合わない事以外は引き受けている。学生の頃から多才な奴だと思っていたが、こんな風に成るとは当時誰も予想していなかっただろう。
おまけに五年前に独立して事務所を立ち上げている。出資したのは港だと聞いた。
船上で開かれた由津木主催の豪華絢爛なまでにきらびやかなパーティーは、いち庶民の私には場違いな気がして居心地が悪かったのを覚えている。
「お前が企画を立ち上げるって事はお前の事務所が主催なのか?」
「恐らくな。だが希望があれば他でもフリーでも声を掛けると言っただろう」
「そうか」
少し考えてみるか。こういうものは実際に俳優や女優を当て嵌めた方が筆も進む。
大まかな登場人物でも決めておいた方が由津木も動きやすいかもしれない。
「じゃあ、俺がだいたい考えている配役を聞いてくれるか?」
「もちろん」
私の提案に「やれやれ長くなるぞ」と店を閉めに行った御巫を見送ると港が持って来た茶菓子を片手に小さな会議が始まった。
あの小説は、お菊が実は十年前に情死した太夫の娘だったこと、何の因果か近江屋へと来たこと、そのままつつがなく幸せに暮らしたというところで話は終わっていた。どうにも座りが悪い終わり方だった。お弓の子供がどうなった、という話は載っていなかった。そこで、私はあの本の出版社に問い合わせ、承諾を得ると、この話を借りて物語の続きを創作することにしたのだ。
あの小説の中ではお菊が主のようなものであったが、あくまでも私の小説の中ではお菊は脇役。主役は近江屋に残されたお美代、もといお幸だ。
この子の運命を書いてみたいと思った。
御巫が太鼓判を押してくれたんだ。
いつになくやる気になった私は、気に入りのマグカップへとコーヒーを注いで、少しばかり上等の万年筆を片手に執筆を開始した。
***
「お幸にもそろそろ縁談を、と思っているんですが」