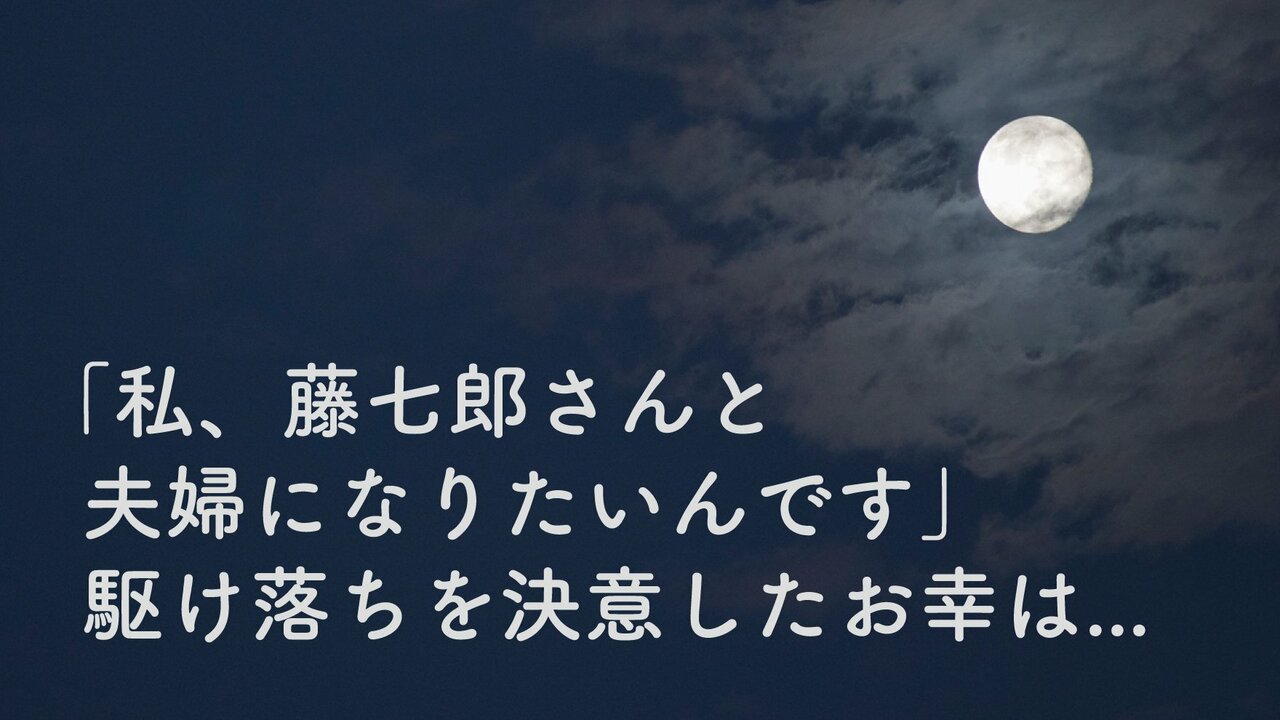「そうだなあ、藤七郎やお菊のおかげで随分と人見知りもなくなっているし、それもあってか店にも顔が出せるようになったからな」
藤七郎やお菊が来てから半年も経つ頃には、お幸の人見知りもすっかり、とまではいかないが、だいぶよくなっていた。店番もすすんでするようになり、馴染みの客とくらいなら会話もある程度はできるようになっていた。
それもあって、先延ばしにしていたお幸の縁談をすすめようか、という話が持ち上がっていた。大旦那の与七もおかみのお吉もお幸に、というよりはこの米問屋を背負って立つ人物――若旦那がいないかとあちこちに声を掛けてはお幸に話をもっていったが、お幸はどうも納得しない。
どうしたものかと頭を悩ませていると、お菊が与七とお吉に話があると言ってやってきた。
「どうしたんです?」
「お幸ちゃんのことなんですが」
「お幸の?」
「はい、縁談の……件なんです」
「縁談の――、……まさか、他に懸想している相手がいるとでも? そう言うのかい?」
「――はい。でも、まだ私にもはっきりとはわかりませんが、おそらく藤七郎ちゃんを想っているんじゃないかと」
「……なんだって?」
「お幸ちゃん、縁談の話のあとは必ず私のところに来るんですがね。視線の先には必ずと言っていいほど藤七郎ちゃんがいて。それでもしや、と思ったんですよ」
「まさか……」
与七とお吉は目を見合わせた。
お幸が藤七郎を思っているなど、夢にも思わなかったのだ。
「……藤七郎か」
「……一旦、縁談の話をやめて、様子を見てみましょうか。お幸の行動も私たちで確認しましょう」
「そうするか」
与七たちは小さく溜め息を吐くと、お菊を下がらせて、当面は二人の様子を見守ることにした。お幸はともかく、藤七郎がお幸をどう想っているのかもわからないからだ。これからの二人を見て、仲を認めるかどうかを判断することにした。
* * *
「こんな感じ、か」
万年筆を置いて一息つく。
この本を出版した会社へ問い合わせて、名前はそのままに、脚色を加えたオマージュ作品にすることにしたのだ。
〝メリーバッドエンド〟
それがこの作品のテーマとなる。
メリーバッドエンドとは、インターネット上で生まれた言葉であるらしい。
読者側からすればバッドエンドであっても、物語の登場人物からすればハッピーエンドな結末、ということをさすのだそうだ。逆もまた然りである。
心中という言葉はメリーバッドエンドを説明するに相応しい事例であると思う。
今までは登場人物の幸せイコール、それを取り巻く人々、ひいては読者の幸せだと思って書き続けていたし、それが私のスタイルだった。
二十年という節目、そのイメージを覆すのもありだろう。
世の中に受け入れてもらえるかどうか、はなはだ不安ではあったが、新境地だ。最近は筆も乗っているし、久しぶりに執筆が楽しくて仕方がない。いい傾向だと、妻は笑っていたが。
「さて」
ぬるくなったコーヒーを飲み干して、新しくマグカップへと注ぎ、また原稿用紙と向かい合った。