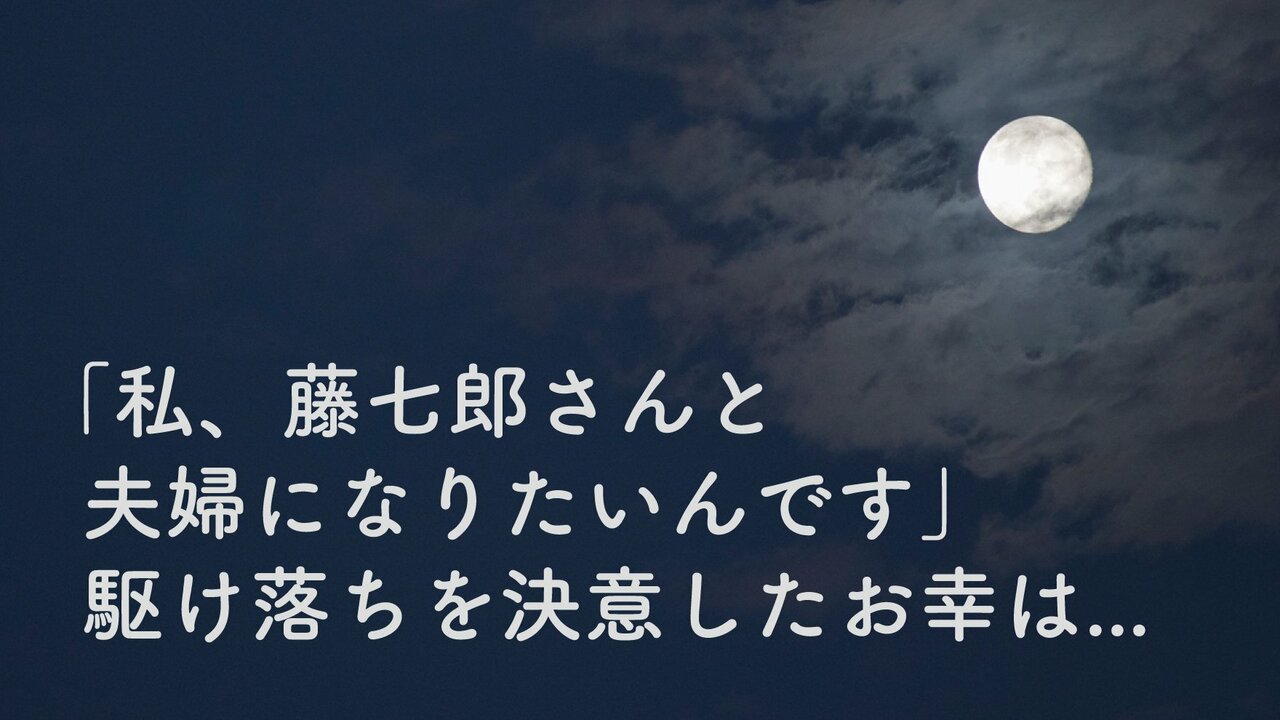【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
来客
「大方、由津木(ゆいつき)にも話したんだろう」
「――よく、分かったな」
「時代物と言ったら旬な俳優はアイツじゃないか」
「確かにな」
「ぴったりだと思うが」
「そうか」
私の返しに「ああ」と短く返事をすると、「オマージュか」とポツリと呟いた。
「そうだ」
「君にしちゃ珍しいな」
「恐らく初の試みだ」
「それはまた」
くつくつと笑う友人はきっと私の意図を分かっているに違いない。
伊達に長い付き合いはしていないな、と思ったがコイツはどうも人の心中を察することに長けているらしい。そういえば学生時代の影の渾名はサトリだったか、なんてどうでもいい事を思い出した。
「てっきりパロディものにすると思っていたんだがな」
とはなす友人に簡素なプロットを渡した。如何せん知識が曖昧なもので、何か不備がないか少し確認して貰いたかった。大抵は自分にある程度知識がある事柄を題材にする。
その方がうまく説明できたり話を展開しやすいからだ。だが今回は全く分からない――それこそゼロからのスタートだ。
多少見聞きして覚えがある中途半端な事は変な先入観が入りやすい。この友人は編集部ではしてくれない事をやってくれているから、こうして頼る事も実は少なくはないのだ。
「――良いんじゃないか?」
「本当か?」
「僕が嘘を言って得することは何も無いと思うんだが」
「そうだが……」
何時もならば二、三訂正が飛んで来る。寧ろ飛んで来ない時はない。明日は雪か、と本気で心配した。
「君、今とても失礼な事を考えただろう」
私の微妙な表情を目聡く見つけた友人は軽く睨みつけてきた。
苦笑しつつ謝罪を述べれば呆れを含んだ溜め息が一つ返って来た。
「これで進めても良いだろうか」
「僕は良いと思うけれど。最終的な判断は自分ですることだね」
確かにその通りだ。違和感がないか、ということを見てもらいたかったのだが、実を言うとこの友人が興味を持ってくれないかと考えたのだ。過去にも御巫が興味を持った作品は売れ行きが良い。
私の小説はマイナー向けだとよく評されるのだが、その枠を超えて多くの人に買ってもらえることが偶にある。それが、この友人が興味を引いた題材なのだ。
私は趣味が高じて小説家になった。御巫とは性格こそ逆だが趣味嗜好が驚くほど合った。ジンクスを信じている訳ではないが、御巫がわざわざ購入してくれる本は通常の七、八倍ほど売れたし、一度は直木賞候補にも上ったのだ。