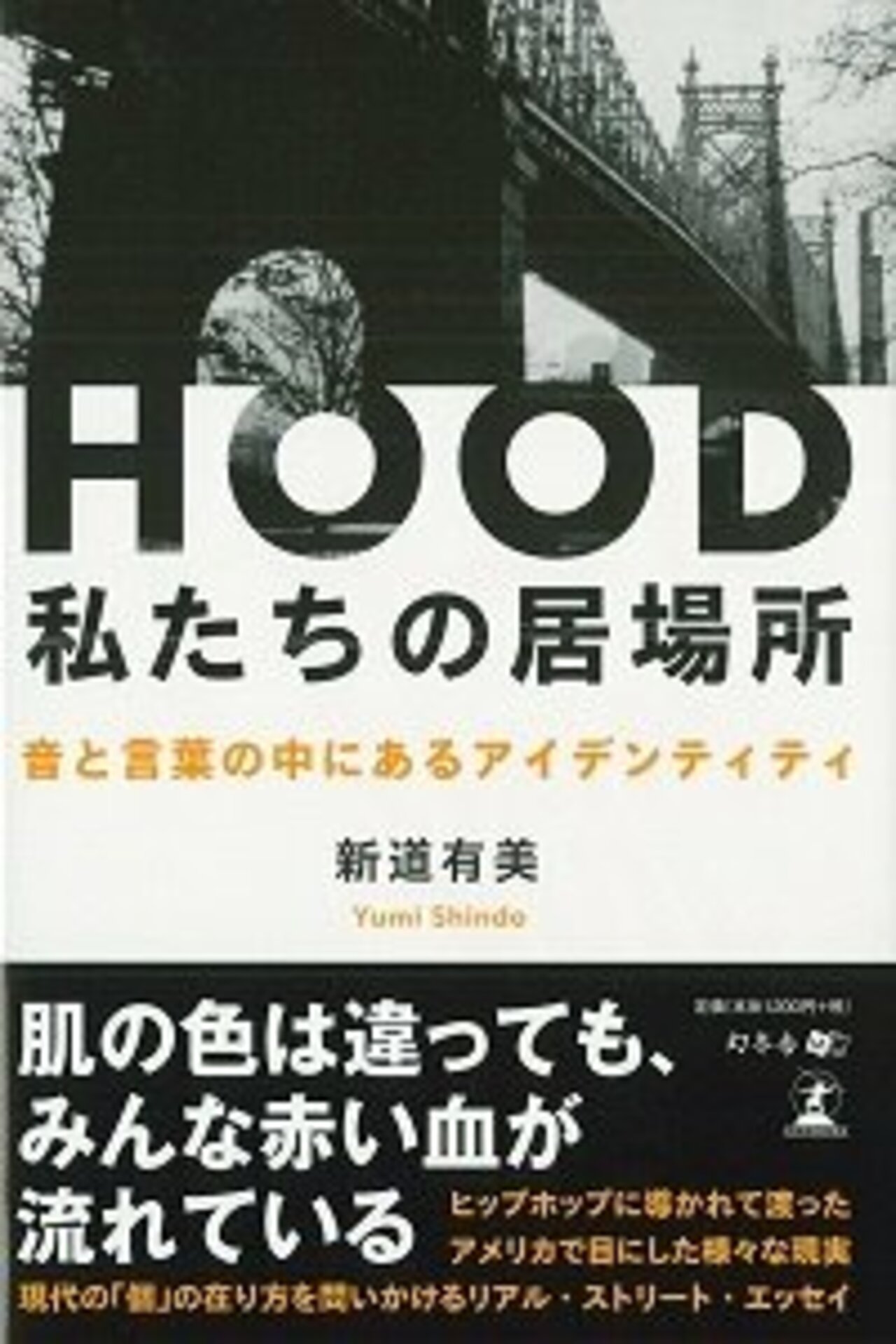Bの従兄弟が咄嗟に立ち上がった。突然、扉が勢いよく開けられ、一人の女性が部屋の中に入ってきた。
「彼のママだよ」。
Bが私の耳元で言った。何が起こったのか私には全くわからないが、ママの凄まじい剣幕から、彼に対して腹を立てていることだけはわかる。ママは両手を激しく振り上げながら息子に詰め寄り、言葉をまくし立てている。
彼はママの勢いに圧倒され、ヨロヨロと後ずさり。必死に何かを伝えようとするが、ママは全く聞く耳なし。「わかった、わかった」。彼は、そう言いながらママを部屋から追い出そうと身体をグイグイ押す。
「ヤレヤレ、まいったぜ」。
そんな表情を浮かべながら、彼はママと一緒に部屋から出て行った。私たちは何事もなかったように、Ludaのラップに再び耳を傾けつつ、まだ酒をチビチビと飲み続けている。
ふと床に目を落とせば、小さなゴキブリがせわしく動き回っている。正面には、Snoopのフィギュアが立っており、サングラスの奥にある目が私を捉えて離さない。ギラギラ光ったスーツはピンプ(ポン引き)を思わせる。
「私、Snoopの大ファンだったの。すっごいcute(キュート)だったし、ファースト・アルバムは最高だった」
「ファースト・アルバム、あれはまさにClassic(傑作)だぜ。ヤツは、すげーcoolだぜ。キミは彼のこともう好きじゃないのか?なんで?」
「ピンプみたいなんだもん」。
Bは興味深そうに私を見て笑った。窓に掛けられたカーテンを手で退けながら私は外を眺めた。「こんなに高いんだぁ」。私は思わず呟く。ここからであれば、ダウンタウンまで見通せてしまいそうな気がする。
実際は、先の先を見てもプロジェクトだらけ。茶色のレンガでできた高層ビルディングが、ニョキニョキとコンクリートから背を伸ばす。
ずっと先にぼんやりとセントラルパークが見える。気が付けば日が暮れてきた。Bたちは今夜、ミッドタウンで大切なミーティングの予定がある。そろそろ帰った方がよさそうだ。
Bが地下鉄まで送ってくれると言う。私たちは部屋のドアを開け、廊下に出た。キッチンでは、まだBの従兄弟がママとやり合っている。ママの方が圧倒的に優勢に見える。