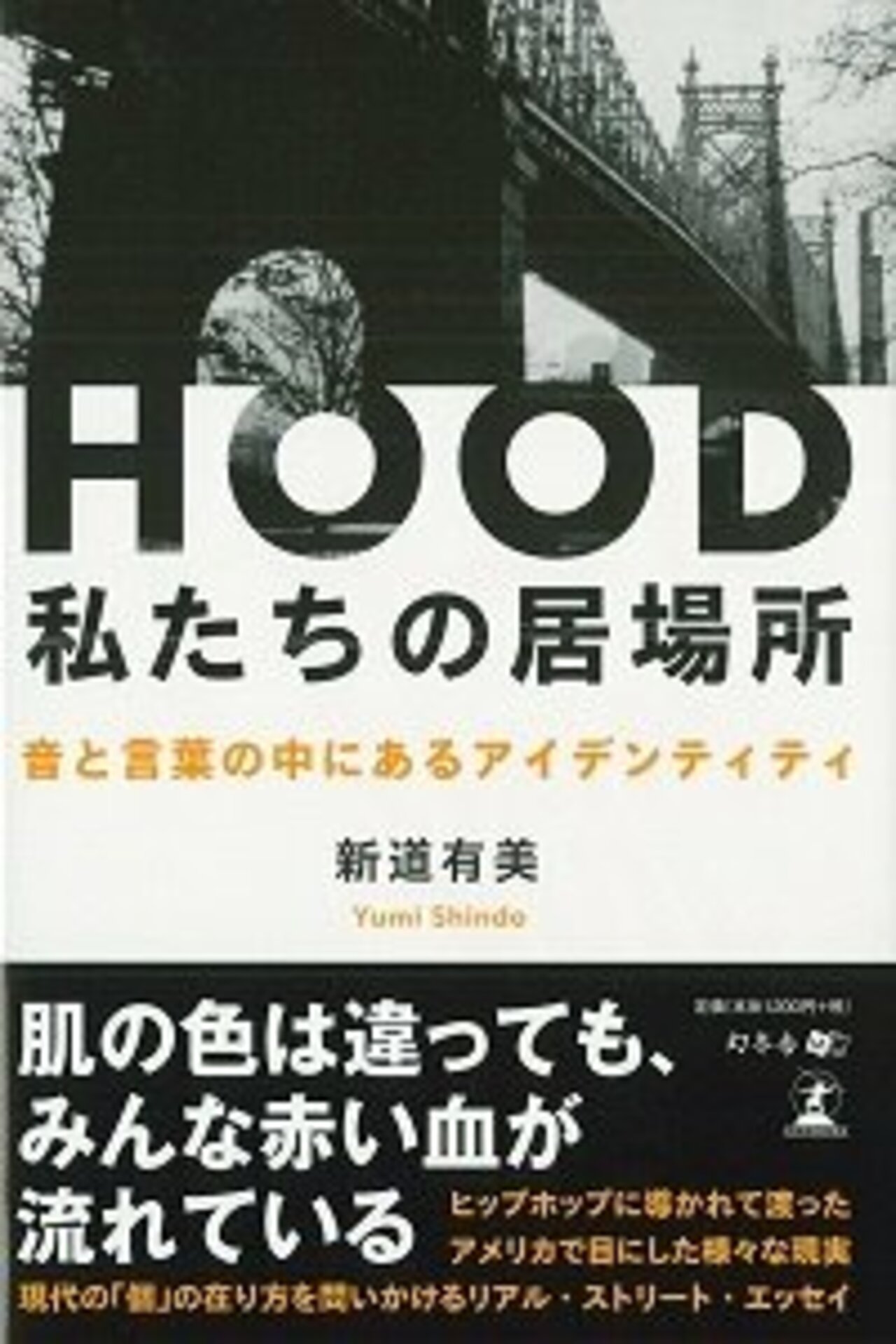ハウス・パーティ
アパートを出て、通りを駅の方へと小走りで下っていく。
ちょうど大きな交差点で背の高い男性の姿が見えた。Sだ。彼は私の頭のてっぺんから足先までざっと目を通してから、私の顔に視線を戻し、微笑んだ。
“What’s up, Yumi?”
“I’m alright. You?”
“I’m good.”
“Sorry, I’m kinda(=kind of)late.(ごめん、ちょっと遅れちゃった)”
“Nah(=No), that’s okay. You look nice.(いいよ。別に構わないさ。素敵だよ)”
Sはそう言うと、もう一度上から下まで眺めた。日本では、パーティ文化がそれほど盛んではない。改めて自分のお洒落度を試される場や機会というのが比較的少ないように思える。
私はさり気なく彼の服装に目を遣った。グレーのストレートパンツに薄いブルーの襟付きシャツ。その上に黒のレザージャケットというスタイルだ。
足元は黒の革靴。髪の毛はコーンローにきっちりと編み込まれている。
2人で横断歩道を渡り、駅の階段下に停めてある車に向かう。
Sが開けてくれたドアから中に入ると、彼のお父さんが黙って運転席に座り、真っ直ぐ前を向いていた。
「こんばんは。お待たせしてしまって、すみません。」
声をかけると、お父さんは一瞬、顔を動かしたように見えたが、無言のまま車を発進させた。ブロンクスからブルックリンへ。車は猛スピードで道路を突っ走って行く。まるでカーレースかのごとく、スピードが決して緩められることはない。走るか止まるか。お父さんにはその2つしかないようだ。乱暴な運転に思い切り振り回される。
私は車内のドアや天井の横に付いているアシストグリップを必死に握りしめた。後部座席からフロントミラーに映るお父さんの目はとても鋭く、私をさらに緊張させる。愛想のひとつも見せず、非常にぶっきらぼうな態度。少し待たせてしまったために、機嫌を損ねているのだろうか。
どのように声をかけ、どのような話をしたらいいのかといろいろな考えが頭の中を駆けめぐるが、私の不安な気持ちをよそに、Sは暢気にiPodで音楽を聴いている。誰かのラップがイヤホンから漏れている。どれほどの大音量なのか。そして車内には、お父さんが選局したと思われるラジオ番組からラテン系の音楽が流れている。
「ま、いっか」。私はふとそう思った。
お父さんとSの様子を見て、気付いたのである。この場の空気を気にしているのは、実は私だけだと。おそらく彼らは、言いたいことがあれば、はっきりと言うだろう。何も言わないということは、何も問題がないということなのだ。そう考えると、急に気持ちが楽になる。
午前1時過ぎ。ブルックリンに到着した。お父さんはエンジンを切り、勝手に車から外へ出た。
「着いたみたいだ。」
Sが言った。
私たちはパーティ会場となる家の前に向かう。
「ちょっと待ってろ。」
お父さんは固い表情のまま、先に階段を下りる。主催者である知人に挨拶をしに行ったようだ。5分ぐらい経ち、お父さんが「下に来い」と合図を送った。私たちは地下まで続く小さな階段をゆっくりと下りる。
入口付近には、若い人の姿はなく、お父さんと同世代の男性が数人立っている。
私は少し落胆する気持ちを隠しつつ、音楽が聞こえてくる方向へとさらに進んで行く。会場が見えてきた。暗闇でも、多くの人でフロアが埋め尽くされている様子がわかる。中をよく覗いてみると、そこには若い世代からお年寄りまで、男女が酒を飲み、話に興じ、踊っている姿があった。私は興奮する気持ちを抑えながらSの後ろに着いていく。今夜はどんなパーティになるのか、非常に楽しみだ。