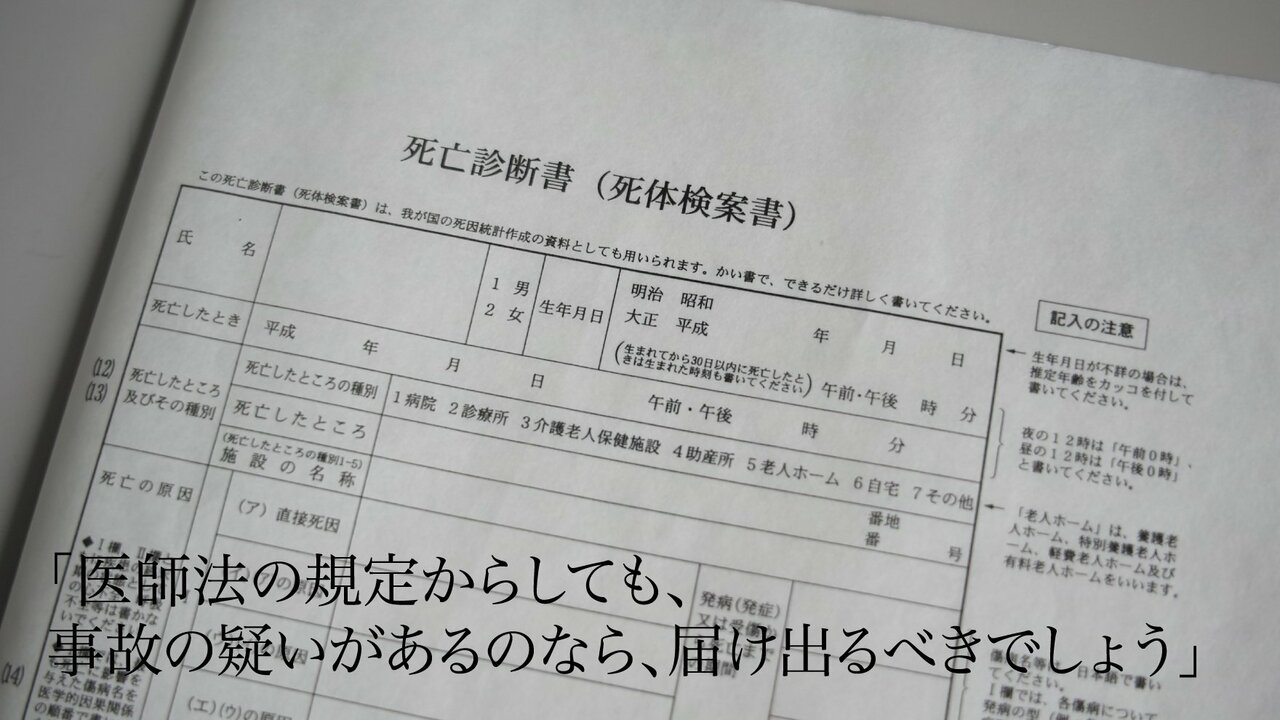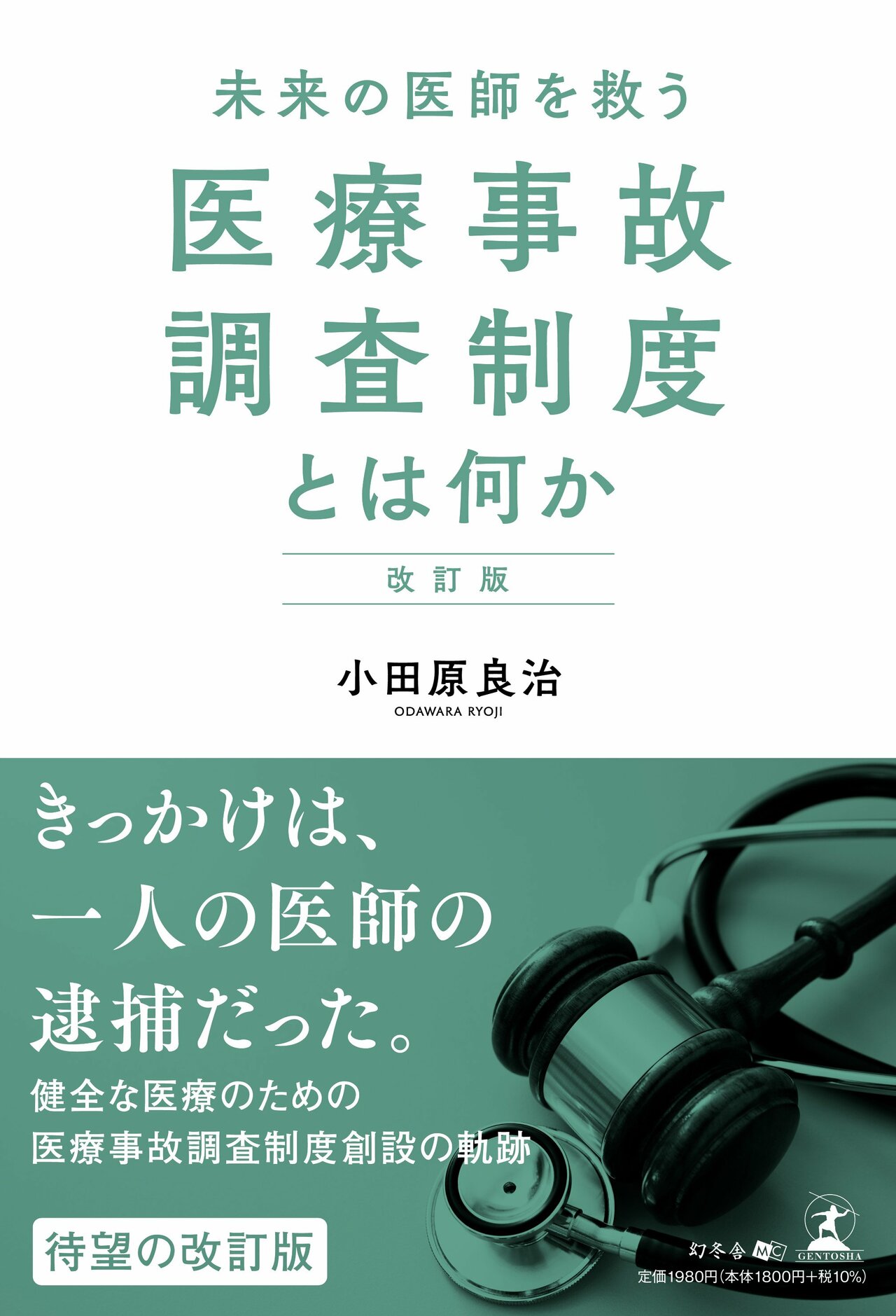東京都立広尾病院事件東京地裁判決
D医師は、Aの主治医であり、Aは術前検査では心電図などにも特に異常は見られず、手術は無事に終了し、術後の経過は良好であって、主治医としてAについて病状が急変するような疾患等の心当たりが全くなかったので、E医師から看護師がヘパロックした直後、Aの容態が急変した状況の説明を受けるとともに、看護師がヘパロックをする際にヘパ生と消毒液のヒビグルを間違えて注入したかもしれないと言っている旨聞かされて、薬物を間違えて注入したことによりAの病状が急変したのではないかとも思うとともに、心臓マッサージ中に、Aの右腕には色素沈着のような状態があることに気付いており、そして、Aの死亡を確認し、死亡原因が不明であると判断していることが認められるのであるから、D医師がAの死亡を確認した際、その死体を検案して異状があるものと認識していたものと認めるのが相当である。
そしてまた、D医師は、Aの死体を検案して異状があると認めた医師として、警察への届出義務を有するものであるが、対策会議において、警察に届け出るか否かについては、J副院長が医師法の話をしていたのを聞いており、本件が看護師の絡んだ医療過誤であるので、個人的に届け出ようとは思わず、都立広尾病院としての対処に委ねており、被告人も、この点については、対策会議を招集して協議し、都立広尾病院として対処することとし、誤薬投与の可能性を熟知しながら、J副院長の「医師法の規定からしても、事故の疑いがあるのなら、届け出るべきでしょう」との発言を始め、
他の出席者も「やはり、仕方がないですね。警察に届けましょう」との意見を表明したことから、医師法の規定を意識した上での警察への届出を決定しながら、病院事業部から「これまで都立病院から警察に事故の届け出を出したことがないし、詳しい事情も分からないから、今からすぐに職員を病院の方に行かせる」旨の連絡を受けて、被告人を始めとする対策会議の出席者は、最終結論は、病院事業部の職員が都立広尾病院に来てから直接その話を聞いてきめることとし、それまで警察への届け出は保留することに決定することによって、医師法第21条にいう24時間以内に警察に届出をしなかったことが認められるのであるから、被告人は、死体を検案して異状があると認めたD医師らと共謀して、医師法第21条違反の罪を犯したものと認めるのが相当である。