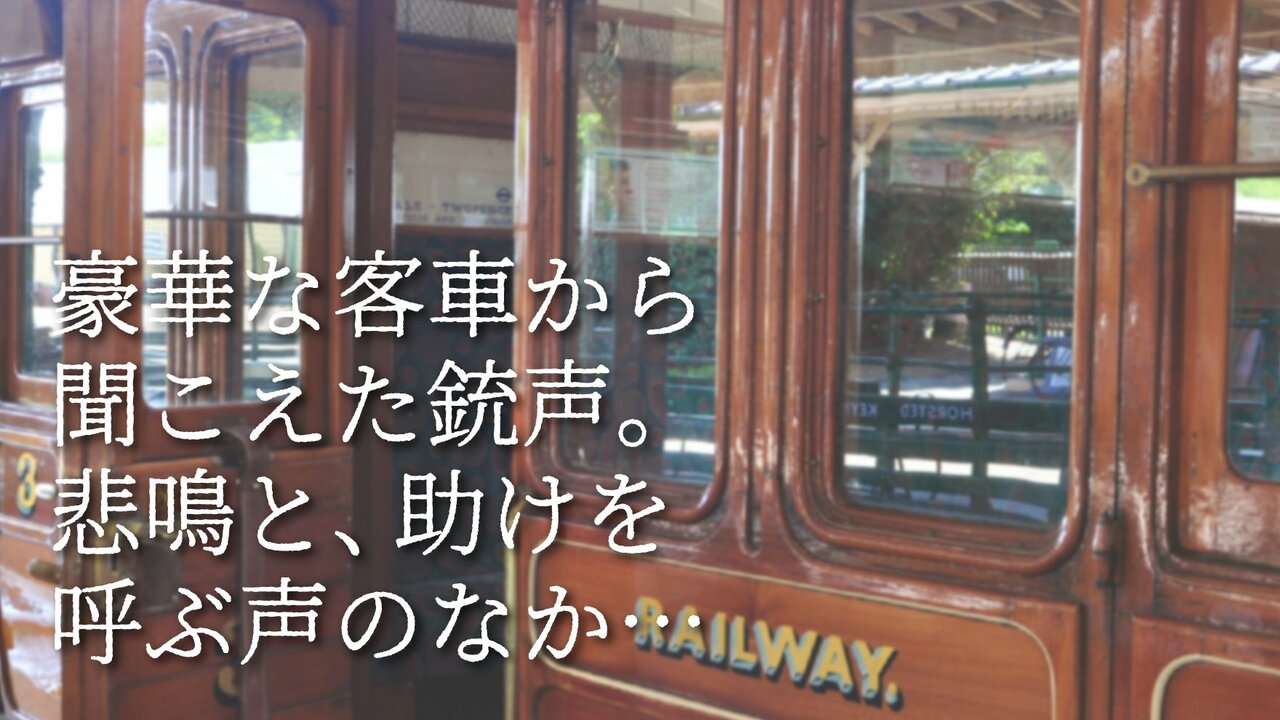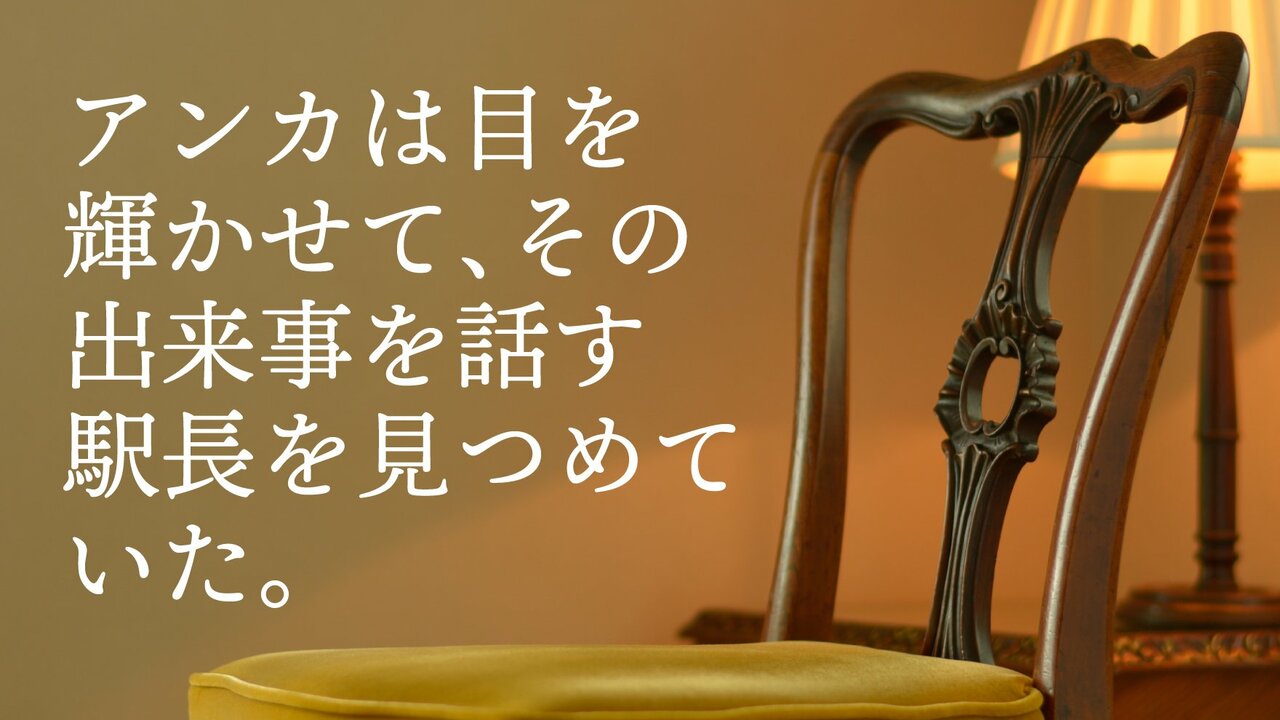第二章 手錠、運送屋、そしてアメリカの漫画 一九〇九年/一九一九年 ベオグラード
部屋には、今、制服姿の看守と、やせっぽちの人物が立っていた。その人物は、少なくとも二サイズ大きい、灰色縞模様の粗末な囚人服を着て、狭い肩越しに毛布を引っ掛け、細い手の関節のところには手錠が付けられていた。
【注目記事】「発達障害かもしれない職場の人」との関係でうつ病になった話
囚人帽がその眼をほとんど隠して垂れ下がっていて、帽子の下からは、汚くて明るい色の髪がはみ出ていた。そして、深い陰影のある顔の中で生き生きとしたところは、ふたつの眼の燃えるような斑点だけだった。落ち着きのない、野獣の目つき。ディミトリイェヴィチはグラスを置いて、ゆっくりと立ち上がって、その奇妙な二人組に近づいた。口ひげをはやした看守については無視した。彼はピンと背を伸ばして大尉の面前で凍り付いていた。
「その女の帽子をはずせ!」と、ミレンコヴィチがせきたてるように言う。看守は、はっとして、囚人の頭から湿った布地を剥ぎ取る。
今や、ディミトリイェヴィチも自分の前に立っているのは十代半ばの長身の少女だと分かる。髪を短く切りそろえ、頬は溶けた雪で濡れて汚れている。ぷりっとした唇が青味がかり乾いていた。
「ターサ殿、この少女は誰ですか?」大尉は自分を見つめ続けている青い眼から視線をそらさないで尋ねた。
「誰を連れてこられたのですか?」
ミレンコヴィチも起き上がり、ディミトリイェヴィチの隣に立つ。
「警察の仕事を始めて以来、わしがどれだけの間働いてきたか、ご存じですな。大尉殿。若い犯罪者や、泥棒、非行者、詐欺師たちをわしは矯正してきたんじゃ。手遅れになる前に、不名誉な仕事にどっぷりと浸かる前に、ね。わしは、時には成功をおさめることもあったが、多くのケースでわしの努力は無駄に終わったと言えるだろうな。でも、貴方の執務室の床じゅうを濡らしているこの少女は、今に野良猫のように思いっ切りひっかきそうに見えるが、貴方の目的からすると興味ありと言ってもらえそうだ」
「でも、この人は女性です」と、ディミトリイェヴィチは叫び、輝いている眼から視線をそらして、ターサ・ミレンコヴィチのほうを振り向く。