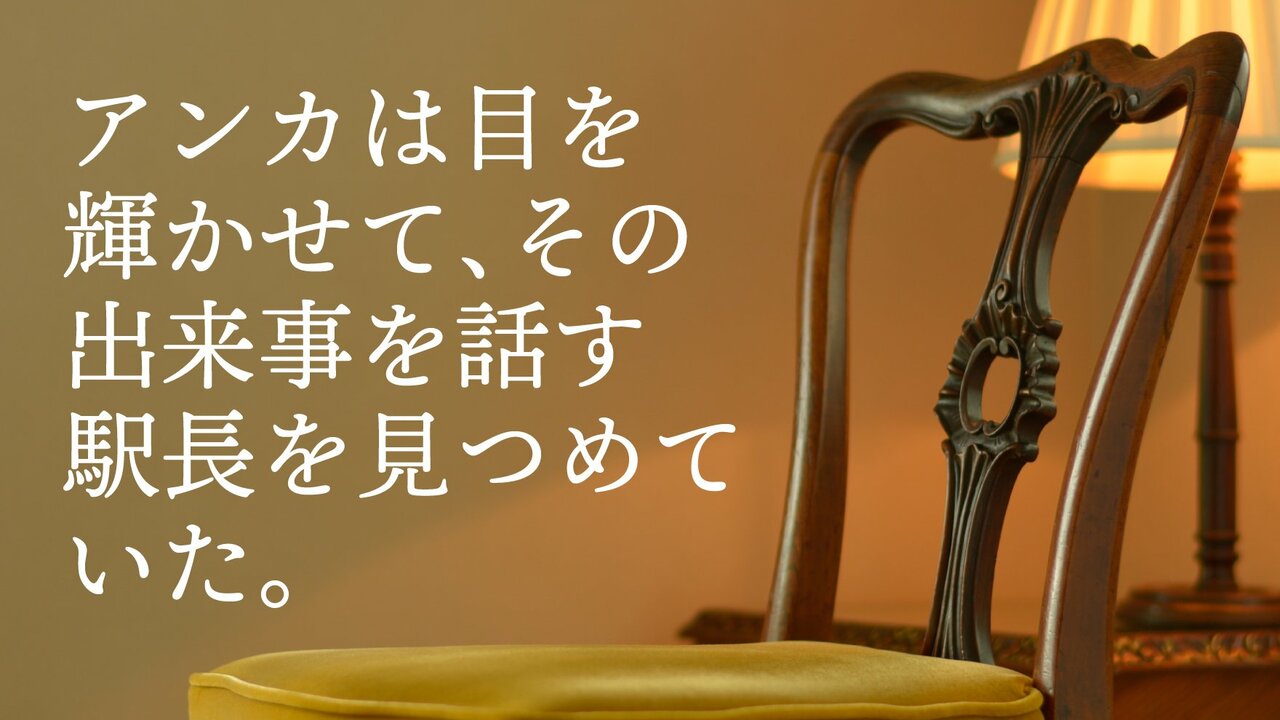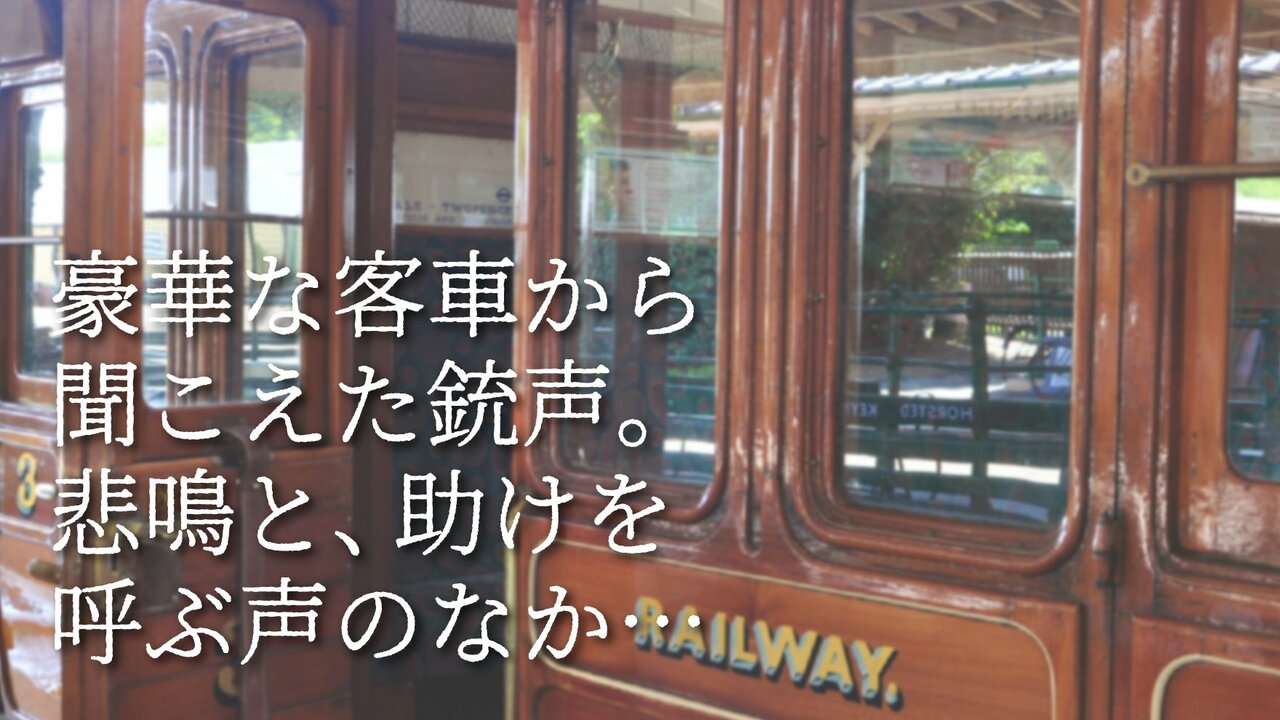一九一五年二月 イストリア半島
「ここにお泊りいただきます」
コート姿の中年男が親切にアンカに言った。グレーの口ひげをたくわえ、濃い眉毛の下から生き生きとしたまなざしで見つめている。
その時彼らはパジンの深い洞窟の上に建つ大きな石造りの建物の前に立っていた。洞窟からは奔流のざわめきが冬の薄暗がりを突き抜けてきていた。
「宿屋ダニイェリ」
と、アンカは、玄関前の大きな木の看板を見て言う。
「所有者はイタリア人ですか?」
「いや、違います」
男が微笑む。
「ダニイェリは、パジンから二十キロ離れたところにある小さな町で、おかみさんのファビリス夫人は、そこの出身です。ここには素晴らしい自家製料理があります。あなたがお部屋で一息ついたところで、夕食をご一緒させていただけませんか?
なかなかのハムとチーズ、ニョッキにイストリア牛のグヤーシュ、ヤマドリタケのフライ、そして良いビール、或いは赤ワイン一杯でもどうですか?お嬢様の好きなものにしましょう」
アロイズ・ヴリシェルはスロベニア人だが、長年イストリア半島で仕事をしていた。時々、ドイツ語、スロベニア語、イストリア方言をごっちゃにしてぎこちなく話した。
彼の『ち』の発音はあり得ないほど柔らかくて、アンカは、それがとても気に入っていた。
イストリア牛のグヤーシュがどのようなものかアンカにはよく分からなかったが、ロビー階の料理場から漂ってくる香りをかいでみたところ、とてもおいしいものだと、少しも疑うことはなかった。
アンカは貴重品の入ったスーツケースを置き(全ての預け荷物はオパティヤに直接運ばれ、翌日、アンカはそこで荷を受け取ることになる)、一階にある部屋から降りてきて、ヴリシェルがおかみさんに紹介してくれたので慇懃にあいさつした。
それからイストリア半島の美味しいものを食べながら他愛のない会話をしていた。
「明日朝、朝食のあとに参ります」
と、ヴリシェルがアンカに言った。
「車でオパティヤにお連れします。船までは、ロシアの貴族が所有するクルーザーに乗っていただくように手配しています」
アンカはプリビチェヴィチから、きっぱりとした連絡メモと他の指示書を受け取り、その中で、ヴリシェルがセルビアのゼムン市で二年間働いていたことを読み取っていた。