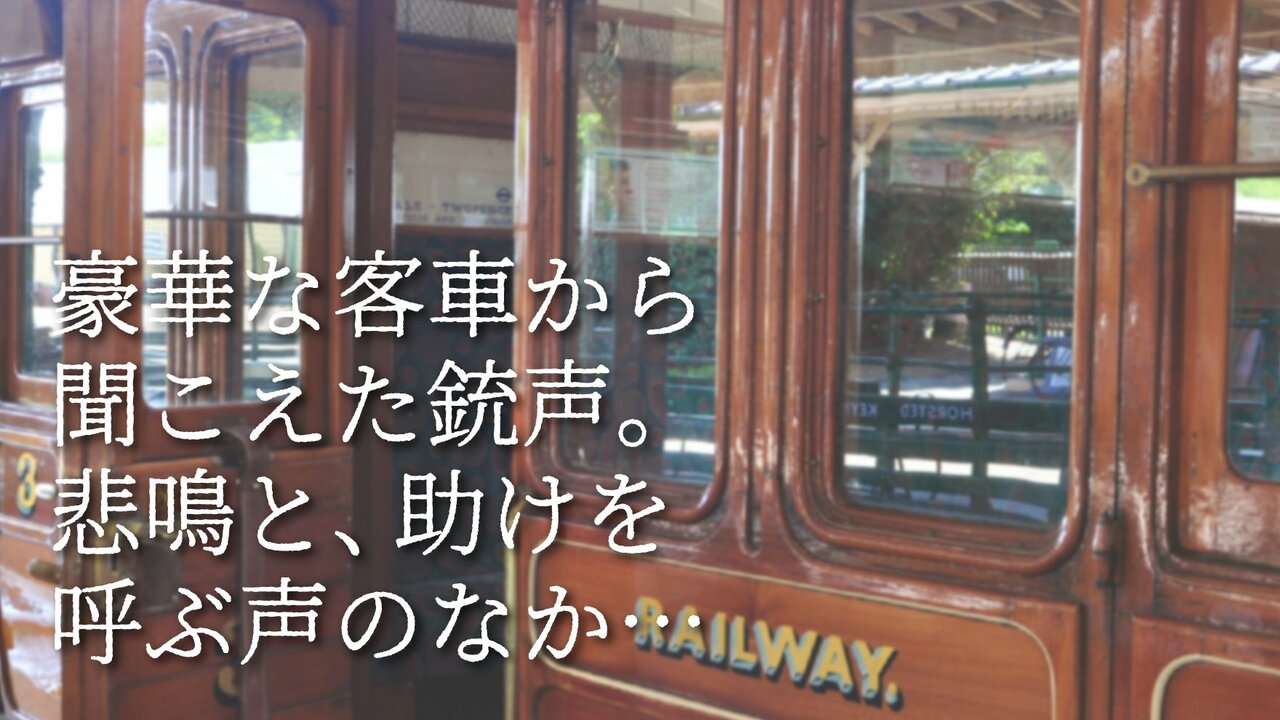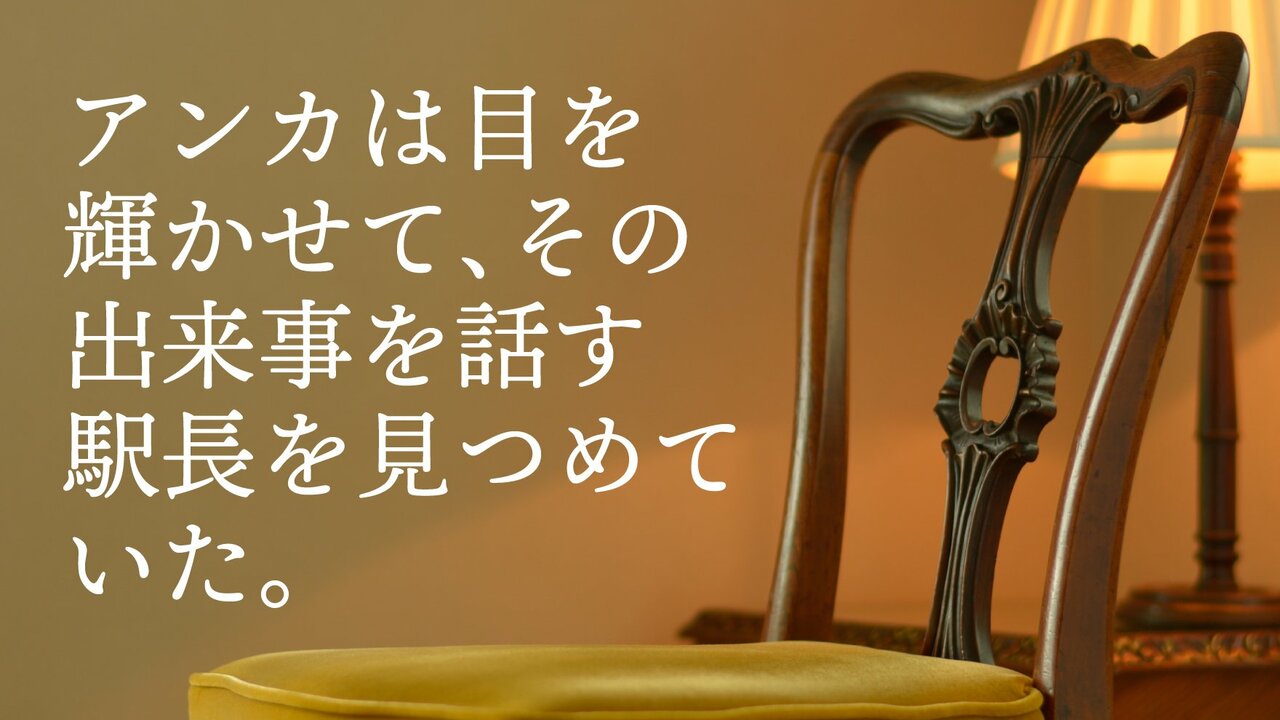彼の話しているセルビア語は十分にわかるものだったが、いささか堅苦しい雰囲気があった。もっとも、大帝の将校に相応しい話し方だった。
「ヴリシェルさん、全てを見事に準備されていますね。ただ、ひとつ質問させていただきたいのですが、私の……雇い主……はどうしてあなたに私の補佐役を依頼したのでしょうか?」
ヴリシェルは、どっしりとした木の椅子の背もたれに体を伸ばして、パイプに火をつけ、紫煙ごしにアンカを見る。
「ツキチお嬢様、この話は長過ぎてうんざりさせるかも知れません。ま、あなたに他にすることがなければ、話してもいいですけど」
アンカは微笑んで肩をすくめる。
「パジンを散策するには天気が悪い。暖炉で火が気持ちよくパチパチいっています。そして、まだ床につくには早すぎます。だから、その先を話してください」
ヴリシェルは、濃い眉毛の下からアンカを見つめ、そしてもう一度たばこの煙を吹き飛ばして、頷く。
「あなたがそうおっしゃるなら。一年半前のことになります。それは、私がパジン駅で、神聖なる皇帝、神の使途たるフランツ・ヨーゼフ陛下の実の孫娘を逮捕した時のことでした。
彼女の名前は、ヴァレリヤ・ヴィンディシュグラツ妃だった。皇帝の息子である亡きルドルフ皇太子の娘で、ヴィンディシュグラツ公の妃となった。ヴィンディシュグラツ公は、その時期、オーストリア・ハンガリー帝国軍の参謀本部長だった。その地位には、今、オスカー・フォン・ポチョーレクが就いている」
宿屋のウエイトレスが、「イストリア風のスープ」──スパイスの入った煮た赤ワイン──を陶器の壺に入れて持ってきたので、アンカは感謝の微笑みを返した。スライスしたトーストが《スープ》に特別な風味を加える。
アンカはそれからより心地よく座り直し、目を輝かせて人生でもっともスリリングな出来事を話している駅長を見つめていた。
「それでは続けますよ。皇太子フランツ・フェルディナンド大公は当時ブリユーニ諸島によく滞在され、そこで政府関係者から地元イストリアの役人に至るまで、様々な人々と政治会談をなさいました。皇太子の客人たちは、プーラ市まで列車で移動し、その後、船で島々に向かった。
ブリユーニ諸島では、フェルディナンドとの重大な政治会談の機会を利用して、幹部がいい気分で放蕩三昧しながら大公と懇意になれた。この時そこには、ヴィンディシュグラツも滞在していて、愛人であるチェコ人女優、エマ・シュヴァンドヴァにプラハから来るように声をかけていた」