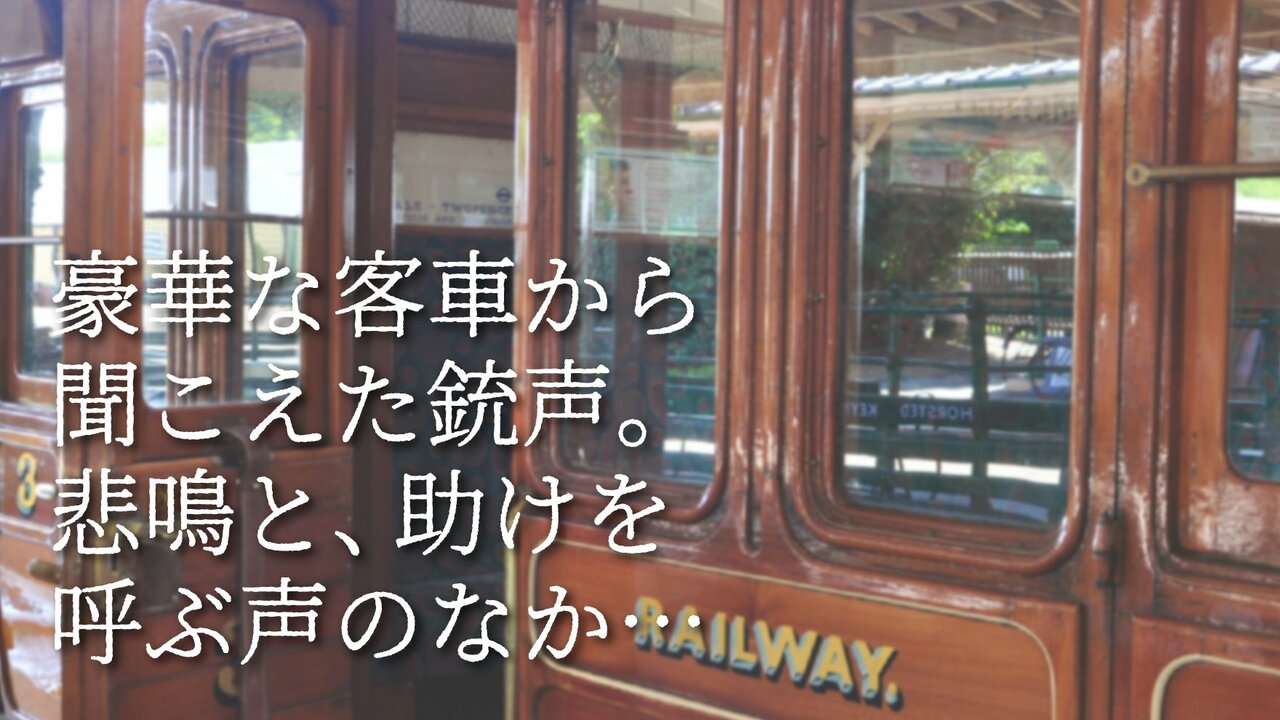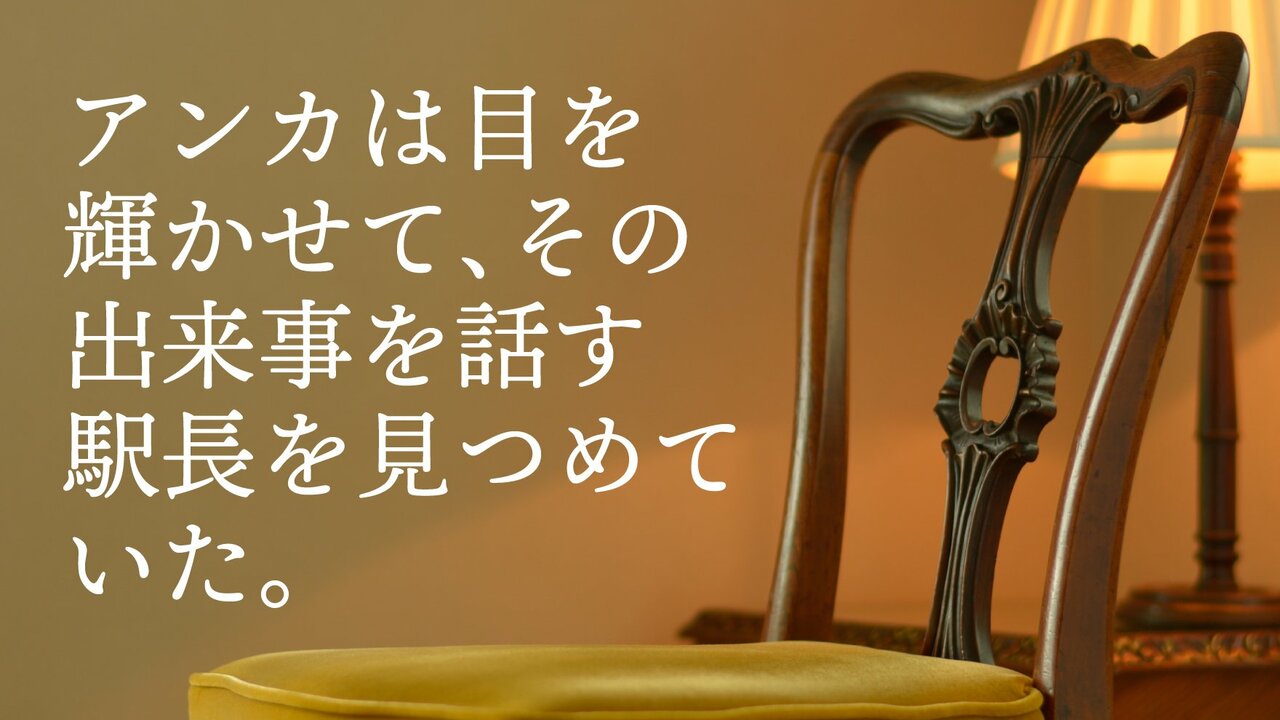「その通り、女性だ。だから何だと言うんだ」と、老警官が頷く。「残酷な運命のゲームに弄ばれ、シラミがはびこる寒い牢屋にたどり着いた女の子だ」
二人の力のみなぎった男達が女性はいないかのように、彼女のことを話していた。その女囚は、今、頭を垂れ、血の気のない裸足に履いた靴、紐のない擦り切れた汚い靴を見つめている。その秘密の会話は自分には全く関係ないといった様子であった。
「女の名前は、ミリツァだ」と、ミレンコヴィチが続けた。
「女の父親は、スメデレヴォ出身のポガチャレヴィチ何某だった。そいつと母親は、女がたった二歳の時に、ベオグラードにやって来た。ポガチャレヴィチは靴職人でバルカン通りに仕事場を持っていた。しかし、肺炎で五年前に死んだのじゃ。彼らの店は銀行からの借金のせいで破産した。ミリツァと母は、ピノサヴァから来た荷馬車の御者に引き取られるまで辺りをさまよっていた。その男はサマルジヤという名前で独身だった。ミリツァの母は、この男としばらくの間、内縁関係を結んでいたが、去年彼女もまた死んだ」
警官は、少しの間、黙ってディミトリイェヴィチの眼を見つめる。「撲殺されて、どぶの中で見つかったのだよ。もちろん警察は荷馬車の男に嫌疑をかけた。しかし、彼はバニツァ地区の何某の家で一晩中賭博をしたと、二人の男が証言している。ミリツァは、荷馬車の男との生活を続けた。他に頼るべき人間がいなかったからだ」
「どういう結末だったか想像できますよ」と、ディミトリイェヴィチ大尉が言う。
「うむ」と、ミレンコヴィチは溜息をついて答える。「このまえの月曜日の朝、少女が何か必要としているかを見に近所の女性たちがやって来て、荷馬車の男が無残な死体となり、その上にいるミリツァを見つけたんだ」
「無残な姿?」
大尉が小声で尋ねる。
「どんな風に?」
ターサ・ミレンコヴィチは肩をすくめる。
「彼の頭部は完全につぶれていた。わしは、少女がすり鉢の重いすりこぎで男をたたいて意識を失わせたと思う。それから、そのすりこぎで体じゅうをたたき続けたんだ。頭部の残りの様子から見て、彼女は一晩じゅうそれを実行したと判断できる。女性たちがこのおぞましい光景を見て悲鳴を上げた時でさえ、彼女らの証言によれば、ミリツァは、すりこぎを握っていた手を持ち上げ、砕けた骨、脳みそ、血と組織が混ざったどろどろ状のものをたたき続けていたのじゃ」
「少女を医者に見せましたか?」と、大尉が聞く。