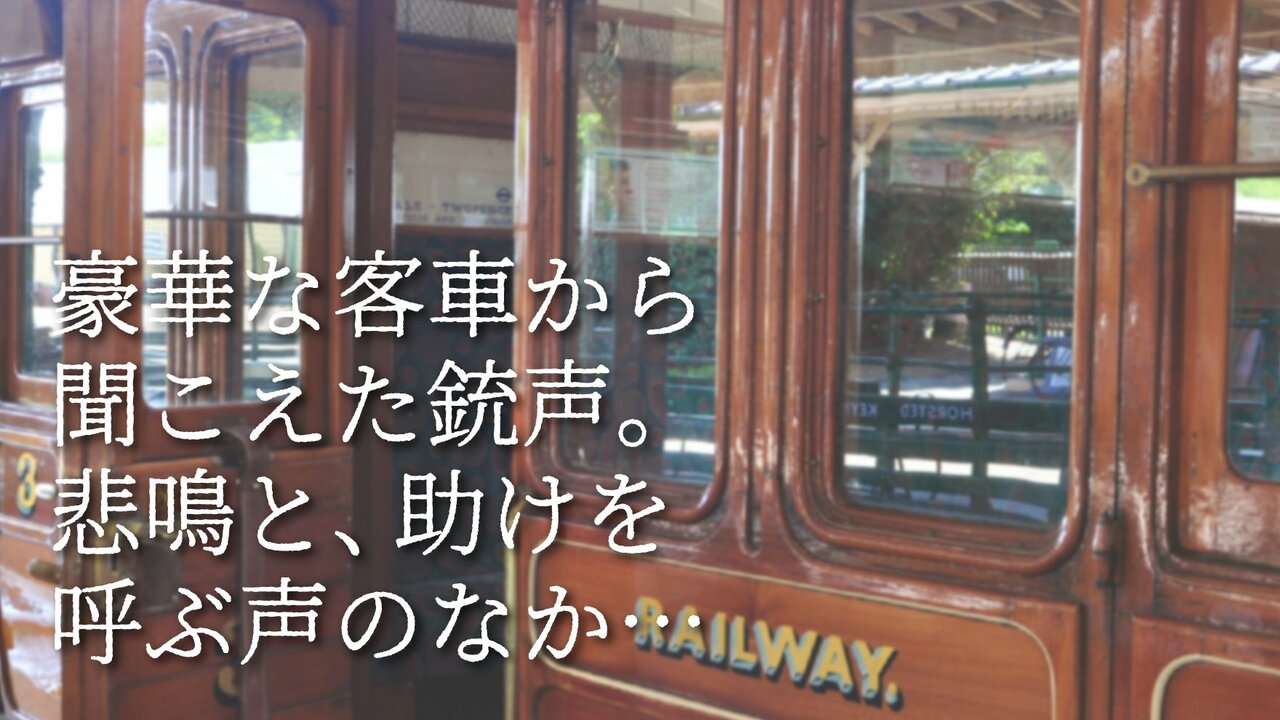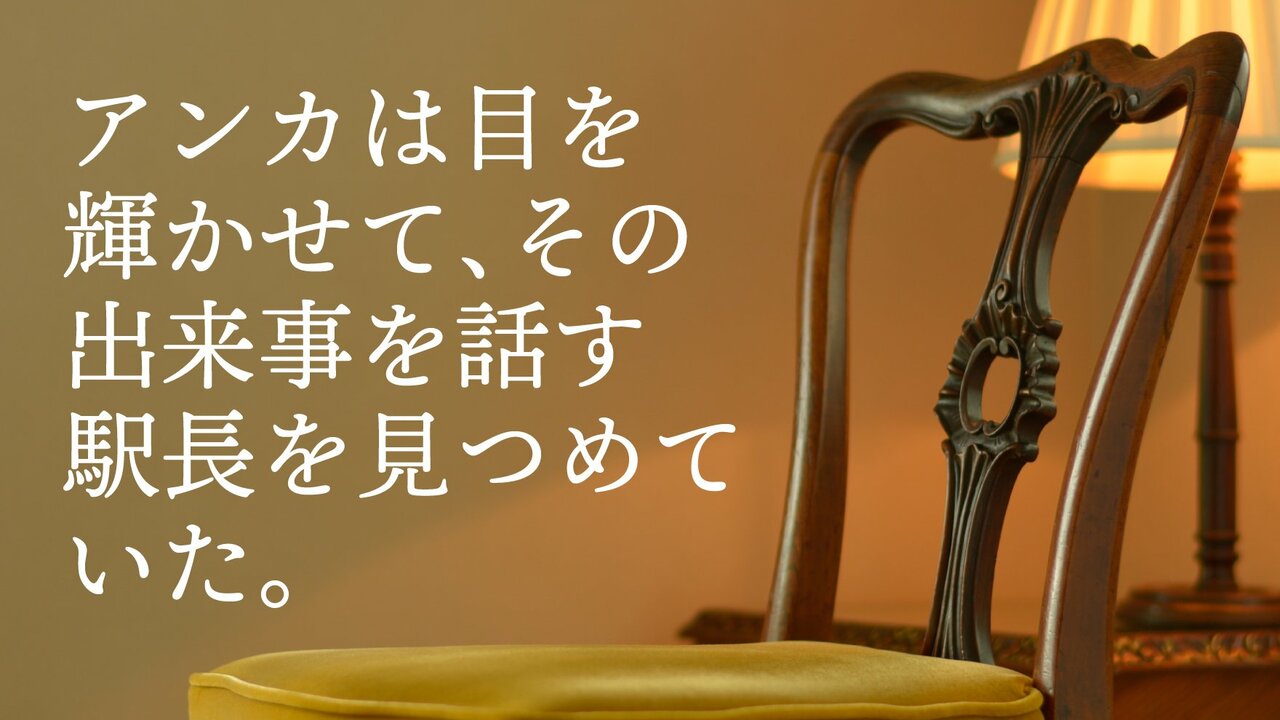第二章 手錠、運送屋、そしてアメリカの漫画 一九〇九年/一九一九年 ベオグラード
「スミィルコ!」大尉が鋭い声で叫ぶ。副官は直ちにミレンコヴィチのコートを預かって、上官の稀な訪問者用に待合室として使われる玄関ホールに持っていくために、ドアを閉めて退出した。
【注目記事】「発達障害かもしれない職場の人」との関係でうつ病になった話
ターサは暖炉の近くの肘付き椅子にゆったりと腰掛け、ディミトリイェヴィチが彼を興味深げに見つめている。ミレンコヴィチはまもなく六十歳になろうとしていた。まだタフで力がみなぎっている。
ただ、彼のきちんと櫛でとかしたグレーの頭髪や口ひげのところに、老年になろうとする気配が見てとれた。
「ターサ殿、いかがなさいましたか?」
スモモブランデーをボトルからグラスに注ぎながら、ディミトリイェヴィチが尋ねる。そのボトルは、スミリィコの親類が最近首都を訪問した際に持ってきたものだった。
「このような天気だと用がなければ外出しませんね」
ミレンコヴィチは濃い銀色の眉毛越しにディミトリイェヴィチをじっと見て、自分とディミトリイェヴィチのグラスをコンと音を鳴らし乾杯してから一口飲み、舌を鳴らす。
「ああ、何て素晴らしい味だ! 一体、どこのブランデーだ?」
「ムラデノヴァツ産で、我が副官のです」
「スモモのブランデーの作り方なら、あの地域では良く知っているんだよ」
と、警察の長が言う。彼は頷いて、グラスの残りをのどに注ぎ込む。ちょっとせき込み、もっと注いでもらうようにディミトリイェヴィチの方にグラスを差し込む。ディミトリイェヴィチは微笑み、自分のグラスを飲み干し、それから再び二人のグラスを満たす。
「それで、ターサさん、最近は何かニュースになることはありますか? 首都での暮らしのダークサイドについての、新しいわくわくするような小説を期待できますか? 『真夜中』の続きみたいな……」
「大尉殿」とミレンコヴィチが少々切れた口調で言う。
「わしは、つつましくやっている文学のあれこれについて貴殿と話すために来たのではないぞ。去年、内務大臣主催のレセプションで話した例のことで来ているんだ」
ディミトリイェヴィチは眉をひそめる。もちろん、そのレセプションのことは覚えている。しかし、その時は多くの役人たちと会話した。それら大勢の中にターサもいた。警察の長と話した事と言えば……
「はい、それについてです」
と、ターサは言う。ディミトリイェヴィチの眼の輝きから、彼がそのことを思い出したことに気付く。
「話は、きみの願いについてだよ。王国の対敵諜報機関を近代化して、その効率を高めるという願いだよ」
ディミトリイェヴィチは、飲んでいる途中のグラスを持ちながら、背もたれに寄り掛かった。
「そうです。私の記憶が確かならば、私は全ての業務が改善でき、また当局から承認を受けられそうな改革のいくつかについて、様々な方法をあなたに申し上げました。