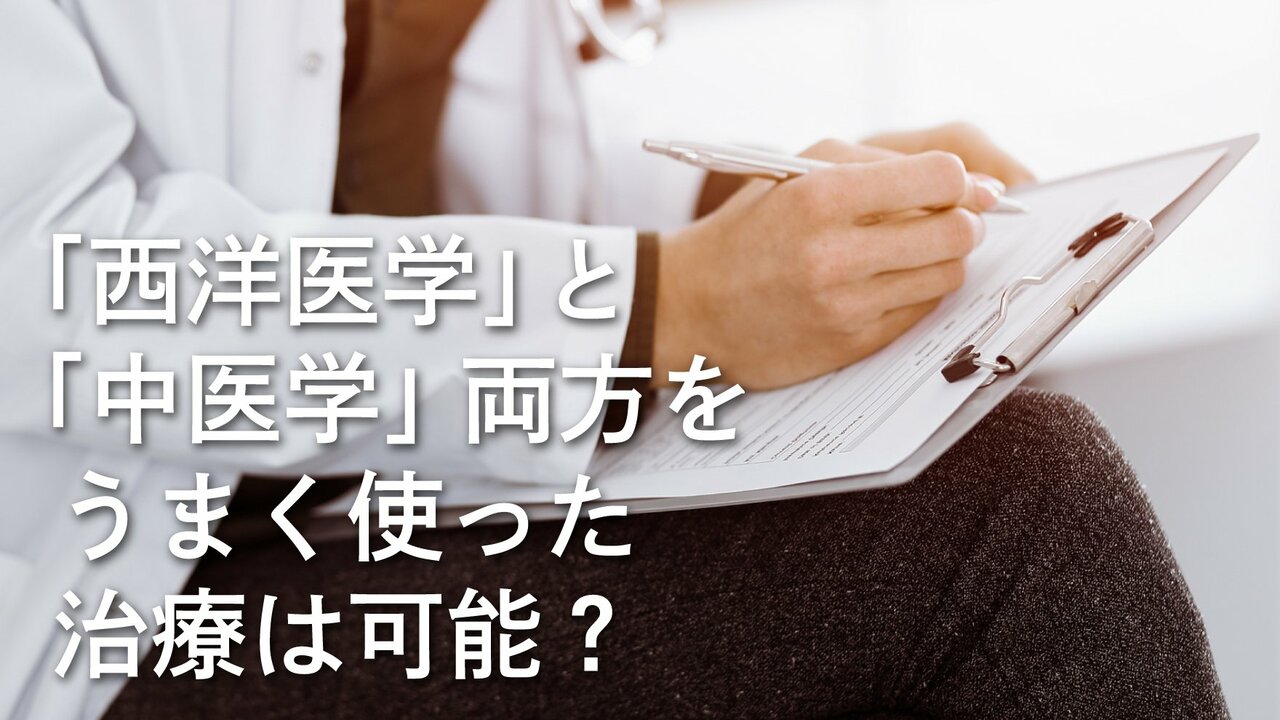上半身はまだそこそこ筋力がありそうだけど、肉が付いたのは……やっぱ腹か。まだそう見えないだけましな気がする。
「なんか一人振り回されてるみたいね」
そう、新入生の中でも、お前は打てるからと、人より走らされているのは事実だ。
「期待されてる証拠じゃない?」
また心にもないことを言って、ケラケラ笑っている。しかし何事もないようにケロッとしている春田に比べるといくらなんでもだらしない。
テニスサークルに入って一カ月。ようやく先輩にも、同級生にも(すでに辞めた人も多いが)、システムにも慣れてきた。おまけにこうして、何もなければまともに目を合わせられない春田とも、わずかな緊張だけで話せるようになった。
もともと何かにつけて真面目な春田は熱心で休むことはない。彼女が来るから、当たり前に休みなく来ている僕とは、同じ学部学科ということもあるのか、ここで話をする機会は多かった。
それも、最初は挨拶程度の会話だったけど、今ではその内容も豊富になってきていた。意外なことに主に春田がしゃべってくれるので、僕はそれに相槌と突っ込みを入れればよかった。
もちろんその方が楽だったし、彼女も楽しんでいるようだった。そんな姿も見られる水曜と金曜のこのベンチでの休憩時間が、次第に待ち遠しくなってきていた。
おまけに最近は僕をからかってくることもある。そんなのも新鮮で、僕にはそんなくせがあるのかと思わなくもないのだけれど、やはり嫌ではないのだ。
「あれ、沢波くん、え? テニス?」
テニスコートに張り巡らされているネットの外から不意に聞こえた声に、僕も春田も同時に振り返った。
「あら、木下さん」
そういえばこのコートは経済学部のすぐそばにある。ネットサイドの通路はその学生の通り道になっているのだ。
木下和はネイビーのチノパンにパーカーを羽織って、リュックを背に金網によりかかっていた。
※本記事は、2020年11月刊行の書籍『桜舞う春に、きみと歩く』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。
★邪気指数、新陳代謝指数、正気指数
漢方の立場で見た、主人公沢波俊樹の体調を示します。本来、漢方にはこんな指数はありませんが、これに近いことをもっと細かく考えながら対処します。これらの変化は人によって異なります。
●邪気指数
体の中に溜まった不要なもの(邪気)の量を示す指数です。邪気は誰の体の中にもあります。食事の質や偏り、嗜好品、食べる時間などで変化しやすく、新陳代謝指数が下がり排出が悪くなることでも上昇します。邪気がかゆみの元にもなることがあります。ここでは50~150を正常範囲とします。150を超えると体調を崩しやすくなります。ただし、正気指数が高い方は、邪気指数が高くなっても体調を維持することができます。
●新陳代謝指数
体の中の、良い物(正気)、悪い物(邪気)がどれだけスムーズに動いているかを示す指数です。通常人が生きていく中で、良い物(新)を取り入れて、いらないもの(陳)を排出しています。それがスムーズに動いていること(代謝)が大切です。飲食の消化吸収、大小便での排出、血流、発汗などトータルの指数とします。運動不足やストレスなどで低下します。ここでは70~100を正常範囲とします。新陳代謝指数が下がると邪気指数が上がりやすくなり、下がっているときには正気指数も下がっていることが多くなります。
●正気指
数
体の元気(エネルギー≒正気)の指数です。バランスの良い飲食で満たされ、ほど良い休息をとることで作られます。逆にストレスや過労で低下します。正気が少なくなると、体のだるさや意欲の低下がみられ、免疫をコントロールする力が弱り、かゆみを抑えられなくなり、症状が悪化します。ここでは70~100を正常範囲とします。正気指数が高いと新陳代謝指数は上がりやすく、邪気指数が少々高くても生活に支障はありません。