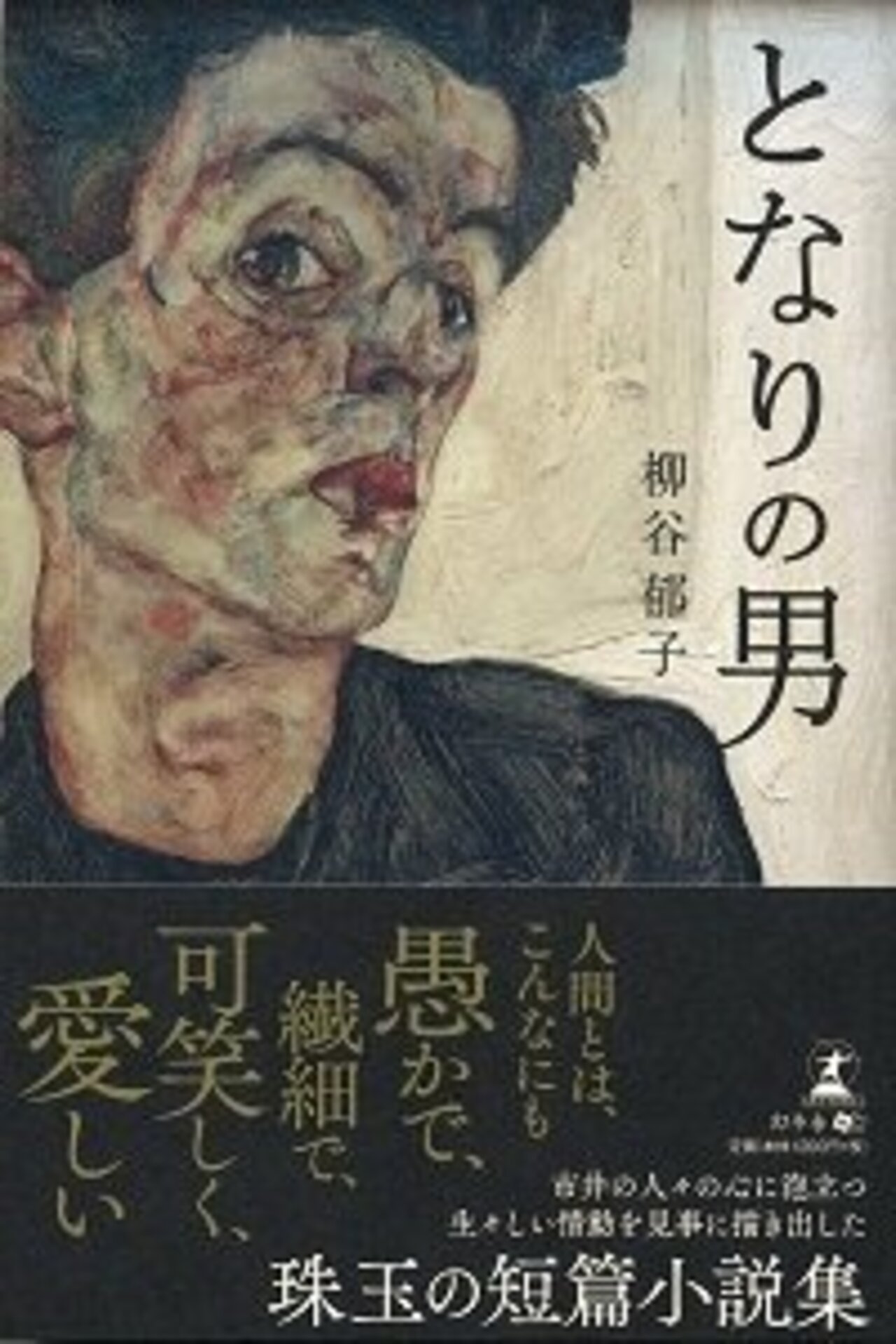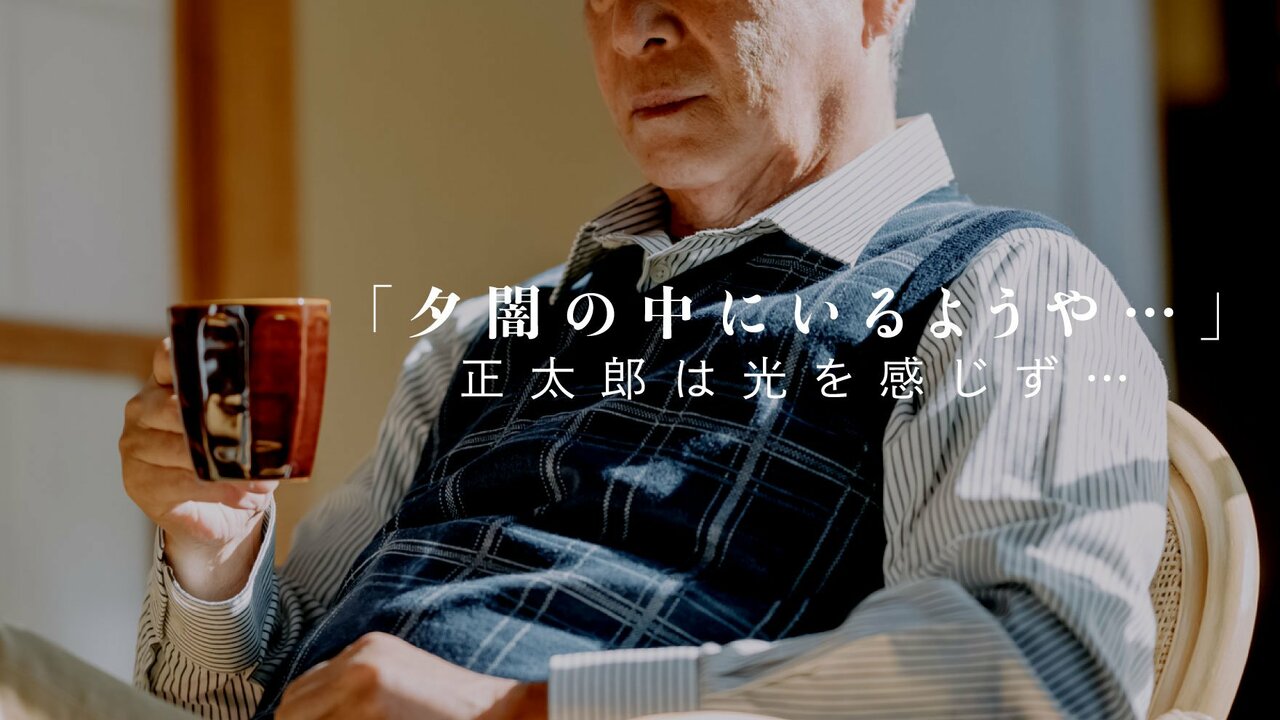――ところで、新超現実派展でオブジェの課題が出た。曰く「殺人は可能か」。作品とともに同封の原稿を添えて出展しました。現物です。貴女はいつか必ずユタに現れる。そして僕を殺す。待っている僕を、君は嘲笑うか――。
《これが昔、僕が死ぬほど好きだった、或る浮気女の乾首なのです。名は由布。僕が殺した。そう、僕がこの手で殺したんです。もし彼女がその辺りを歩いているとしたら、それは彼女の亡霊に違いありません。いや、きっと、人違いです。だって、僕が、この手で由布を殺したんですから。――未完の告白より》
作品の世界とも現実ともつかぬ彼の手紙に添えられた原稿の詞句を、あなたは忽(たちま)ち空んじた。そしてやはりそのまま放置した。やがて新聞のコラム「美術展望」に伊藤一仙率いる一派が紹介解説されているのをあなたは見る。
《超現実主義の運動がすでに終息してしまったと早まった断定を下してはいけない。人類が理想郷に到達せぬ限りは超現実主義の主張は常に正しく、その運動は永遠に続けられなければならないのだ。
―という勇ましい宣言文が現れた。新・超現実派十一人の侍たちの結成宣言である。前衛芸術の主流を抽象絵画に奪われて久しい。その巻き返しを目指すものとして注目されるが、日本におけるシュールレアリズム退潮の原因がどこにあったか、まずその分析から始めなければ、単なる亡霊の跋ばっこ扈に終わってしまうだろう》
あなたはコラムを切り抜き、しばらく見入ったのち、日記帳のその日の欄に貼り付けた。虚しい闘いにまみれる野望と悲哀に彼らが本気で挑んでいるらしいことだけは分かった。
すると、田島の発する禍々しく曲がりくねった華麗に過ぎる言葉の羅列にも、少なくとも彼の血の一滴はこもっているのだ。けれどもそうであればあるほど、あなたと田島の間には渡ってはならない橋があるようである。
田島から果たし状にも似た勇み立った手紙を受け取ったのは、その年も終わりに近い、ちらちらと小雪の舞う日であった。