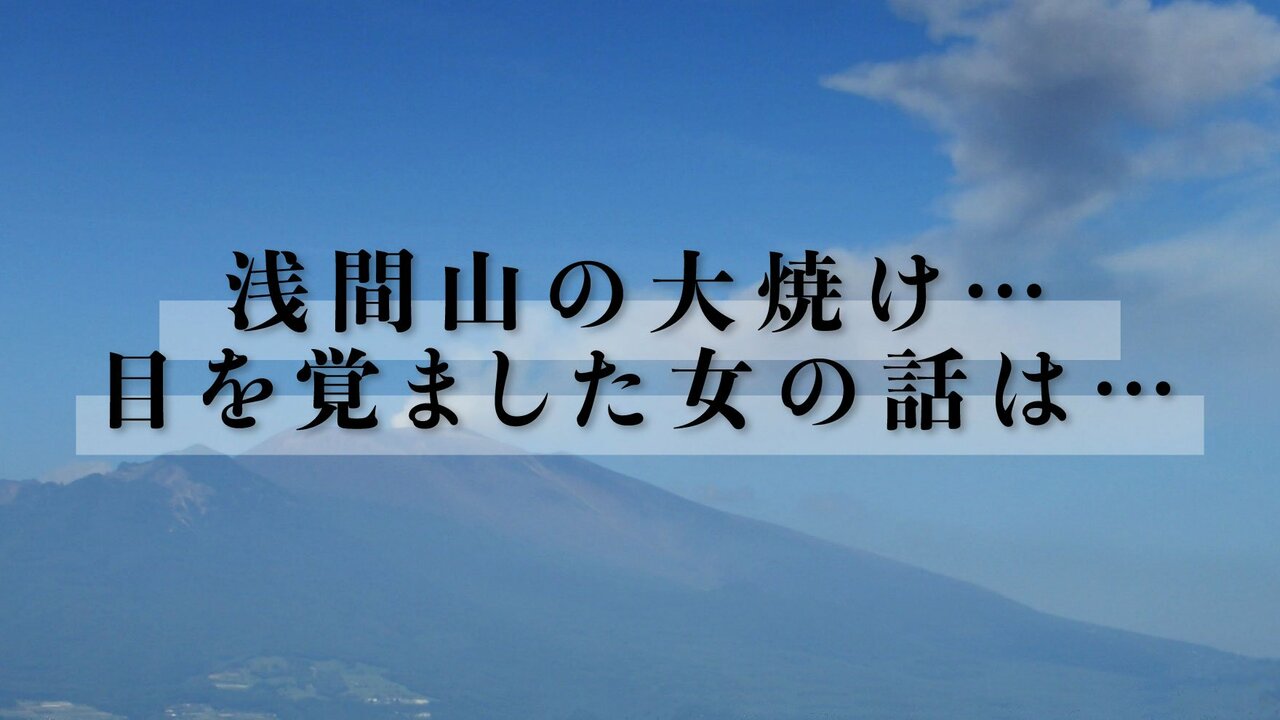伊助が部屋にやってきて、かしこまりながら頭を下げた。結衣は改まったように顔を向けた。
「伊助、私は今日、おまえや吾作、そして若い夫婦と話をして、自分がいかに我儘で傲慢で、世間の厄介者だかよくわかったわ。少し世間というものが見えてきたような気がする。お父様や私の元には多くの百姓衆や小作、杣人がいて、みんなに支えられていることがわかってきたわ。このままではいけない。私も何か人様の役に立つことをしなければ、人様に喜ばれることをしなければと……、今はそう思う。伊助、私はどうしたらいいの?私に何かできることがあれば教えて!」
伊助は結衣の心変わりに驚いたようだったが、しばらく考え込むとおもむろに言った。
「お嬢さんは、いずれ婿を迎えて名主の女房としてこの村を取り仕切っていく身だから、百姓や杣人を大事にしてやることだ。百姓は国の宝だからな。百姓に信頼されて好かれるような人になればいいと思うがな」
「わかったわ。そうなるよう心掛ける。でも、すぐにでも百姓衆のために何か……私にできることはないかしら?」
伊助が微笑みながら、
「お嬢さん、今日の小作の若夫婦、なんであんなに明るいかわかるかい? 貧しくて家や食い物、着る物も粗末だが、土間や板の間を見たかい? きれいに掃き清められて磨かれてただろ。雨漏りするようなぼろ家だが、家を磨くことによって自分の心も磨いているんだよ」
結衣は夫婦の家の様子は思い出したが、伊助の言っている意味は理解できなかった。
「きれいになれば気持ちもいいし、やればやっただけ、きれいになるってわかってるんだ。だから頑張れば米だってたくさんとれるようになるんだって希望を持ってるんだ。そしていつか暮らしが良くなるって……だから明るいんだ」
結衣は、伊助の見ている世界と自分に見える世界がまるで違うと思った。
「もし、お嬢さんが今何かやりたいなら、そうだなあ……女子衆がいつも手にしている雑巾を縫ったらいい。今までにない丈夫な雑巾を作ったらいい。そして村の女子衆にやったらいい。喜ぶと思うがな。雑巾は足拭きから床拭き、塵取り、水拭きと何でもこなすから丈夫な物がいいんだが、どうしても布だからすぐだめになる。拭き掃除で棘を刺したり、手に怪我をすることも多い。もっと厚くて丈夫な物、それにきれいに刺し子された雑巾があったらいいと思うがな」
結衣は伊助の気配りの鋭さに驚かされた。同時に自分の存在価値を確かめるために、一つの光明を見出した思いがした。