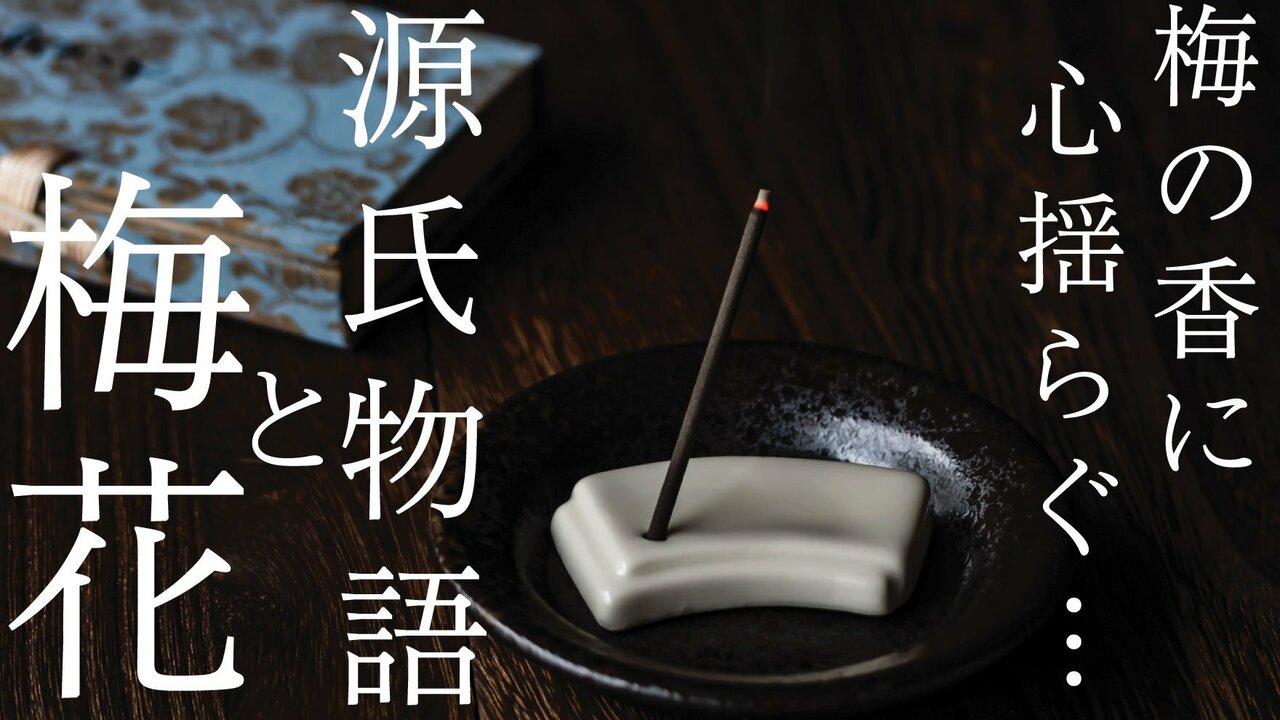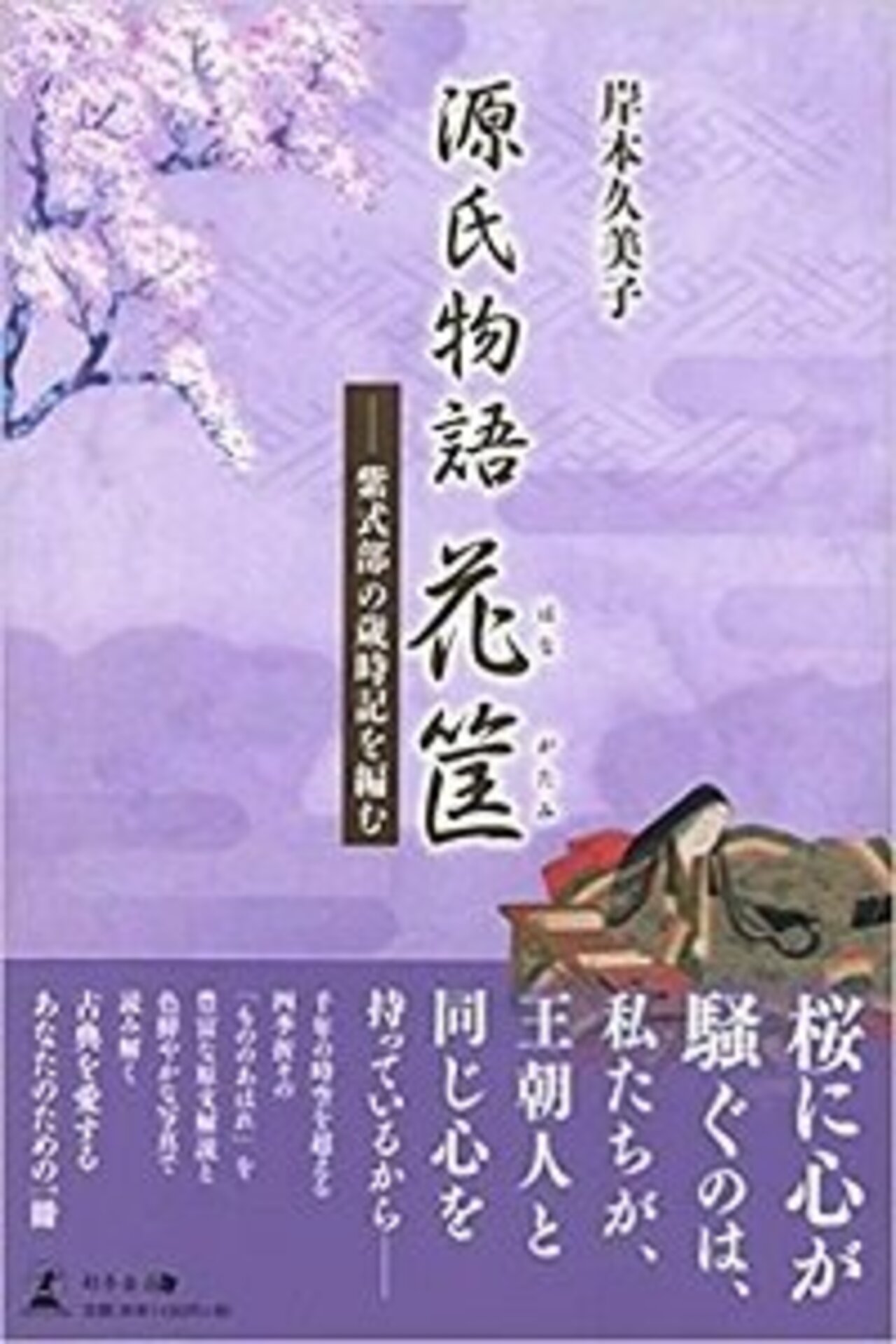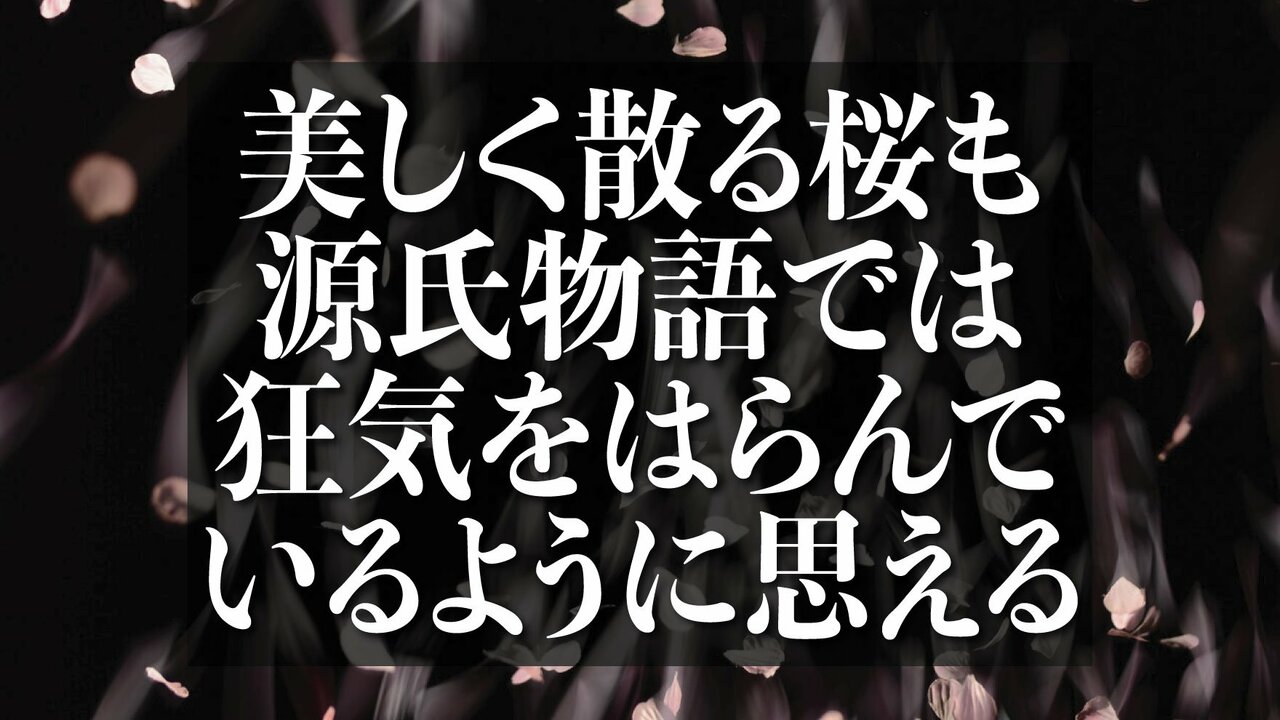春:2 梅の香
源氏物語に登場する花で、圧倒的に多く登場するのが、桜・藤・梅です。
宇治十帖に入ると、薫の纏う香りが梅によそえられたり、対抗する匂宮が梅を愛してその香りを身に漂わせていたことなどが書かれ、梅の登場率は高くなります。


「紅梅」の巻では、按察使大納言が、娘の婿にと願う匂宮に、紅梅を送る話があります。その紅梅の枝を受け取った匂宮は、
「園ににほへる紅の、色に取られて、香なむ、白き梅には劣れるといふめるを、いとかしこく、とり並べても咲きけるかな」
とその枝が薫り高いことを愛でていますが、その宮自身が
「花もはづかしく思ひぬべくかうばしくて」
とあり、梅の花以上に薫香を焚きしめていたことがわかります。
その匂宮と薫との関係に悩んで入水自殺を図って、意識を失って倒れていた浮舟は、尼君たちに助けられ、小野の里に暮らします。夏のことでした。
そして迎えた秋のある日、浮舟は尼君の留守に、出家を断行してしまいます。出家してから後は、少し明るくなって碁を打ったりもしたとありますが、春が巡り来る頃、彼女の心は過去を思い少し揺れています。
年も返りぬ。春のしるしも見えず、氷りわたれる水の音せぬさへ心細くて、「君にぞまどふ」とのたまひし人(匂宮)は、心憂しと思ひ果てにたれど、なほそのをりなどのことは忘れず。
かきくらす野山の雪をながめてもふりにしことぞ今日も悲しき(手習の巻)
匂宮を信じ切ることはできず、離れようと思ったけれど、あの匂宮と宇治の小家で過ごした時間、あの甘い言葉と情熱は、忘れられない……。その時と同じ雪・氷を見て過去を思って悲しんでいます。
そして、やがて梅が咲けば、梅の香にまたその人を思い出し、懐かしまずにはいられません。人の記憶は視覚よりも嗅覚によって蘇るとどこかで聞いたことがあります。
閨のつま近き紅梅の色も香も変わらぬを「春や昔の」と、異花よりもこれに心寄せのあるは、飽かざりし匂ひのしみけるにや。後夜の閼伽たてまつらせたまふ。下臈の尼のすこし若きがある、召し出でて花を折らすれば、かことがましく散るに、いとど匂ひ来れば、
袖ふれし人こそ見えね花の香のそれかとにほふ春のあけぼの(手習の巻)

「袖ふれし人」は薫、匂宮の両説あるのですが、私は匂宮だと思っています。