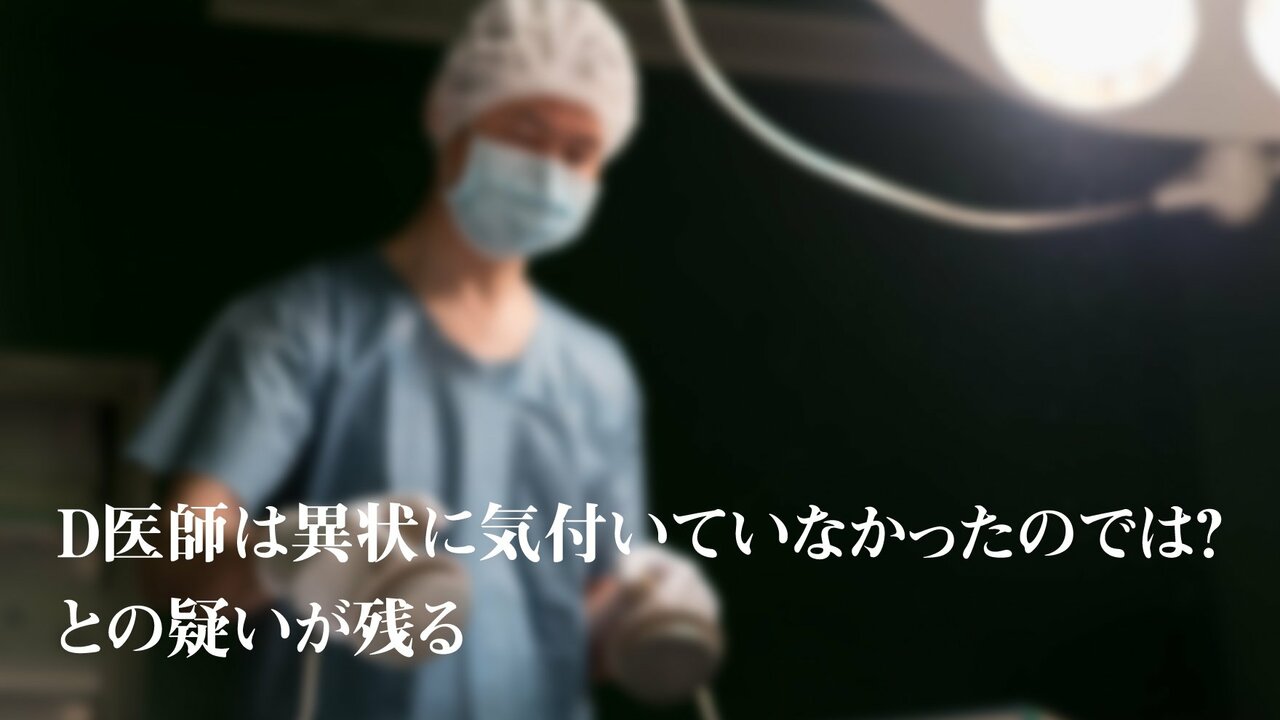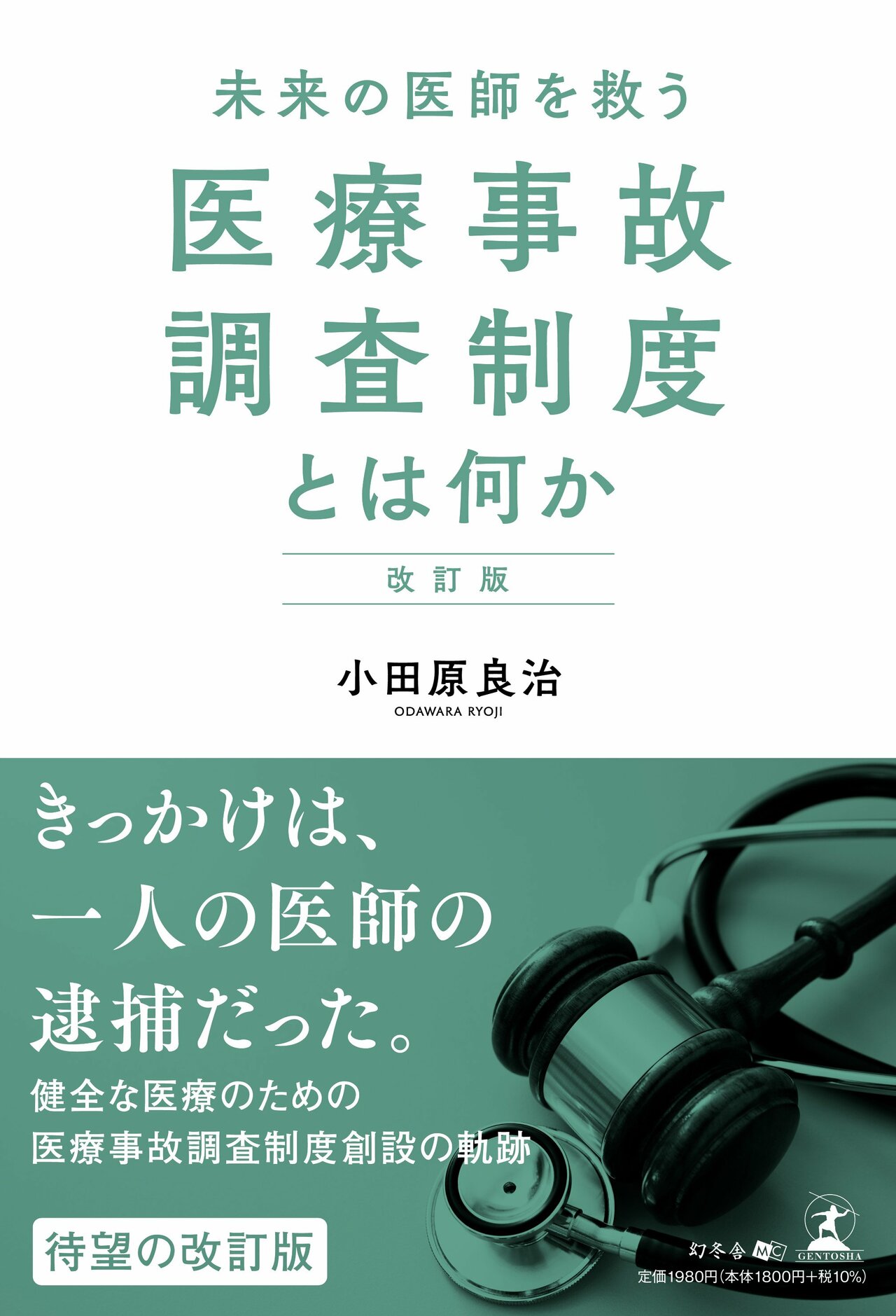東京都立広尾病院事件東京高裁判決と医師法第21条
原判決は、上記【1】で認定したところと同様の事実を前提に、D医師は、Aの主治医であり、Aは術前検査では心電図などにも特に異常は認められず、手術は無事に終了し、術後の経過は良好であって、主治医としてAについて病状が急変するような疾患等の心当たりが全くなかったので、E医師から、看護師がヘパロックした直後、Aの容態が急変した状況の説明を受けるとともに、看護師がヘパロックをする際にヘパ生と消毒液のヒビグルを間違えて注入したかもしれないと言っている旨聞かされて…
【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
薬物を間違えて注入したことによりAの病状が急変したのではないかとも思うとともに、心臓マッサージ中に、Aの右腕には色素沈着のような状態があることに気付いており、そして、Aの死亡を確認し、死亡原因が不明であると判断していることが認められるのであるから、D医師がAの死亡を確認した際、その死体を検案して異状があるものとして認識していたものと認めるのが相当である、としている。
また、原判決は、AはD医師が主治医として診療してきた入院患者であり、D医師は、Aの容態が急変して死亡し、その死亡について誤薬投与の可能性があり、診療中の傷病等とは別の原因で死亡した疑いがあった状況のもとで、それまでの診療経過により把握していた情報、急変の経過についてE医師から説明を受けた内容、自身が蘇生措置の際などに目にしたAの右腕の色素沈着などの事情を知った上で、心筋梗塞や薬物死の可能性も考え、死亡原因は不明であるとの判断をして、遺族に病理解剖の申出をしているのであるから、Aの死体検案をしたものというべきであるとする。