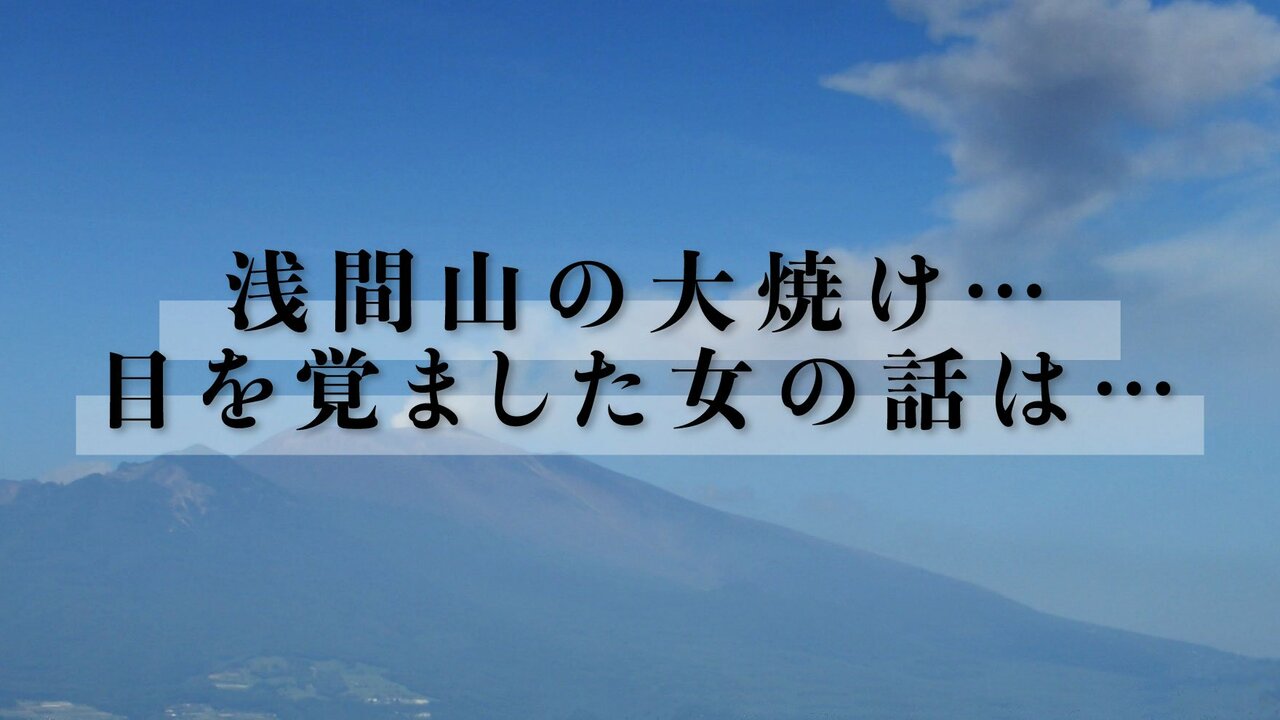いよいよ落胆した平吉夫婦に、このときまだ四歳になる三男の伊助が、
「おとうも、おかあも、おいらがいるじゃねえか!」
の一言で、前を向かなければと気づき、なんとか立ち直ることができた。
しかし、このとき伊助は、すでに他家へ養子に出すという約束がなされており、自分たちの子であって人様の子でもあった。
当時、農村では、子どもは働き手としてどの家も子だくさんが当たり前であった。裕福な百姓であれば長男が世襲で跡継ぎとなると、次男や三男は田畑を分与して新家として独立させるが、持ち田や財産が少ない百姓の次男以下は良い養子口を探すか、入り婿するか、あるいは職人などになって生計を立てるしか生きていく術はなかった。
平吉一家はわずか三反の畑を耕作する百姓であり、将来、三男の伊助を新家として分家独立させることは不可能だった。そこで平吉は伊助の行く末を考え、まだ幼子のときに養子の口を斡旋してもらっていたのである。
すでに藤左衛門の口利きで縁組が取り決められていた。養子先は武州日野川辺(かわべ)村の名主、九右衛門(きゅうえもん)家である。
九右衛門と平吉との約定では、伊助が七歳になったら正式に養子縁組をすることとし、それまでの養育料及び支度金として十五両が支払われていた。
しかし、長男、次男ともに亡くなった今、平吉の跡継ぎは伊助しかおらず、養子縁組を破談にしてもらうしかなく、藤左衛門を仲立ちにして話し合った。
その結果、養育料及び支度金十五両と違約金五両の、合わせて二十両の返済と藤左衛門、組頭、平吉の連名の詫び状を九右衛門に入れることで決着がついた。
平吉は借金に奔走したが結局、二十両を返済することができなかった。洪水で度々野菜が全滅し、年貢代や生活の賄い、雑木林の返済金などに使ってしまい手元に金が残ってなかったのである。