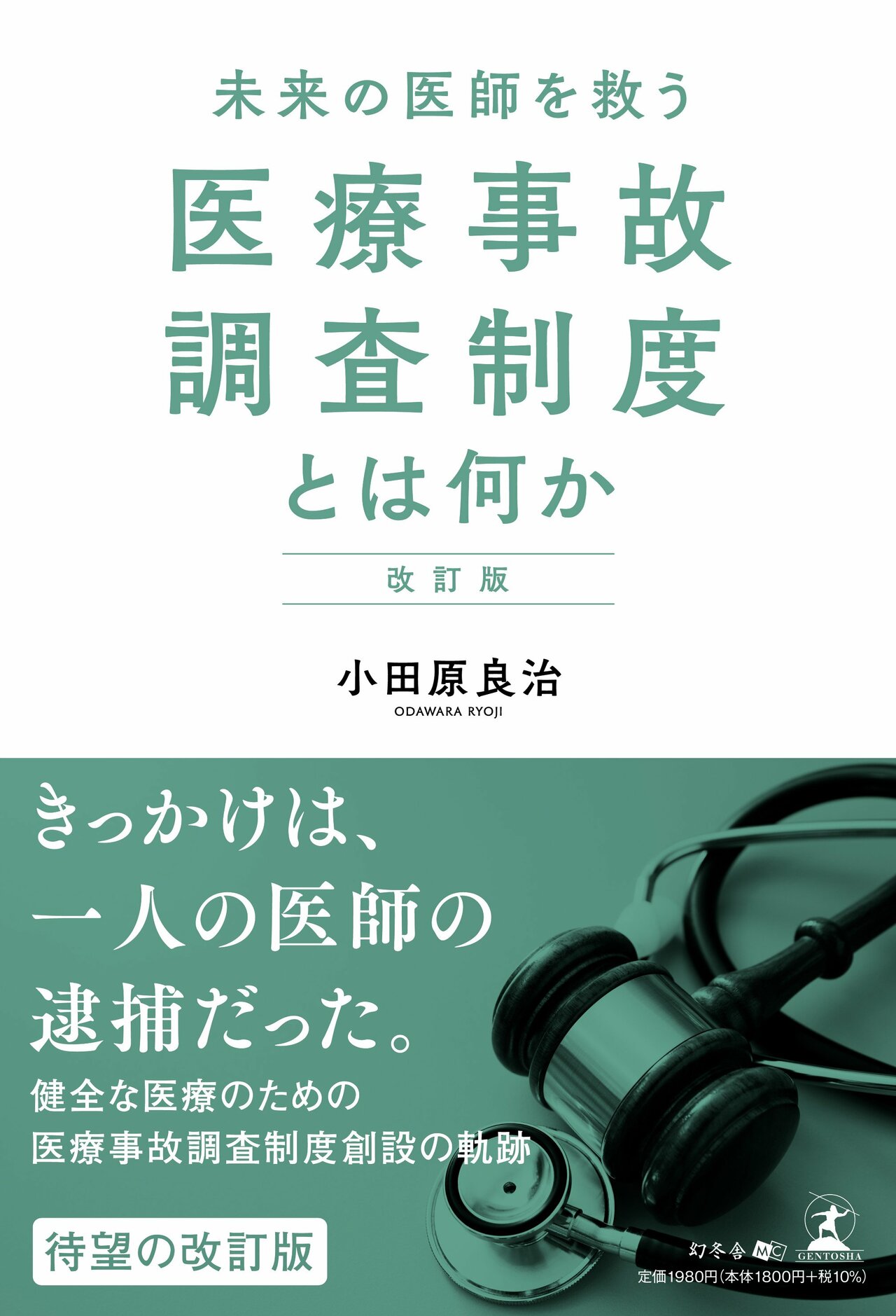(2)東京都立広尾病院事件判決の歴史的意味
東京都立広尾病院事件については別項で詳述するが、異状死体等の届出義務の歴史的流れの一コマとして、ここで概略とその意味を考察したい。本事件は、看護師がヘパリン生食液と消毒液を取り違えて注入し、患者が死亡した事件である。
被告人は同病院の院長であるが、担当医と共謀して医師法第21条の警察への届出義務を怠ったとして起訴された。被告人(院長)は無罪を主張し、事実関係と法令適用を争ったが、第一審、第二審ともに有罪とされ、上告したものである。
上告趣意は、
(1)医師法第21条にいう死体の『検案』とは、医師が死後初めて当該死体に接して、その死体を検分することを言い、生前患者であったものについて死後検分することは、医師法第21条にいう『検案』に該当しない。(これは、旧医師法施行規則第9条当時から、ずっと医療現場で常識とされて来た見解である)
(2)仮に、生前に患者であった者に対して行う死後の検分が『検案』に該当するとしても、担当医は業務上過失致死等の刑事責任を問われるおそれがあり、届出を義務付ける医師法第21条の規定は憲法第38条1項で保障する自己負罪拒否特権に反するとした。
しかし、最高裁は、上告棄却するとともに、職権で判示を行った。この最高裁判決には憲法違反である等の批判があった。判例時報1861号によれば、一般に、『検案』とは、「医師が死者の外表検査により死因や死因の種類を判定する業務」とされ、(1)診療中の患者であった者は含まれないとする消極説、(2)原則的には含まれないが、診療中の患者でも、交通事故など、別個の原因による死亡の場合は含まれるとする原則消極説、(3)診療中の患者も含まれるとする積極説があるとされているが、積極説は東京都立広尾病院事件第一審判決後に現れた見解であり、このような見解はそれまで皆無であったとしている。
この積極説の論拠に二〇〇〇年(平成十二年)八月に出された、厚労省「リスクマネージメントマニュアル作成指針」が挙げられている。この経緯をみても厚労省の安易な対応が医療現場に混乱を与えた元凶と言えよう。
同指針について、二〇一二年(平成二十四年)十月二十六日の第8回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会で、田原克志医事課長は同通知は国立病院等のみを対象とした通知であり、他の医療機関を対象としたものではない旨明言した。
また、同通知は、国立病院等の独法化に伴い失効した旨、二〇一五年(平成二十七年)七月三日、厚労省医政局医療経営支援課が回答している。
厚労省は従前より一貫して、医師法第21条は医療事故等々を想定した規定ではない旨の立場をとって来た。ところが、安易に出されたリスクマネージメントマニュアル作成指針が拡大解釈され、医療現場の混乱をもたらしたため、厚労省は、田原課長発言で、軌道修正を図ったものであろう。
消極説は従来からの見解であり、「死体検案書」は診療中の患者以外の者が死亡した場合に作成されるものであるとされて来た。大正七年大審院判決も東京地裁八王子支部判決もこのような見解に立ったものと思われる。
原則消極説の根拠も「死体検案書」と「死亡診断書」の使い分けを根拠にしており、昭和二十四年厚生省通知(昭和二十四年四月十四日医発第385号、次項に記載)を根拠としていると考えられている。
「異状」については、法医学的異状とされており、これは、犯罪が疑われる死体という意味であり、旧医師法施行規則第9条から一貫した厚労省見解と言えよう。判決文そのものについては別項で記述したい。