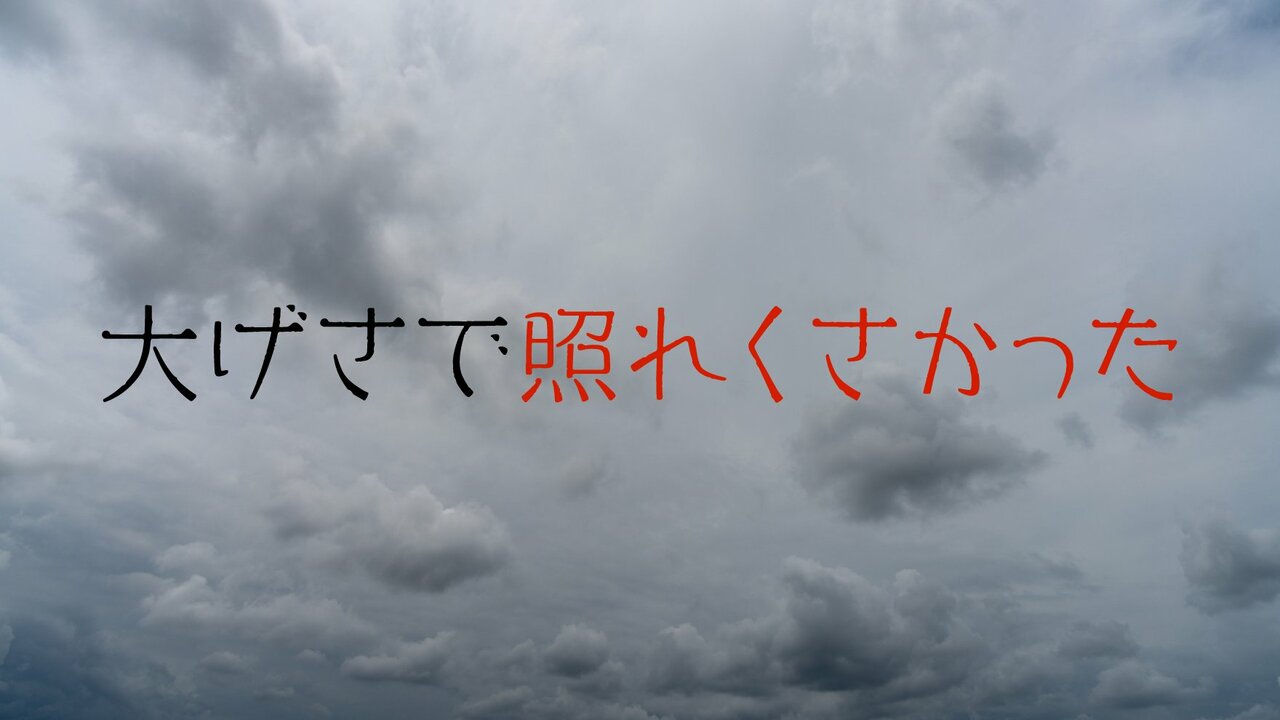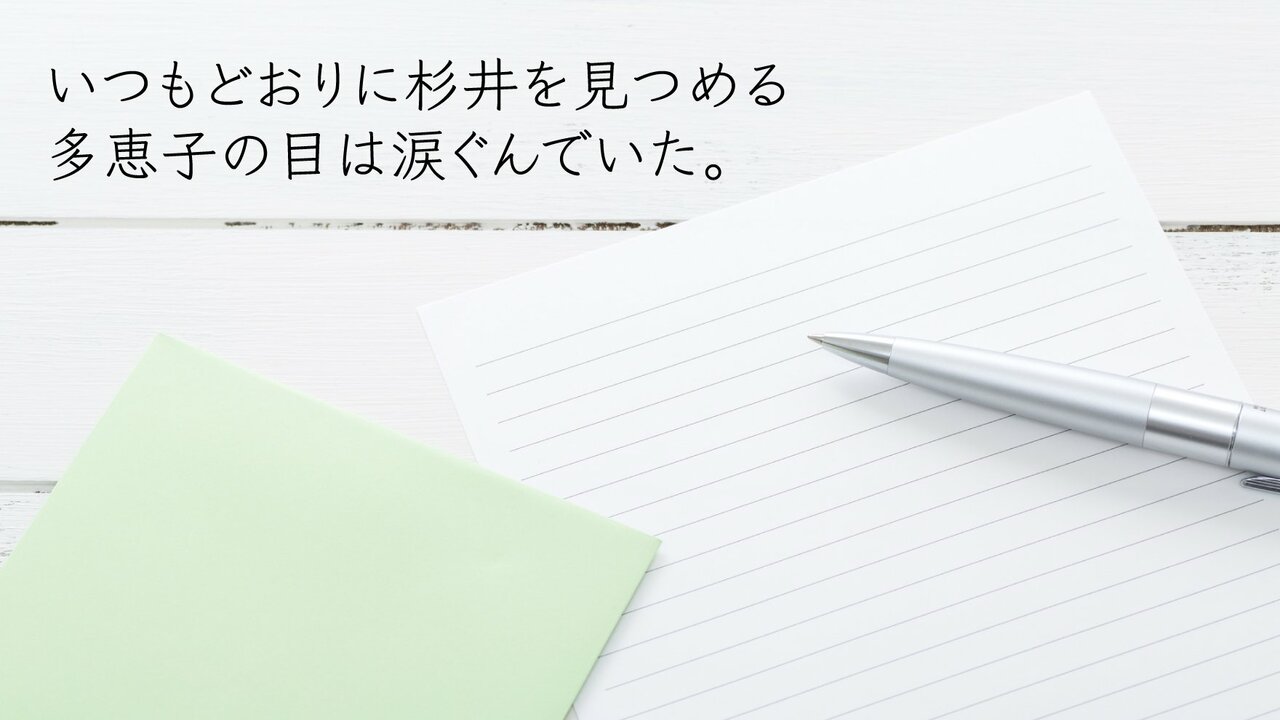第一章 新兵
壮行
杉井は、家業を離れても手掛けた仕事がうまくいくよう、自分が開拓した関東一円の取引先に従業員の下川を伴って回るなど着々と準備を進めた。
真面目に仕事は続けてきたものの、自分に合っていると思って就いた職業ではなかったため、間もなくこの仕事ともしばらく離れるとなると、そうあってはいけないと思いつつ、勤労意欲が萎(な)えていくのを杉井は感じていた。
十月になると、連隊区司令部から「所属は名古屋野砲兵第三連隊、入営日は昭和十四年一月十日」との通知があった。自分の帰属する組織が決まって、杉井は身の引き締まる思いがしたが、連隊とはどのようなものかについては、全く想像がつかなかった。
学校の修学旅行以外旅行らしい旅行もしたことがなかった杉井は、名古屋が如何なるところかを知らなかったし、初めて親もとを離れる生活にも期待と不安の混在するものを感じた。
一ヶ月ほど経つと、親戚知人から「祝入営杉井謙一君」と書かれた約八メートルの「のぼり」が送られてきた。その数も全部で二十三本となり、杉井家は家の前に十メートルの柵を作り、柵に竹竿を縛りつけて「のぼり」を立てた。
毎朝この「のぼり」を上げ、夕方になって下ろすのは杉井と弟たちの日課となった。数が数だけに、突然雨が降って急いで下ろすのは大仕事だった。二十三本の「のぼり」が並ぶ様は壮観であり、謙造は毎朝機嫌良くこれを見上げていた。
杉井はどうかといえば、まずこれだけ大仰に祝われることが照れくさかった。謙造から、
「これだけお祝いをしてもらえるお前は本当に幸せ者だ」
と言われても、何もしていないのに祝福されるのは何故かという疑問がまず先に立った。
学校の入学にしても、第一志望を失敗して第二志望に進む時でも周囲はおめでとうと言うし、就職もとにかくどこかに決まりさえすれば、周囲はお祝いを持ってくることを考えれば、この入営祝いもある種、ルール化された祝福かも知れないと杉井は思った。
更に、このルール化された祝福というのは、むしろ本人が幸福でない場合に行われることの方が多いのではないかとも考えた。
十二月に入ると母方の杉井家と父方の八田家がそれぞれ親戚一同で盛大に送別会を催してくれた。杉井家の送別会は伯父の杉井辰之助の主催で、「佐の梅」で開かれた。たえの兄弟が多いせいもあって二十六名参加の大宴会で、芸者も七、八名侍った。
この種の宴会で杉井は常に自分の持つ問題点の一つに直面する。それは酒が飲めないことである。小さな盃でまず一杯飲むとそれだけで背中にゾクッと悪寒が走る。概ね四、五杯が限界で、それだけ飲むともう食べられない。
それを超えるとまず百パーセントの確率で嘔吐した。親戚も杉井が飲めないことは承知しているので無理強いはしないと思ったが、さすがに自分の送別会となれば勧められた盃をそう無下に断ることもできないだろうと、杉井も覚悟を決めて臨んだ。