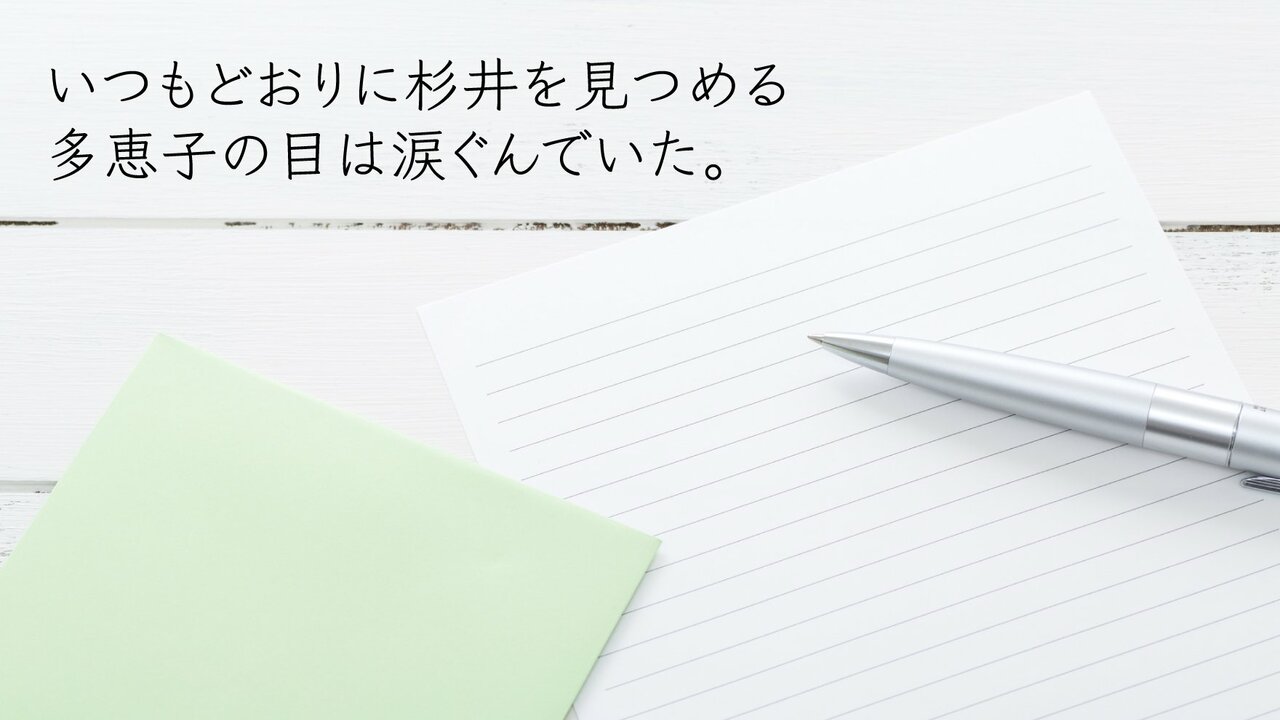主賓席に座る杉井に、志郎という男名の源氏名の芸者が侍った。細面の美しい芸者で、薄く塗った白粉に深紅の口紅が鮮やかだった。化粧を施した女性の年齢は杉井にはほとんど推測不能だったが、ひょっとしたら同い年ぐらいかなと思いつつ、杉井はその白いうなじをながめていた。
志郎が、
「おひとつ」
と、とっくりを傾けるので、杉井は正直に、
「すみません。自分は飲めないので」
と答えた。志郎はとっくりを持った手を少し引き、目を大きく見開いて、首をちょっと傾けながら、
「まあ……。それではお料理を召し上がって下さい。お酒の方は形だけ」
と言って、小さな盃に三分ほど注いだ。
宴が進むと、案の定、親戚が一人一人杉井のところへ来ては酒を勧めた。杉井は口だけつけて膳の上に盃を置いたが、志郎は、人の目が離れたと思うと、杉井の盃の中の酒をそっと膳の下の灰皿に移してくれた。人の気遣いにはいろいろあるが、今日この瞬間において自分にとってこれほど有難い気遣いはないと、杉井は素直に感謝した。
やがて母たえの兄弟の末っ子の安治叔父が杉井の席の前にどっかと座った。志郎がこぼしてくれたおかげで空になっている盃を見て、
「謙一、今日は頑張って飲んでいるじゃないか」
と、酒を勧めた。
「ええ、まあ」
と酌を受けながら、安治が最も歳も近く、日頃から気楽に話せる叔父だったこともあり、杉井は、配属決定以来感じてきた疑問を吐露した。
「本当に身に余る送別会ですが、これほどのことをしていただくようなことでしょうか」
「そんなことを言うものではない。お前の一世一代の晴れ舞台じゃないか」
安治叔父の認識も他の親戚と異なるところはないなと杉井は思ったが、なお言葉を継いだ。
「しかし、私はまだ何をした訳でもありませんし、おめでとうと祝福されても、そんなに名誉なことかなと……」
「これはお前がこれから打ち立ててくる数多くの名誉の前祝いだ。せいぜい頑張ってお国のためにすべてを捧げてくるんだぞ」
安治はそう言って、どんと杉井の肩をたたいた。