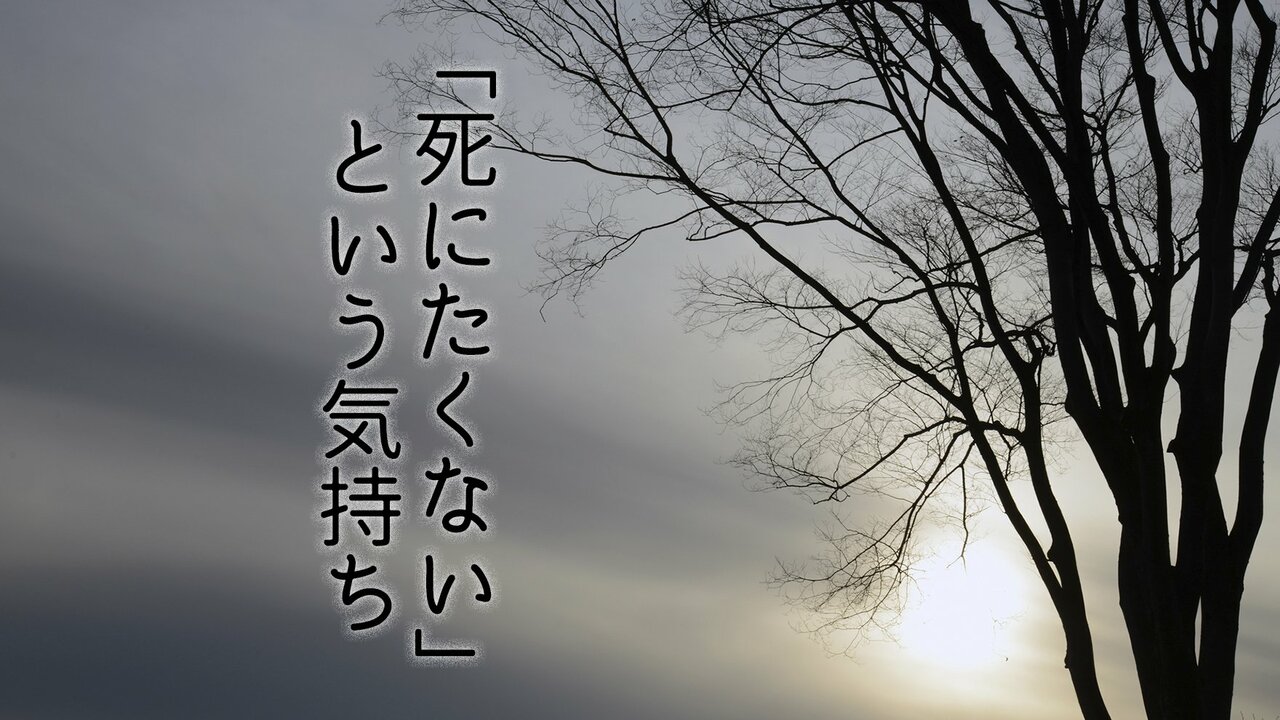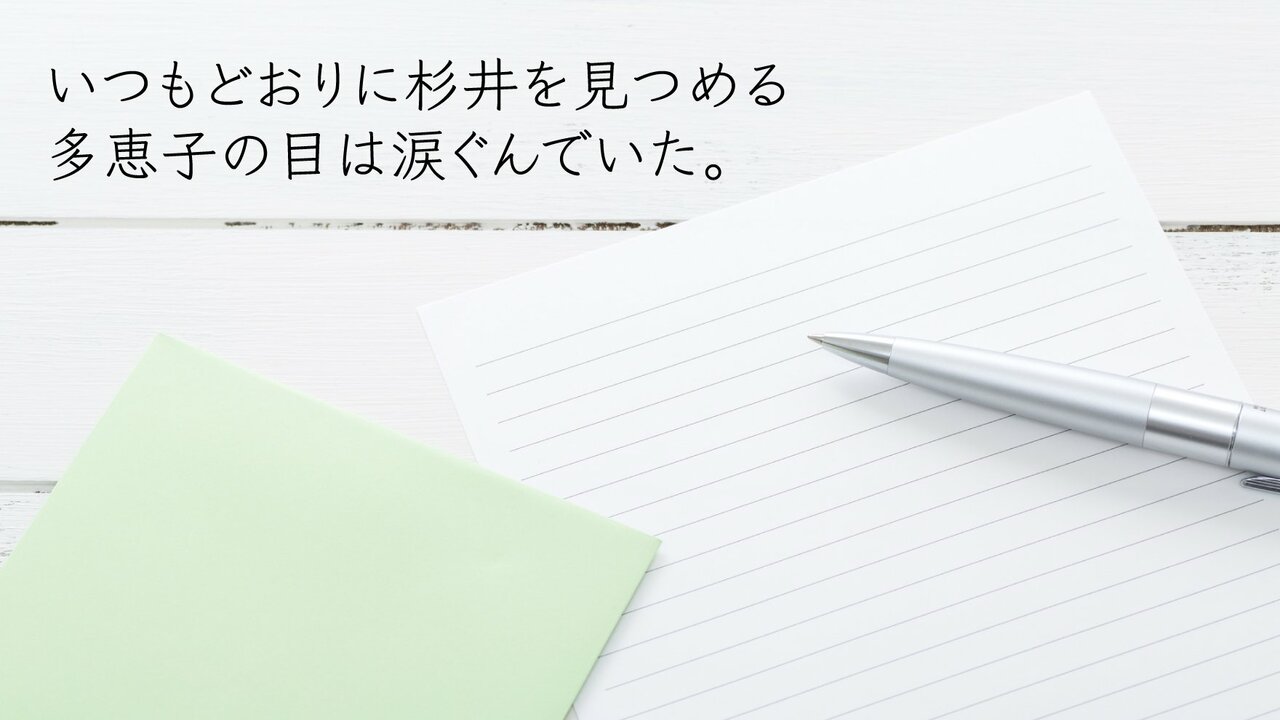第一章 新兵
壮行
八田家の送別会は謙造の長兄の喜一の主催で「旧交亭」で開かれた。前回同様、杉井は主賓席にちょこんと座らされ、周りで伯父たちがご機嫌で盃を上げているのを、努めて明るい表情を作りながら、眺めていた。
酒の飲めない杉井は、当然のことながら宴が進んだからといって酔う訳でもなく、学生の頃勉強が一段落した時によくやっていたように、雑然とした思考を繰り返していた。もとよりこの種の宴会には名目が必要だ。
年の瀬になれば忘年会と称して皆で飲むが、忘年会の最中にその年のことを忘れようと必死で試みている者などいない。盛夏になれば今度は暑気払いと称して飲むが、暑気を払うどころか、皆飲み過ぎて真っ赤な顔をしてフーフー言いながら帰って行く。
元来人間というものは何の名目もなしに飲むことに若干の躊躇を感じる動物なのかも知れない。その意味で「入営祝い」という格好の名目を提供し得た自分は、その限りで、今こうして飲んでいる面々には大いなる存在価値となり得ているのかも知れない。
退屈しのぎにそんなことを考えていると、謙造の弟の幸作叔父が酌に来た。幸作は、幼い頃杉井をよく映画に連れていった思い出などをひとしきり語った後、急に真顔になって言った。
「謙一、決して死ぬなよ。自分から危険を買ってでるな。お前は長男だから必ず生きて帰って来るのだぞ」
幸作の発言はこれまでどの親戚からもなかったものだった。血のつながった甥に対する有難い言葉であると、杉井は、積極的に感謝の念を持たなくてはいけないと思った。同時に、杉井は自分の死の可能性の存在を初めて認識した。
徴兵検査から入営に至るまで、誰にも同じように適用される一連の手続きに漠然と乗ってきた杉井だったが、幸作の言葉を聞いて、自分にとっての修羅場が確実に近づいて来ているという、何故か苦痛を伴わない恐怖感を覚えた。
十二月三十日、杉井の家は、新年に備えての事務所と工場の大掃除だった。朝から従業員総出で取り組んだ結果、夕方には大体の目鼻がついたため、杉井は佐知子に会いに行った。
この日、佐知子の姿は倉庫になかったが、谷川の従業員の浜名が、
「謙一さん、佐知子さんなら二階にいますよ。今呼んできましょう」
と、佐知子を連れてきてくれた。
「今年のお仕事はもうおしまい?」
いつもの元気な佐知子だった。
「今日は朝早くから大掃除だったんだけど、今さっき大体片づいてね。明日は帳簿の整理があるけど午前中には終わるだろうから、午後はおふくろの買い出しの手伝いかな」
「うちも今日で仕事は終わり。お正月の準備が全然できてないから、明日はお母さんとおせち作り」
「佐っちの作るおせち料理なんてぞっとしないな」
「失礼しちゃう。見たこともないくせに。でも本当を言うと、おなますや黒豆やきんとんはやっぱりお母さんの方が上手。私はお野菜を炊いたり、お魚を煮しめたりが役目」
「そんなの特におせち料理じゃないじゃないか」
「おせち料理って何もだし巻きとかごまめとか決まったものでなくっちゃいけないってことないのよ。日持ちのするものでお正月三が日食べられるものなら何だっておせち。それにお料理だっていろいろ種類があっていろどりが良い方がいいでしょ」
「そう言われてみればそのとおりだけど」