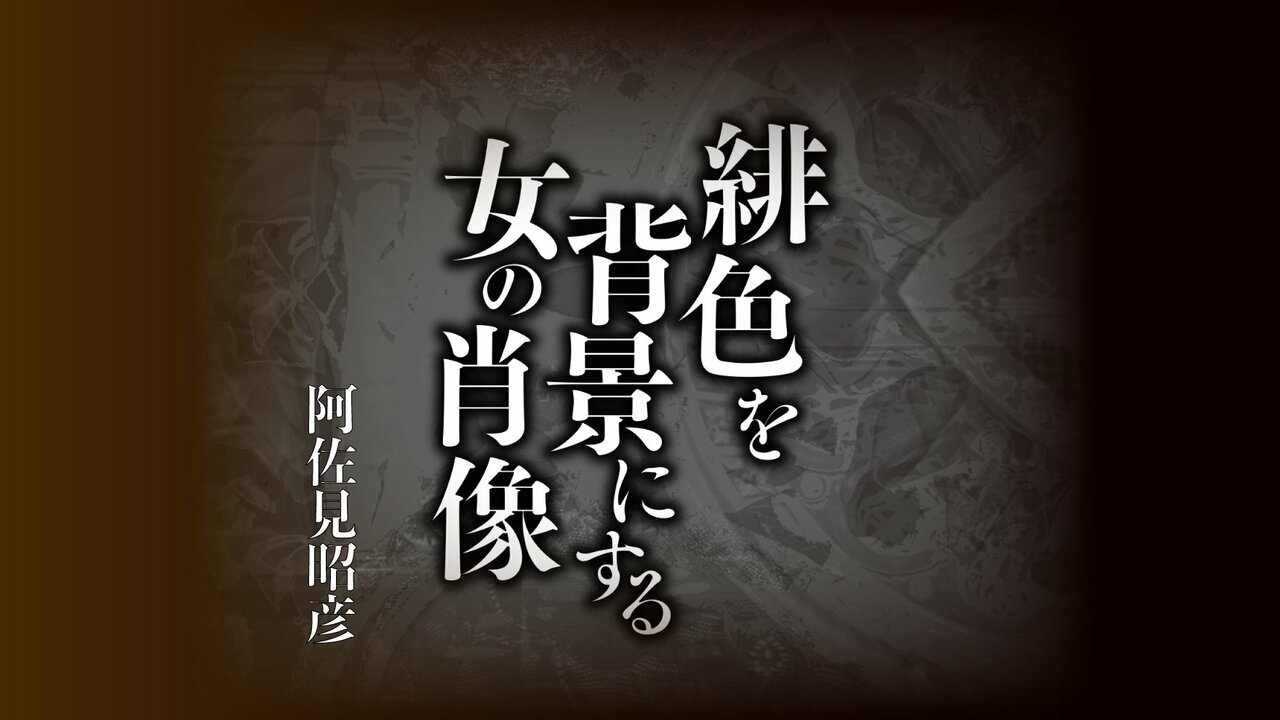5
バーテンダーに注文したドライ・マティーニ入りのグラスを携えて進むと、装飾的なデザインの銘版がその開口部の上枠に取り付けられている。《男爵のサロン》と書かれていたのだが、カジノに縁のある、爵位を持つ人物を記念するメモリアル・ルームのようである。
足を踏み入れると、そこは高い天井を持つ正方形の部屋だった。白い石膏塗りで仕上げられた天井の中央には、不釣合と思えるほど大きいクリスタル・ガラスのシャンデリアが吊り下げられている。無数の明るい煌めきに織り成された光模様が、まるで万華鏡のように真紅の床に投影されている。
先ほどの廊下に敷かれた赤い絨毯の表面に見えていた艶やかな模様は、このシャンデリアの反射光だったらしい。部屋はカジノの喧騒から離れ、アルコールなどを飲みながら休憩するためのサロンとして供されているようだった。
暖炉のある正面と右の壁側に、猫足のついたロココ・スタイルのカウチと小椅子が、それぞれ三組ずつ、小さい楕円形のテーブルを挟みながら置かれていた。沈み込むほど深い毛足の絨毯の上を右に回り込むように進み、反対の壁を振り向いた宗像の歩みが突然止まった。
一瞬、身体が凍りついたように、二つの目が正面の壁に釘付けになった。それは、あまりにも突然といえば突然な出会いだった。ロープ・スタンドで隔てられた正面の壁には、スポット・ライトに煌々と照らされて五十号ほどの油絵が飾られていたのである。
「この絵は……何と、ピエトロ・フェラーラではないか!」