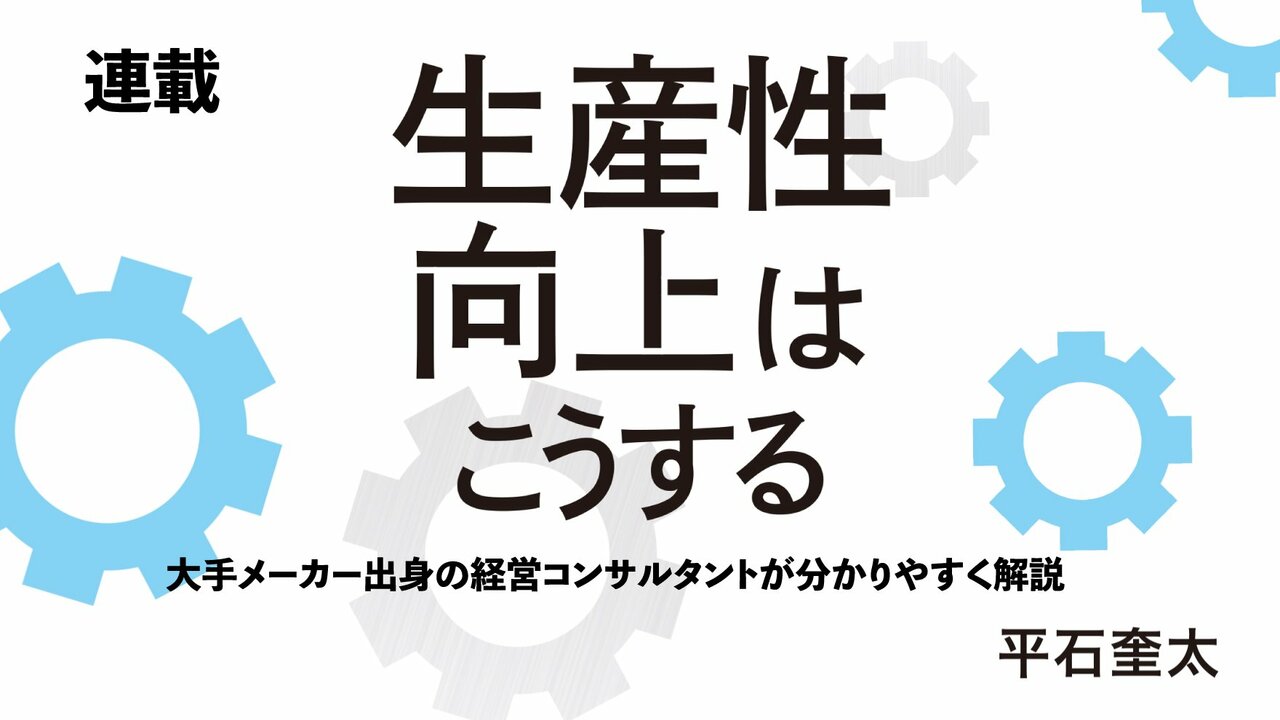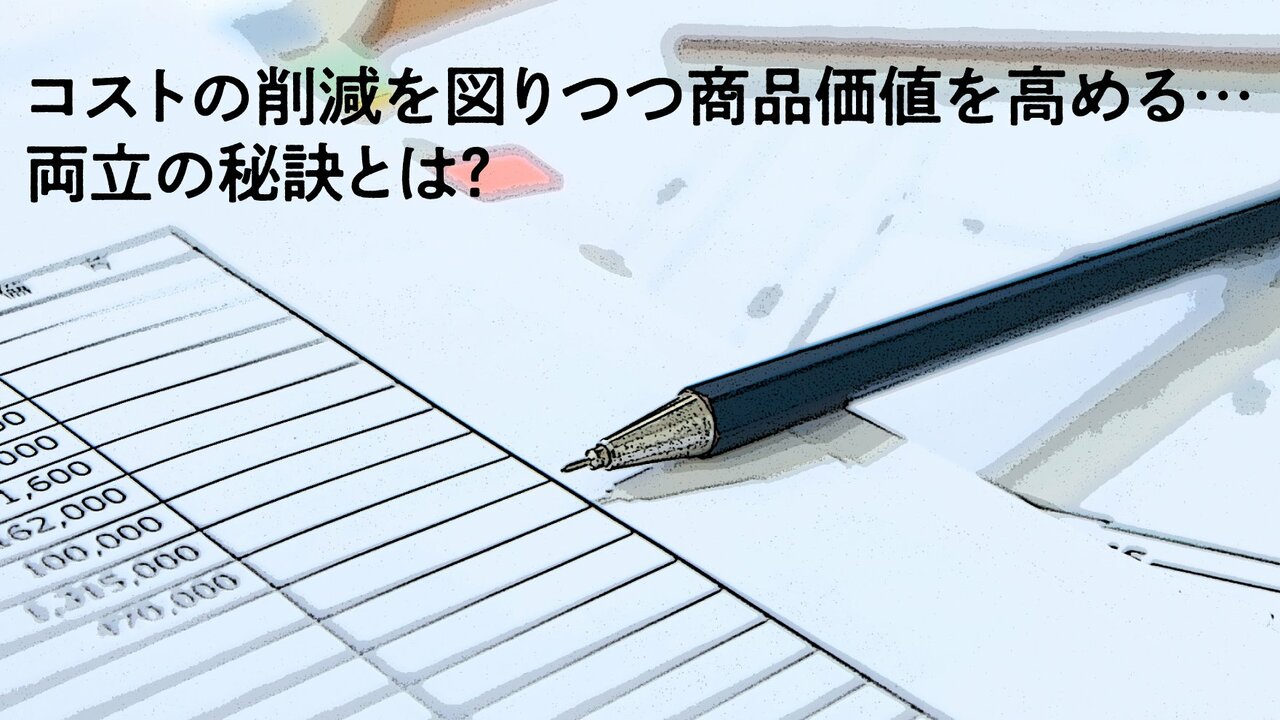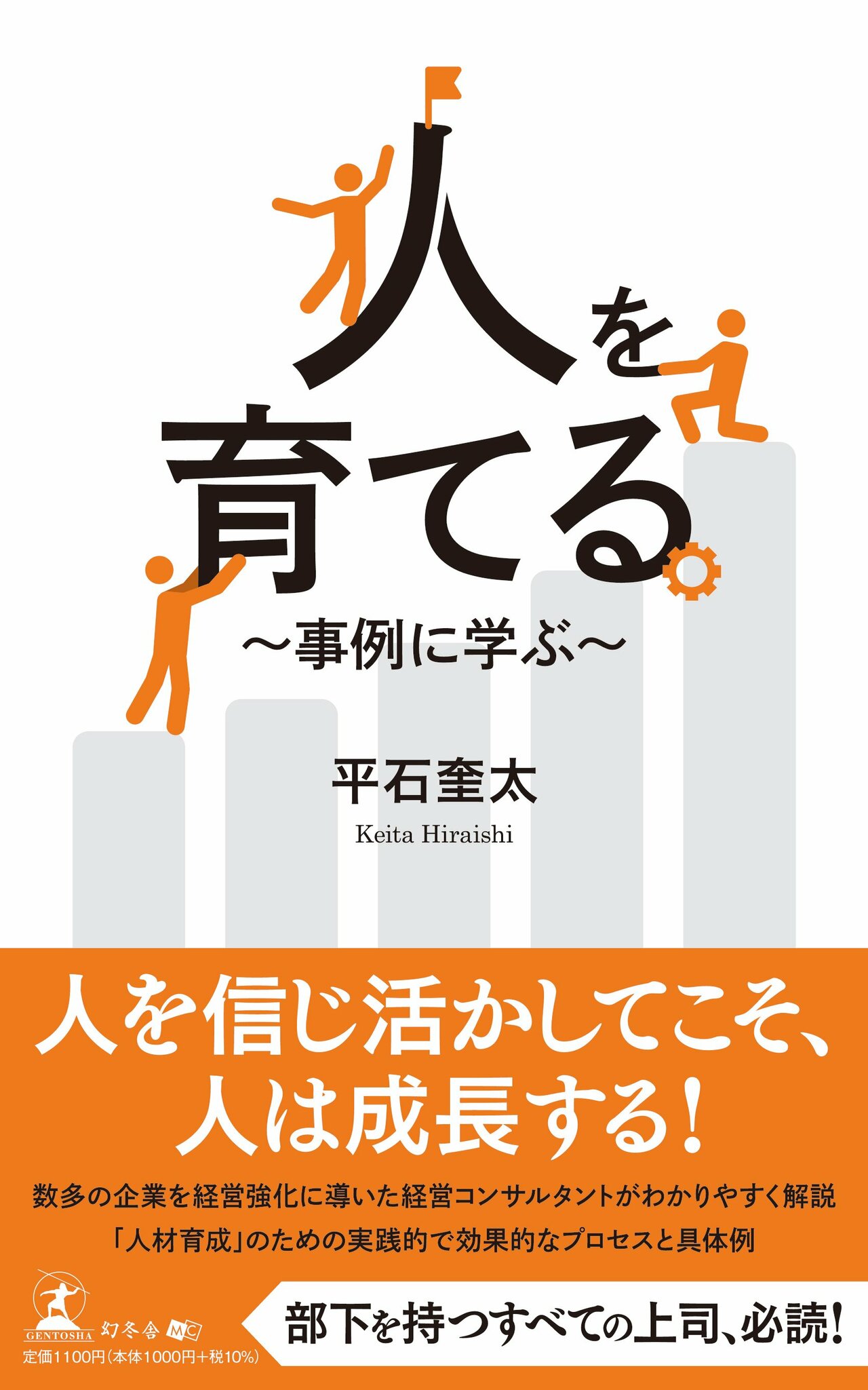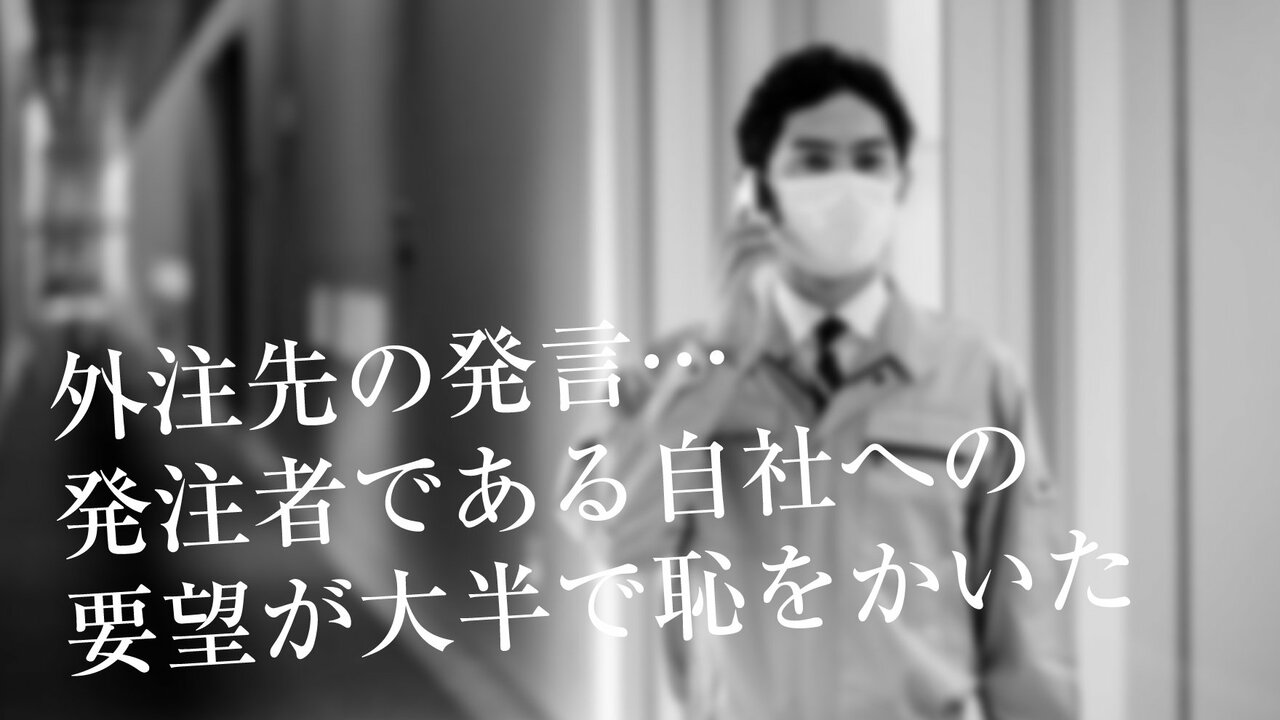「変動費」の改善 設計主導のコストダウン
設計主導のコストダウンの事例として私自身の経験を読者のご参考に供したいと思います。
1、コストダウンのプロジェクトチームをスタートさせる
既に試作設計・技術試作を終えた時点からのスタートで、果たして十分な成果を上げうるか、又6ヶ月後に迫った発売時期に間に合わせられるか不安を抱えてのスタートでした。
先ずチーム構成を次に記します。
1)チームの構成
チームは「実行推進委員会」と「プロジェクトチーム」から構成されました。
①「実行推進委員会」
・推進委員長 事業部長
・副推進委員長 副事業部長
・推進委員 関係各部部長8名
2)「プロジェクトチーム」
・統括リーダー 技術部長
・事務局 原価管理課長他 1名
①企画チーム
技術部 6名
生産技術部 1名
製造部 4名
資材部、原価管理課、品質保証部、業務部 各1名
デザイン部 1名
合計 16名
②実行チーム
技術部 6名
生産技術部、資材部、原価管理課、品質保証部 各1名
製造部 0名
合計 10名
2、組織の壁を越えて、全部門・全員参加の体勢(C・F・T)をつくる
商品のコストは設計で70%が決まるといわれています。それだけに設計部門の役割は大変大きいということが出来ます。然し、設計図が完成してから実際に商品を生産開始するまでには現場各部門の協力が必要です。
現場では材料事情、生産技術、設備などなど、量産開始までに解決すべき問題や課題が数多く生じます。そして当然のことながらそれらの後工程も、コストに大きくかかわっています。
それら設計に続く後工程の意見を、予め設計時に取り入れることができれば大きなコストダウンの成果が得られます。組織の壁を越えた全部門参加の活動がコストダウンに大変有効なゆえんです。
ところが、現実には思い通りには行かないことが多いのではないでしょうか。
コストを追究するあまり品質がおろそかになったり、人や設備など製造現場の事情を理解しない設計では不当に造りにくくなったりします。往々にして部門間で利害が対立して、設計部門対製造部門などといった部門間の争いが生じたり不信感が生じたりしています。
このプロジェクトでもスタートに当たり2つの問題に対処することになりました。
第1は、デザイン部を参加させたことです。
私はコストダウンの目標は思い切って大きなものを設定してほしいと思っていました。大きな目標を掲げて限界に挑戦するのでなければ、真に価値ある成果は生まれないからです。