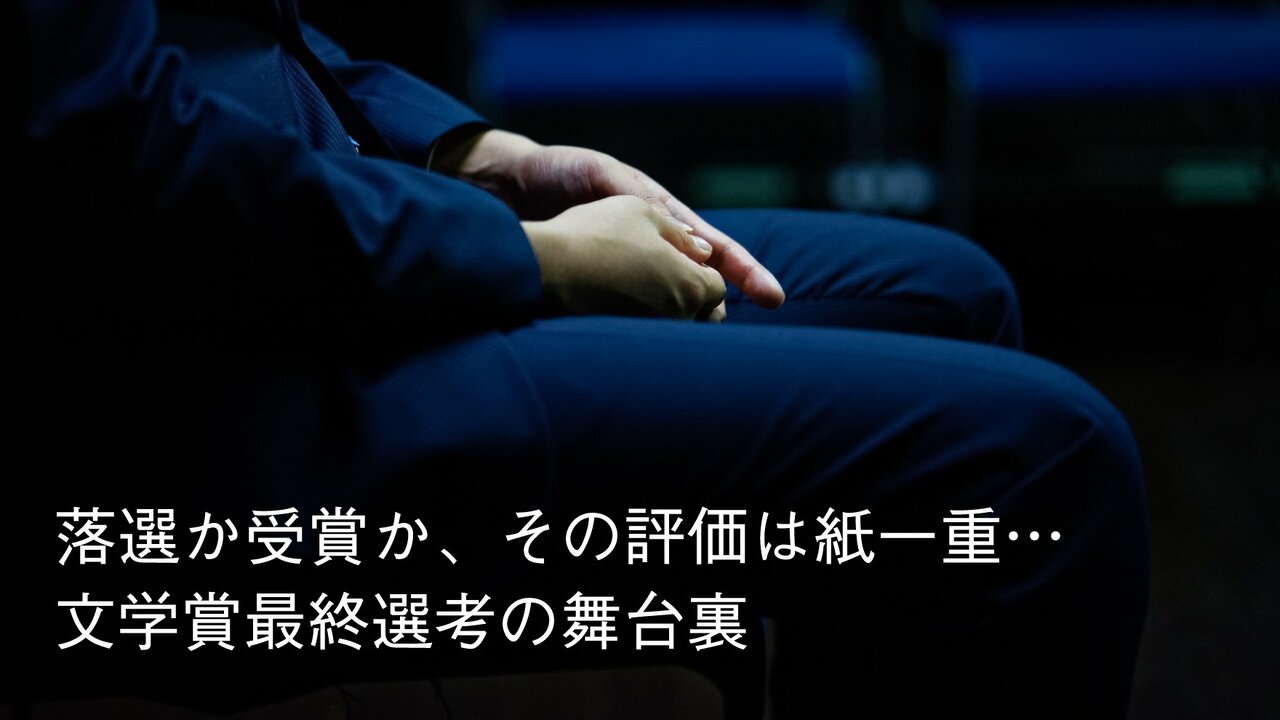ライジング・スター
「あ、いえ、葭葉出版はコスモTVと並んで第一志望です。幸いコスモTVが落としてくれたので葭葉一本に絞れて……。お蔭様でお世話になることができて本当に幸せです。島崎部長にもお会いすることができたしぃ。人間万事塞翁が馬ですね」
「それはこんなときに使う諺(ことわざ)かい。調子のいいやつだ」
爆笑につつまれた。西脇美和は華やぎと場を和ませる雰囲気を持っている。飛びぬけた美人というわけではないが、男好きのする独特の愛嬌を滲ませている。
「確かにコスモTVさんのように高給でないことは認める」
島崎が言った。
「でも将来性は抜群だぞ。なにしろ愛澤先生という強い味方がいるからね」
「本当ですよ。愛澤先生、よろしくお願いしますぅ」
「うーん、西脇くんにそう言われると頑張ろうという気分になるよ。でも、本当にそう思うなら原稿料を上げてくれないと。いつ他社に浮気するか分からないですよ。島崎さん」
「脅かさないでくださいよ。うちは愛澤先生だけが頼りなのですから」
島崎の、大げさに肩をすぼめて懇願する仕草が笑いを誘った。そつなく、すきなく、かといって相手に警戒感を与えない島崎の所作から、相当なやり手編集者であることは想像できた。それにしても川島の、早くも大作家然とした態度が鼻につく。
「まあ、すっかり大作家ね」
理津子が少し皮肉を込めて言った。
「でも、流行作家の世界も浮き沈みが激しいから油断しないでね。売れなくなると出版社も手のひらを返したように冷たいわよ。テレビの世界も同じだけど」
島崎が慌ててかぶりを振った。
「ご忠告ありがとう。でも、はっきり言って『わたし』には無縁のことだと思うよ。あの人は今、みたいな落ち目のタレントのようにはならないよ」
川島は、これまで使っていた「俺」でも「僕」でもなく、自分のことを「わたし」と称した。
「たいした自信ね。サークルの頃から自信家だったけどますます拍車がかかっているわね。その自信はどこから湧いてくるの?」
「頭の中の泉かな」
「泉?」
「そう。自信の泉ではなく発想の泉。何ていうか、その泉から自然と構想が湧き出てくるんだ」
「ふーん。発想の泉ねえ。確かにサークル時代も多作ぶりは際立っていたわね。あり得ることね」
理津子は、妙に納得した顔になった。