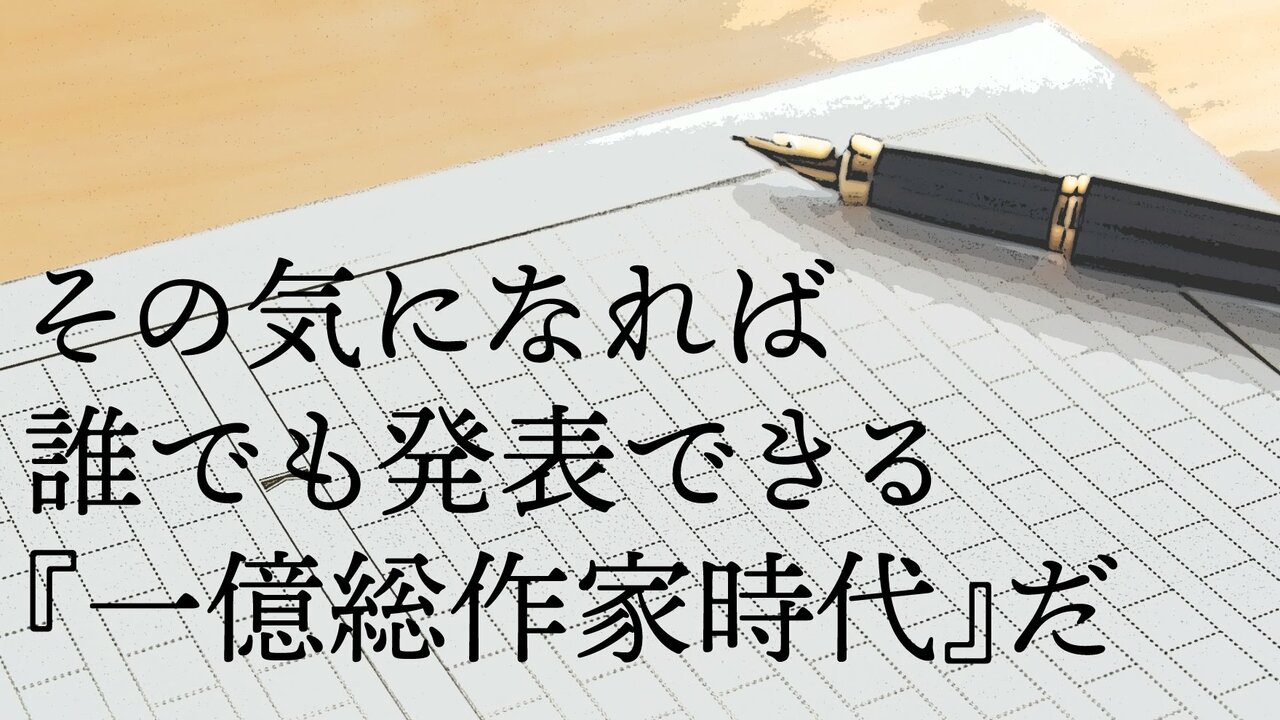ライジング・スター
川島は拍手を浴びながらゆっくりと、しかし堂々とした足取りで中央に進んだ。そして参加者に向き直り、深々とお辞儀をした。割れんばかりの拍手とかけ声が会場を支配する。
「皆様、盛大な拍手をありがとうございます。予定では改めて拍手をお願いする場面でしたが、どうやら不用のものとなりました。わたしも文壇パーティーの司会は幾度もお引き受けいたしましたが、本日のような熱狂的なオープニングは経験がございません」
ようやく静まりかかったところで、司会が言葉を継いだ。
「それでは、これから乾杯に移らせていただきます。乾杯のご発声を、全日本ペンクラブ会長の美倉文夫先生にお願いしております。美倉先生、よろしくお願いいたします」
「美倉文夫が乾杯の音頭とは、たいしたものね」
「これで川島も正式に文壇の仲間入りかい」
「まあ、そういうことね」
祝辞が次々と披露され、パーティーは滞りなく進んでいる。談笑の輪が、うず潮の如くそこかしこに見渡せる。理津子はメディアに身を置くだけあって、その輪をあちこち移動しながら挨拶に廻(まわ)っている。
俺はただ黙々とグラスを口に運ぶ以外、この場に相応(ふさわ)しい振舞いは思い浮かばなかった。
「ひとまず営業活動は小休止」
理津子が戻ってきた。
「精力的だね」
「今の仕事のためというより将来のためよ。ちょっとしたコネクションがいざというときに役立つこともあるわ。コスモTVの看板を使えるうちに自分を売り込んでおかなくちゃ。芹生くんもせっかくの機会を活かさないと。紹介するからいっしょに廻ろう」
「遠慮するよ。名刺も持っていないし」
「名刺なんていらないわよ。どうせ、ほとんどはすぐに捨てられるんだから。顔を覚えてもらうのよ。さあ」
そこへ川島が現れた。
「やあやあ、お二人さん。ここにいたのかい」
一年ぶりの川島は、タキシード姿もあって煌びやかに見える。今の彼が別の世界の住人であることだけは峻別(しゅんべつ)できた。
「想像以上に派手なパーティーね」
理津子が口を開いた。
「それにそのコスチューム。まるでタレント並みね」
「ありがとう。でも、それは皮肉だね」
川島は余裕の笑みを浮かべながら言った。