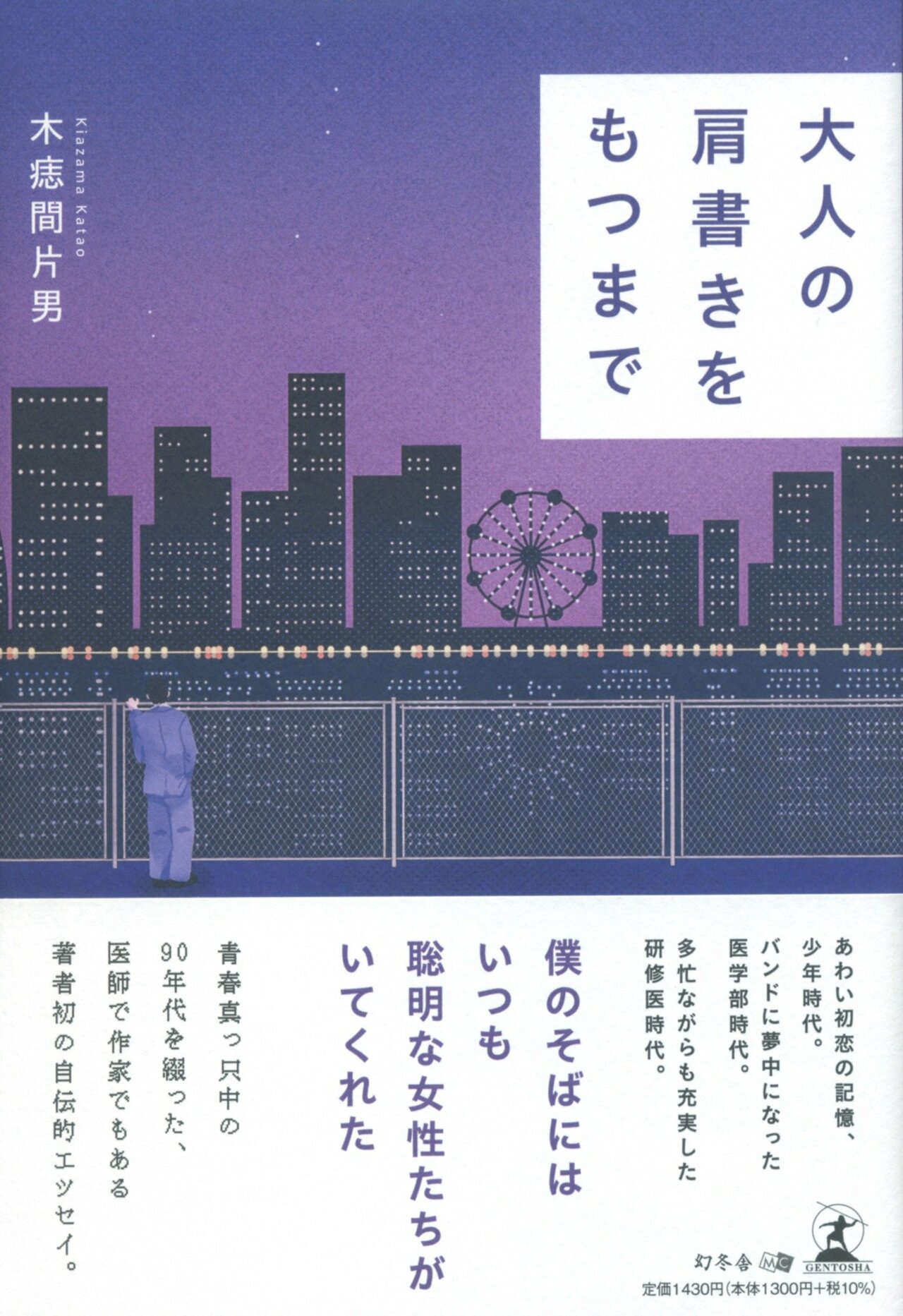*
すべての受験に失敗し、あえなく浪人生活に突入したなかで、ある日彼女と再会した。同級生だった“インドア派芸術女子”の大川朋子だ。それは地元と東京とをつなぐ列車のなかだった。彼女は移動途中、僕は予備校をサボって帰宅するところだった。
いまでも目に焼き付いている。黄色と黒のバイカラーワンピにパテントレザーのパンプス、肩には大きなキャンバスバッグで、極めつけは、ほどよい長さに切り上げたワンレンのボブヘアーだった。メガネはかけていなかった。
なんて垢抜けたんだ……、そうか、美大生になったんだっけ。もともと長身でスタイルが良かっただけに、ちょっとしたモデル風にも見えた。
「ああっ、久しぶり……、な、なんか、ちょっと変わったね。美大に通っているって聞いているよ……」
とってつけた言葉をかけたような記憶がかすかにある。
「うん、まだまだはじまったばかりで勉強中だけどね……」
眩しいくらいモード系に変化した彼女に対して、「返しそびれていた『すくらっぷ・ブック』の最終巻が家にあるから今度返すよ」と、時間の止まったような昔話を打ち明けて、あわよくばもう一度会おうとする勇気は到底得られなかった。
ただ中学のあのとき、「木痣間くん、放課後も一緒にいたいからアタシと同じ学習塾に通ってよ」と声をかけてくれたことを、いまでも彼女は覚えているだろうか。