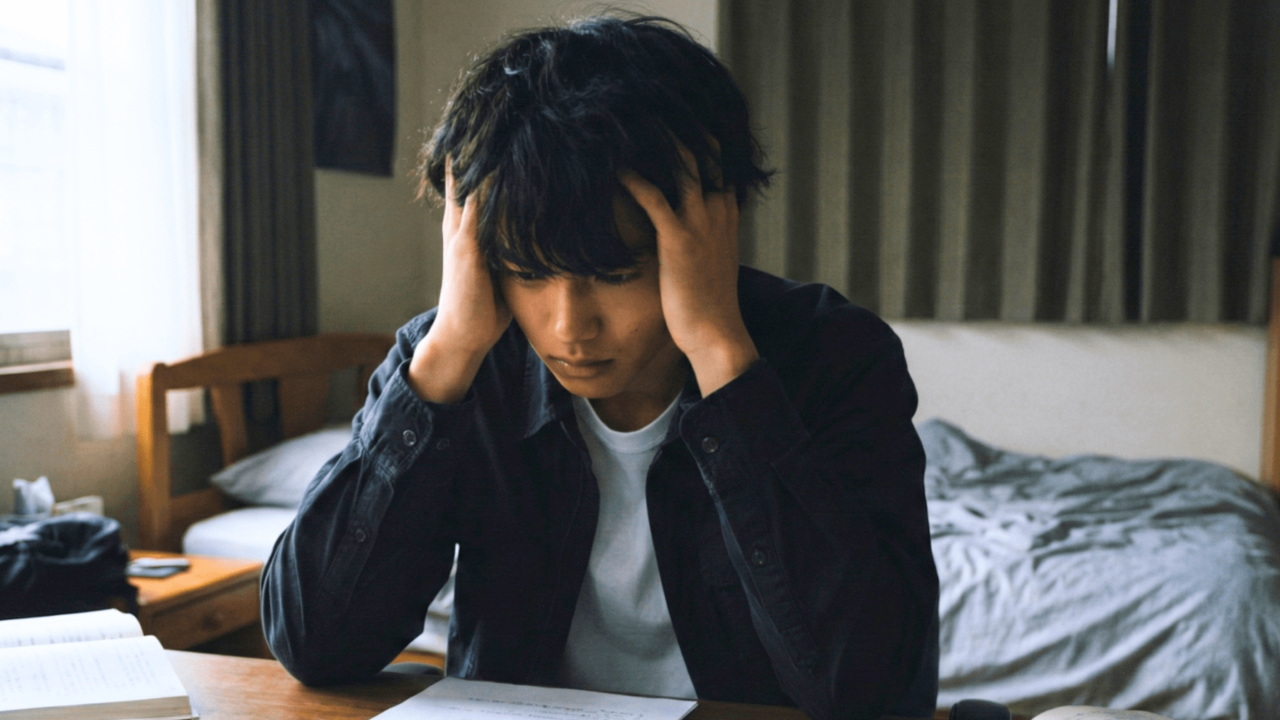「なーんちゃって」
「……は?」
「うそうそ、ごめんね。あなたが浮気なんてする度胸がないことくらい知ってるんだから」
つまりはアレか。からかわれたのか、俺は。十も年下の、結婚した当時はこれほど『幼妻』という言葉が似合う女は他にいないと思っていたほどの涼子に。全身の力が抜けた俺は足元がおぼつかなくなり、その場でたたらを踏んでしまった。それを涼子は腹を抱えて笑いながら見ている。
だが俺と違って目尻に笑い皺もできない。若いな、涼子。お前はまだ、死ぬには早すぎる。実のところ俺はまだ迷っていたんだ。俺だけじゃなく、息子の存在を消してまで神に抗うようなことをしていいのかと。
だがこれで決心がついた。俺はやはりこの笑顔を失いたくない。命を貰った涼子は独身時代に戻って俺じゃない誰かを恋人にし、また別の家庭を築くのかもしれない。それでもよかった。涼子が笑って幸せに生きてくれるのなら、その隣にいるのが俺じゃなくても構わない。
「涼子……。俺の妻でいてくれてありがとう。キミがいなければ、俺はとうの昔に潰れていた。本当に感謝している」
「え、な、なに急に? 変なものでも食べたの?」
俺が突然しんみりした雰囲気をまとったからか、涼子は目に見えてうろたえている。これはさすがに演技じゃないだろう。かと思うと涼子は何を企んでいるのか、俺の眼前に顔を突き出しておでことおでこを突き合わせた。
昔なら、それこそ俺が高校生くらいまでなら照れ臭くてすぐに離れただろうが、あいにくその程度でドギマギする年でもないんだ。
「風邪かと思ったけど熱はないわね。もしかして酔ってる? お酒飲んだ?」
「風邪もひいてないし酒も飲んでない。だから至って平常で平生だ」
「そういう理屈っぽいところを見ると……うん、納得。でもやっぱり変」
言いながら離れる涼子に、俺は半ば自棄になって「こんな日くらい変になったっていいだろ」と呟いた。それは口を滑らせたと言ったほうが正しいかもしれない。
「こんな日?」
「あ、いや……」
迂闊だった。今ので涼子は絶対に勘付いたに違いない。くそ、どうすれば誤魔化せる。凝り固まった頭でどうにか柔軟な発想を思い浮かべようとしたが、焦ると視野は狭くなるしロクなアイデアが浮かばない。浮かぶのは額の汗だけだ。
それがますます涼子の疑念を深めていったようで――
「やっぱりこんな場所であなたと二人っきりなんて変だと思ったのよ。私に……何かあったのね?」
「違う、何も起きてなんかいないよ。本当だ、信じてくれ」
「じゃあどうして私はここにいるの? 直前の記憶も無いし。その様子だとあなたは理由を知ってるんでしょ。ねぇ、説明してよ」
次回更新は2月7日(土)、11時の予定です。