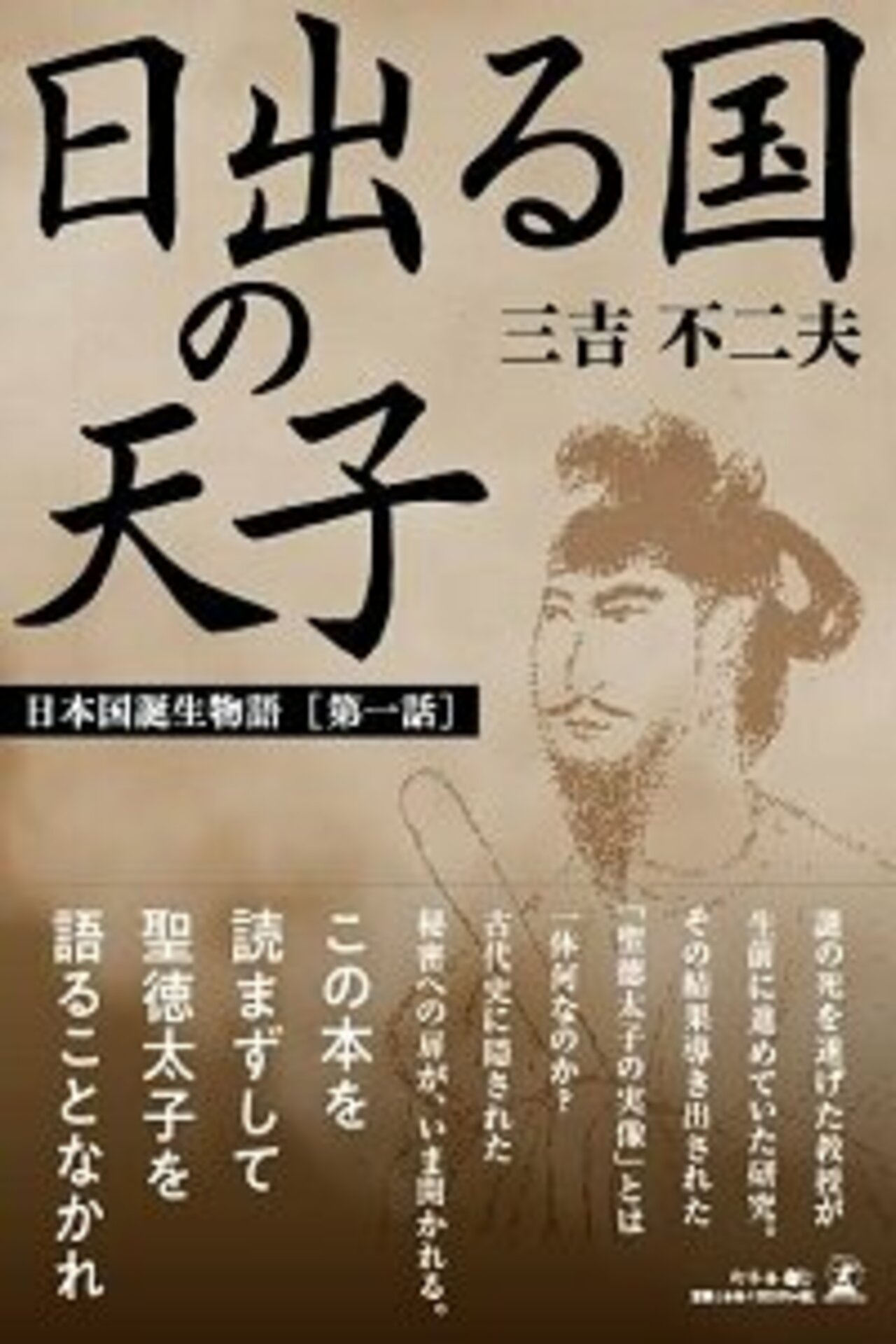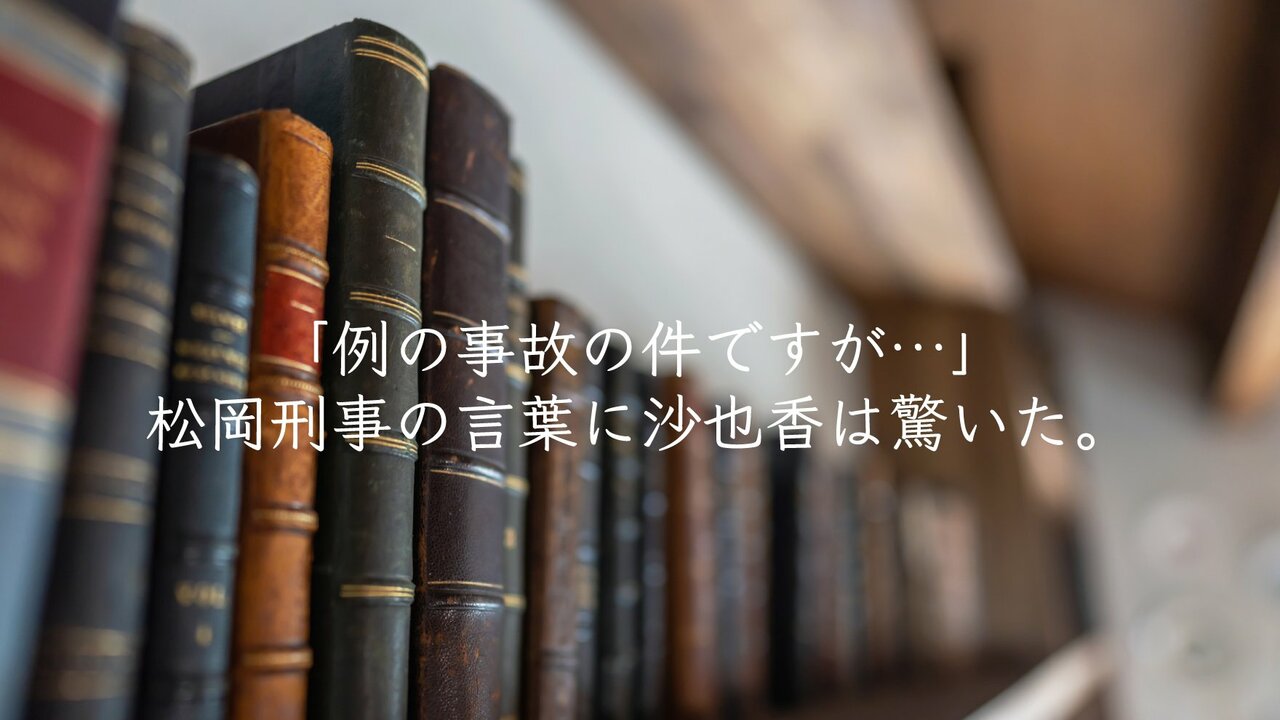第一章 ある教授の死
1
「そうです。高槻(たかつき)さんが亡くなられたのは、 間違いなく交通事故でした。そのことについては、なにも疑問をはさむ余地はありません」
「ではなぜ……」
「交通課の者が説明したと思いますが、高槻さんの車は首都高速を運転中、オーバーヒートを起こし、エンストして動かなくなってしまいました。やむなく故障車の標識を設置しようとして道路上を歩いていたところを、走ってきた乗用車にはねられたんです」
「ええ、そんなふうに聞きました」
「一方、加害者の車ですが、たまたま別の乗用車と並行して走っていまして、急カーブの道路上を被害者が歩いているのを発見したときは、もう目の前だったということです。急ブレーキをかけましたが間に合わず、はねてしまいました。でも一台だけで走っていたのなら、右にハンドルを切ってぎりぎりでかわせたかもしれませんが、悪いことにすぐ右の車線には車が走っていて、そちらにハンドルを切ることはできなかったんです」
「そうですか……運が悪かったんですね」
「そう考えるしかありませんね。しかも右の車線を走っていた車も高槻さんを発見して、あわてて急ブレーキをかけたといっています。もしそのままの速度で通過していたなら、加害者の車はハンドルを切ってかわせたかもしれない、といって悔やんでいました」
「そうですか。でもそんな場合は、誰でも急ブレーキをかけて止まろうとしますよね」
「それがふつうの神経でしょう。この運転者は非常に親切ないい方で、事故を見てすぐ停車して、後続の車に非常停止の合図を送って止めた上で、一一九番と一一〇番に通報して、被害者の救助にあたってくれています」
「でも助からなかったんですね」
「そうなんです。すぐ救急車が駆けつけて病院に搬送しました。病院では緊急手術をしようとしたのですが、すでに手遅れで、まもなく死亡が確認されたそうです」
「わかりました。でも、あの……」沙也香は 少し口ごもりながらいった。「最初の話に戻りますが、お話の限りでは、交通事故だったのに、なぜ捜査一課の方がおいでになっているのか、不思議に思っているのですが」
「ええ、そのことですよね」松岡は小さくうなずきながら答えた。「少し話がややこしいので、腰を落ち着けてゆっくりお話ししたいのですが」
つまり部屋に上がらせてほしいという意味だなと解釈して、
「ああ、気がつきませんで……。どうぞ、お上がりになってください」
といいながら、来客用のスリッパを出した。